
岩田太郎
米オープンAIが営利法人への転換を決め、200兆円超の投資計画を打ち出した。生成AIの「ChatGPT」で旋風を巻き起こした同社だが、その裏ではライバルの猛追を受け、サム・アルトマン最高経営責任者(CEO)が「コードレッド(緊急事態宣言)」を発出するほどの焦燥感に包まれている。生き残りのために狙いを定めたのは米政府の「AI国家戦略」だ。民間主導から政府との一体化へ――。AIブームの終焉を見据え、したたかに生き残りを図る同社の内情を浮き彫りにする。

AI(人工知能)には“貧富差”拡大の危険が伴う。米国では製造業回帰の雇用効果が薄い中、AIが富裕層を潤す一方で中間・若年層を直撃する懸念がある。AIがもたらす“分断の未来”をノーベル賞学者が読み解く。
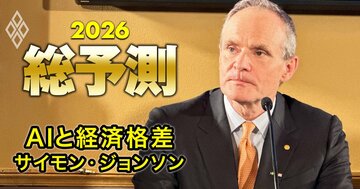
米トランプ政権が「法の支配」に挑戦している。緊急事態の拡大解釈や関税政策など、大統領の強権的な手法に対し、米最高裁や米議会が果たすべき役割は。憲法学の専門家にその行方と限界を聞いた。

巨額の投資マネーを飲み込む“AI(人工知能)ブーム”はいつまで続くのか――。2026年もAIへの巨額投資は続き、米国経済を牽引する可能性は高い。株式市場は、まさに「バブル」の様相を呈しているが、その持続性はいかほどか?米CNNテレビの著名司会者で国際問題評論家のファリード・ザカリア氏が、AIバブルの“賞味期限”と米AI産業の中長期的なリスクを指摘する。
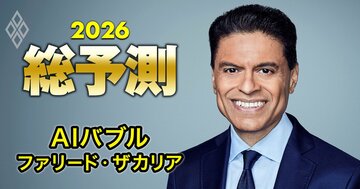
「リベラリズム(自由主義)は左右両派から邪魔者扱いされている」。レーガン氏、オバマ氏、バイデン氏の3人の米大統領に仕えた法学の権威、ハーバード大学のキャス・サンスティーン教授は米国の現状をそう分析する。個人の自由や法の支配はトランプ政権下で守られるのか。2026年11月の米中間選挙で勝利すると見られる党や、議会をも凌駕する大統領権限の実態について聞いた。

米トランプ政権がレアアース関連企業の株式購入を進めている。先端工業製品に欠かせないレアアースは中国が最大の産出国であり、米中通商摩擦の焦点になっている。安全保障の強化のための株買いでレアアース銘柄はバブルの様相を呈しているが、リスクも見え隠れする。

#4
低コスト・省エネルギーかつ高性能の生成AI(人工知能)であるディープシークや、電気自動車(EV)大手BYDのAI自動運転システム「天神之眼(神の目)」など、中国発の最先端テクノロジーに関するニュースが、米IT企業の株価やライバル間の競争の構図に小さくないインパクトを与える例が増えている。とりわけ注目されるのがxAIのイーロン・マスク氏がオープンAIのサム・アルトマン氏に仕掛けた場外戦だ。中国からの衝撃が、どのように米国内のAI開発競争を変え、さらに激化させているかを読み解く。

#1
中国発のベンチャー企業ディープシークが低コストかつ高性能の生成AI(人工知能)を開発したと発表し、世界最先端のAI大国を自任してきた米国に大きな衝撃を与えている。ディープシークは、「弊社のAIのコストは、米競合のオープンAIの開発したチャットGPTの10分の1以下だが、性能はチャットGPTに匹敵する」と主張している。1月27日にはディープシークのAIが出現したことで、AIの性能を左右する半導体を製造する米エヌビディアの株価が17%も暴落。5890億ドル(約88兆円)もの時価総額が1日で吹き飛んだ。この日以来、ディープシークを巡るさまざまな報道が飛び交っているが、ディープシークのコストや能力がいくら優れていてもオープンAIに近づくことができない分野がある。本稿では、米国のサンクチュアリともいえる軍事向けのAI市場が急成長している実態をデータに基づいて明らかにする。

米航空宇宙軍需産業の名門ボーイングが、小型機「737MAX」、大型機「787」など複数の主力旅客機で相次いだ安全性の問題をはじめ、生産ラインの品質や労働問題のため経営危機に見舞われている。ボーイングは米最大手の輸出企業の一つに数えられ、米経済に推計で年間790億ドル(約12兆円)もの貢献をしている。直接的・間接的な雇用も全米50州の1万社で160万人に及び、同社の事業継続は国家レベルで重大な意味を持つ。日本もひとごとではない。三菱重工業や川崎重工業、富士重工業、IHI、ナブテスコなどの企業が777や787を中心とするボーイング機の主翼や胴体、エンジン部品などの製造、システムの開発、部品加工などの下請けとして重要な役割を担っているからだ。
