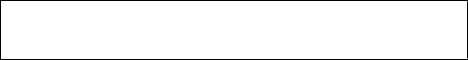東電の西澤俊夫社長(右)と機構の下河辺和彦運営委員長(中)、杉山武彦理事長は10月24日、枝野経産相に緊急特別事業計画を話した
東電の西澤俊夫社長(右)と機構の下河辺和彦運営委員長(中)、杉山武彦理事長は10月24日、枝野経産相に緊急特別事業計画を話したPhoto:JIJI
「原子力損害賠償支援機構の首脳らが描く東京電力の改革は、日産自動車のカルロス・ゴーン社長が実施したクロスファンクショナルチームを活用するイメージだ」とある政府関係者は説明する。
10月28日、東電と機構は、政府から福島第1原子力発電所の事故による損害賠償の資金援助を受けるための「緊急特別事業計画」を提出、11月上旬に枝野幸男経済産業相から認定を受ける見通しだ。
東電は資金援助を受ける代わりに、人員削減などの経営合理化や資産売却を進める。その一方、これらリストラ策の進捗状況を確認するために機構は、東電の首脳との「経営委員会」(仮称)を設置するほか、東電への機構職員の常駐を決定している。
彼らが経営合理化の実動部隊として考えられているのが、冒頭に挙げた“ゴーン方式”のような経営改革チームなのだという。
改革チームは機構職員のほか、東電社内の各部門から抜てきした若手社員中心で構成し、合理化テーマごとに複数グループを組織する。
社内の各部門と直接、意見交換しながら、年末をメドに工程表を含め、今後の具体的な改善策やアクションプランなどを作成する。そして、社内の状況や今後のリストラの進捗状況について、経営委員会に報告していく計画だ。
このような組織横断的な改革チームをつくる狙いは主に二つある。
一つは、「原子力村」という言葉に象徴される、東電の“たこつぼ化”した社内組織と慣例を破壊し、情報の伝達性と透明性を全社レベルで高めることだ。
ある関係者は「160ページもの損害賠償請求用書類を被害者に送り付ければ、通常なら被害者がどう思うか予想できたはず。明らかに狭い組織の中にいて、常識と想像力が欠如している傾向にある。社内の一部ではなく、会社全体で検討する仕組みづくりが必要だ」と説明する。
改革チームの狙いの二つ目は、若手社員を中心としたメンバーで構成することにより、リストラに対する抵抗感や閉塞感を緩和することだという。
すでに東電に対して、政府の第三者委員会が資産・財務の調査を実施しているが、機構では、これら改革チームの協力を得て、再度、東電の資産と財務の調査を行うことになっている。これら調査結果を基に、東電と機構は来年3月にも、より踏み込んだ「総合特別事業計画」を策定する予定だ。
日産は、外国人のゴーン社長というしがらみのない強力なリーダーの採用によって改革に成功した。はたして、東電の場合、どの程度の効果を出せるか。巨額の賠償を抱える東電は、政府の資金援助によって延命される。強力なリーダーが不在のなか、自ら血を流す努力を怠っては、国民の納得は得られないだろう。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 山本猛嗣)