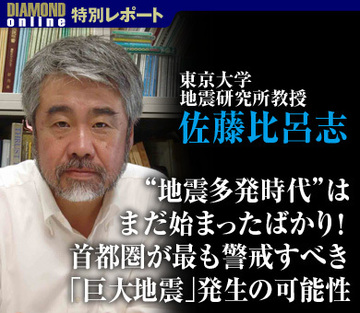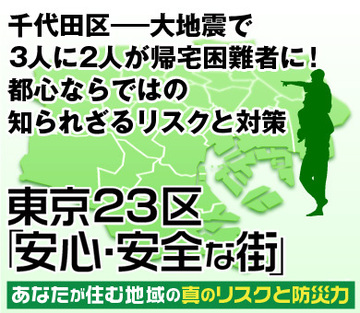「“教訓”がむしろ被害を大きくしてしまったのではないか」
東日本大震災により死者・行方不明者約1万9000人を出した東北沿岸エリアは、これまで幾度となく津波の甚大な被害を受けてきた。それにも関わらず、これほどの犠牲が出てしまった理由を防災アドバイザーの防災システム研究所・山村武彦所長はこう語る。
現在、マグニチュード7クラスの首都直下型地震が発生する確率について、政府の地震調査委員会は「今後30年以内に70%」、東京大学地震研究所が「4年以内に50%以下」と試算しているのは誰もが知るところ。東日本大震災時の混乱から落ち着きを取り戻したとはいえ、首都圏では大きな不安を抱える人が少なくないはずだ。
そうした状況を踏まえ、最近では東京都をはじめとした自治体や国、民間企業、そして個人が防災対策や訓練を始めた。しかし、果たして来たる大災害への備えとして十分といえるのだろうか。
50年前の津波、空振りの津波警報…
“直近の経験”に捉われる落とし穴
首都直下型地震に向けた防災対策や訓練の現状を検証する前に、東日本大震災で多くの犠牲者を出してしまった背景について改めて考えてみよう。
まず、冒頭で紹介した山村所長の「東日本大震災では“教訓”がむしろ被害を大きくしてしまった」とはどういう意味なのか。
東日本大震災の被害を受けた東北沿岸は津波常襲地域であり、『津波てんでんこ』、すなわち「津波が来たら血縁を絶やさないためにも、肉親にも構わず各自ばらばらに逃げろ」という教えや文化が根付いてきた。しかし、最近は科学技術の発達、例えば津波を防ぐ巨大防潮堤、緊急地震速報や津波警報などの“新しい文化”によって、“昔からの教え”が疎かにされてしまった面がある。
実際、2011年3月11日の2日前の9日に津波警報が出されていたが、これが空振りに終わり、さらに11日当日の地震直後の津波警報では、予想される津波の高さが宮城県で6メートル、岩手県と福島県で3メートルと発表されていた。そのため、人々の間には「どうせ大したことはないだろう」という意識が刷り込まれてしまい、津波警報が“オオカミ少年”になってしまった。こうした“直近の教訓”の積み重ねがあった中で、“想定外”ともいわれる大津波が襲い、多くの人々が犠牲になってしまった面も大きい。