東日本大震災から1年。首都直下型地震をはじめ次なる巨大地震の可能性も示唆され、国民に不安が広がるなか、我々現役世代は何を為すべきか。それは東日本大震災から得た教訓を、次世代へと確実に引き継ぎ、活かすことではないだろうか。そしてその役割はこの1年間、着実に果たされてきたと言えるのか。各分野の専門家へのインタビューと現地取材を交えたレポートで検証する。
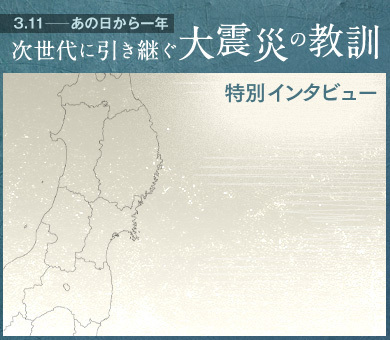
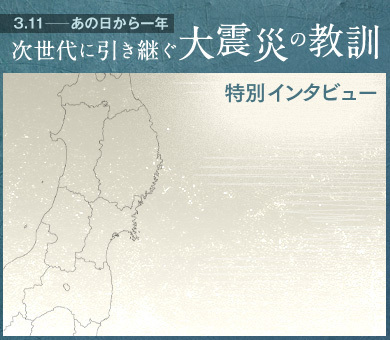
東日本大震災から1年。首都直下型地震をはじめ次なる巨大地震の可能性も示唆され、国民に不安が広がるなか、我々現役世代は何を為すべきか。それは東日本大震災から得た教訓を、次世代へと確実に引き継ぎ、活かすことではないだろうか。そしてその役割はこの1年間、着実に果たされてきたと言えるのか。各分野の専門家へのインタビューと現地取材を交えたレポートで検証する。