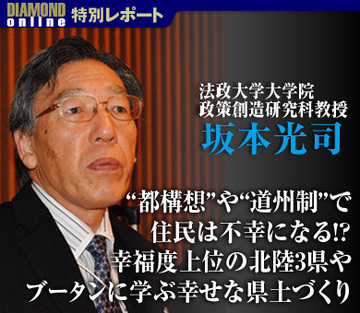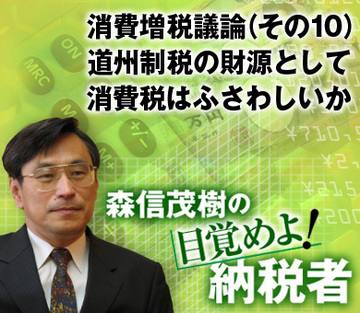「セントと言いますと――」
「都を移すことだ。平城遷都、平安遷都だ。昔、首都機能移転の話があっただろう。実際に準備室も出来たが、数年前に幕引きをしたものだ」
秘書は首をかしげながらも、やっと納得したようだ。
「首都移転を実際に行う上で必要な法的手続きは?」
「政府で法案として国会に提出して、衆参両院で過半数が得られれば成立かと思います」
総理は動きを止めて秘書を見た。
「その程度でいいのか」
憲法改正の場合は、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成と、さらに国民投票で過半数の賛成が必要だ。
「普通の法律ですから。それに、東京を首都にするという法的裏付けはないはずです。江戸から明治になって国会、議会、裁判所が東京に出来て、たまたま江戸城が皇居として使用出来、マスコミ、主要企業が集まり、自然と東京が日本の中心になった、と何かで読んだ記憶があります」
「こんな重要事項が、その程度のことで決められるのか――」
総理は再び考え込んだ。なんだ、首都とはその程度のことで決まるのか。拍子抜けした気もしたが、自分でもやり方によっては不可能ではない。
「ちょっといいですか──」
秘書の一人が遠慮がちな声を出した。総理がじろりと見た。
「現在、国交省に、首都移転チームが出来ています。総理が決裁しました。現在は、20人体制ですが、すでに動き出しています」
そうだ、たしかにそんな話があった。このどさくさで完全に忘れていたのだ。いや、頭のすみにはあったが、現実の重みで押しつぶされていたのだ。
「責任者は誰だ」
秘書たちは顔を見合わせている。誰も思い出せないのだ。
「至急調べて、呼んでくれ。出来れば今日会いたい」
総理は大声を出した。
「首都移転か。迫り来る巨大災害から逃れ、国民の意識を一新して、新たなる日本の夜明けを創造した偉大な宰相か」
総理は窓に向かって立った。窓ガラスには猫背気味の初老の男が立っている。ことさらに背筋を伸ばし、胸を張った。自分の名が後世に残り、孫たちが自分の名と写真を教科書で見る。悪くない、悪くないぞ。
「至急、首都移転の法的手続を内閣法制局に確認しろ。解散した首都機能移転準備室の全ての資料を集めろ。現在発足している首都移転チームのメンバーの資料を持ってこい」
総理は秘書たちに矢継ぎ早に指示を出しながらほくそ笑んだ。
横で官房長官が、唖然とした表情で立っている。
(つづく)
※本連載の内容は、すべてフィクションです。
※本連載は、毎週(月)(水)(金)に掲載いたします。