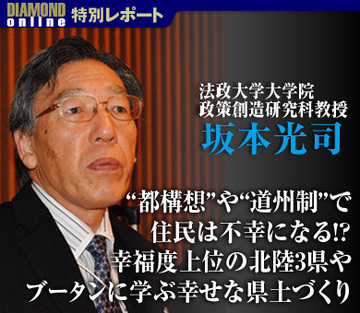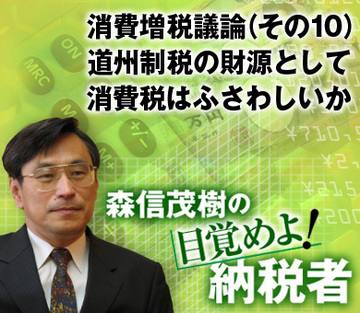「もう当分、地震はないだろう。東京の地下のエネルギーが解放されたんだ」
「お前はアメリカにいるときも、ウソをつくのが下手だった。誰かに言われたことはないか」
森嶋の脳裏に理沙の顔が浮かんだ。彼女も同じことを言っていた。
そういえば、理沙とロバートとはどこか似たところがある。なりふりかまわず突っ走り、挫折して酔いつぶれていたかと思えば、翌日には新しいことに夢中になっている。そして2人とも、強く陽気で楽天的だが、その性格の裏に妙な脆さと孤独を感じさせるのだ。
「お前のハイスクール時代の同級生で、ドクター高脇がいるだろ。東都大学理工学部で、地震を研究している准教授だ。いま、彼の論文がワシントンで話題になっている」
森嶋はかすかに息を吐いた。昨日、自分が苦労して読んだものに違いない。
やはりアメリカはすでにつかんでいるのだ。今回の地震が最後ではない。日本政府には、高脇が直接話しても反応が鈍かった論文だ。
しかし、ロバートの口から高脇の名が出たことは意外だった。驚くべき情報収集力だ。ひょっとしてアメリカ政府が高脇を──。ふっと浮かんだ考えを振り払った。そうであれば、ロバートが高脇の名を出すはずがない。
「その准教授が総理に会ったという情報も入っている」
「当然、彼が話した内容も知ってるんだろ」
ロバートは頷いた。そのとき同席したのは森嶋だということは知ってるのか。ロバートの表情からは読み取れない。
「きみが政府に提案した首都移転の話はどうなっている」
「それも知ってるんじゃないのか。俺以上に」
「国交省に新しく首都移転チームが出来て、元首都移転準備室室長だった村津真一郎が退官しているにもかかわらず呼び戻された。そして、森嶋真はその下で文句を言いながらも働いてるということくらいだ」
「それだけ知ってれば十分すぎる」
「細川優美子も一緒だろう。前に来たとき、お前のマンションに来た財務省の美人だ」
やはり知っていたのだ。これでは理沙や早苗のこと、殿塚とのことまで知っているのかもしれない。
森嶋はため息をついて口を閉じることにした。
30分後、森嶋とロバートは帝都ホテルのロビー内の喫茶室にいた。
2人は朝食を食べながらフロントを見ていた。
地震の前に優美子と来たことは言わなかった。だがひょっとして、すでに知っているのかもしれない。おそらく、ここに来た目的もあのときと同じだろう。
「あの男を知ってるか。いまロビーに入って来て、フロントに向かっている2人連れの男だ。それとなく見るんだぞ」
ロバートが身体を森嶋に近づけて言った。
(つづく)
※本連載の内容は、すべてフィクションです。
※本連載は、毎週(月)(水)(金)に掲載いたします。