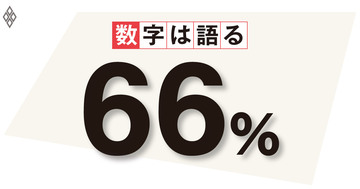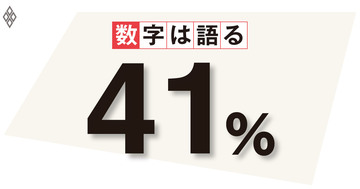1989~2018年の労働生産性上昇率
 (年率) 内閣府「国民経済計算」を基に就業者1人1時間当たりの実質GDP成長率を算出。2018年の総労働時間は筆者推計による
(年率) 内閣府「国民経済計算」を基に就業者1人1時間当たりの実質GDP成長率を算出。2018年の総労働時間は筆者推計による
平成が幕を閉じた。この30年間の日本経済を振り返り、低迷した時代だったといわれることが多い。しかし、意外かもしれないが、統計から見た平成の日本は「失われた30年」では決してなかった。
例えば、過去30年間の実質GDP(国内総生産)成長率はG7(主要7ヵ国)の中で2番目に低いが、これは週休2日制の導入や非正規雇用の拡大などで労働時間が減少したためである。就業者1人1時間当たりの実質GDP、つまり労働生産性は同期間で年率1.6%と、米国やドイツ並みに上昇した。直近10年間では同0.8%だが、日本を除くG7の平均を上回る。すなわち、平成の日本は主要先進国の中でも高い労働生産性上昇率を実現した。
家計消費額に見る生活水準も着実に向上した。2018年10~12月期の1人当たり実質家計消費額は、資産バブルの絶頂期だった1989年10~12月期のそれを3割上回る。「バブル期」と聞くと、世の中全体が楽観ムードに包まれ、高級品が飛ぶように売れたというイメージが強いが、現在の私たちはバブル期よりも豊かな生活を平均的には送っている。
半面、経済財政の持続性では深刻さを増している。その最たる要因は社会保障費の一部が赤字国債で賄われていることにあり、政府債務は対名目GDP比で上昇し続けている。
道路や橋などのインフラ整備は将来世代も便益を受けられるが、社会保障は現在世代に限られる。その対価として現在世代が負担すべき費用が、将来へ先送りされている。他方、デフレ下で日本銀行が実施した累次の金融緩和は国債の発行を容易にし、利払い費の増加を抑えている。こうした状況を家計に当てはめると、低金利のクレジットカードのリボルビング払いで、借金を増やしながら生活を維持しているようなものだ。
インフレが定着し、金利が正常化すれば、負担先送りの財政構造はいずれ維持できなくなる。令和の日本が「失われた時代」とならないよう、社会保障給付の重点化や、年齢ではなく負担能力に応じた負担の徹底などを進めるべきだ。
(大和総研シニアエコノミスト 神田慶司)