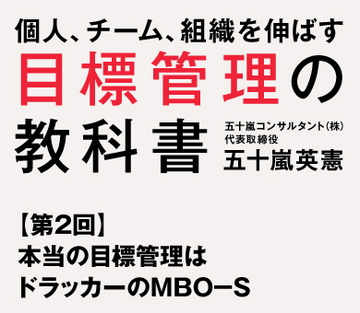本書には、意欲・能力・責任感のかけらも感じられなかった町工場の人たちが、潜在能力を発揮して、万年赤字の会社を黒字に転換したプロセスが克明に描かれています。
私は、この本をある所まで読んだとき、大変な感動を覚えました。そして、涙が止めどもなく溢れてきました。その箇所を引用します。
2月10日の午後、沢井は例によって現場を歩いていた。今では協力会社の社員たちも含めて、「おはよう」とか「ご苦労さん」という沢井の声に、ほとんどの人が笑顔で挨拶を返すようになっている。
だが200名余りの人びとのなかで、ところどころに返事もせず、いまだに沢井と言葉を交わしたことのない人が何人かいた。
人間いろいろだ。200人もいると私と肌が合わない人もいれば、なかには私を嫌っている人もいるかもしれない。あるいは無口な人、口下手で人と話すのが苦手な人もいるだろう――と沢井は考えていた。そういう人のそばへ行くと、黙々と仕事をしているその人の背中に「ご苦労さん」と声をかけて、返事を期待せずに沢井は通りすぎていく。
この日も、鋳造工場の造型の職場に来た沢井は、小林研三という作業員の背中に「ご苦労さん……」と声をかけて、そのまま通りすぎようとした。彼もまだ一度も話したことのない人の一人であった。
しゃがんで砂型の手入れをしていた小林が、慌てて立ち上がった。沢井はすでに数歩先へ行っている。小林の顔が緊張し、真っ赤になった。工場内の騒音を突き破って、小林が大きな声を出した。
「社長!」
沢井の背中がビクッとして、止まった。ゆっくりふり返った沢井の前へ、小林が近づいた。
「小林君か。どうした。何かね」
「あのう……う、オレ、あんたの本を読んだよ」
「え、私の本を……」
「うん、この間の日曜日、用事で駅前へ出て、本屋に入ったら、そうしたら、あんたの本があったから」
「買ってくれたのかね」
「うん、買った。なんたってうちの社長が書いた本だもの」
「で、読んでくれた」
「読んだ」
「どうだった」
「うん、面白い。仕事だけじゃなく、生活していくうえでも役に立つ。勉強になった」
しばらく本の内容についての話が続いた。
話していることは本のことだった。だが沢井の心のなかには全然別のことが伝わってくる。
小林は、沢井を嫌って話をしなかったのではない。むしろ沢井と立ち話がしたくてしょうがなかったのだ。
だが、中学卒ですぐ仕事につき、真面目一本槍に固く生きてきた小林にとって、沢井という男はあまりにもかけ離れた存在だった。東大卒、親会社からの出向社長、経営管理に関する著書も何冊かある勉強家――沢井は雲の上の人で、とても対等に話はできない。少なくとも常日ごろ仲間や家族と話している低次元の話題では、社長に失礼になる、とこの真面目な男は考えたのだ。
何か高級な話題を探して……と思っているところへ、沢井の本を見つけた。これだ。この本を話題にすればよい。とうとう見つけたぞ。小林は喜んでその本を買い、読んだのだった。そして沢井と話しのできるときを待っていた。
ところが沢井のほうは、どうせ返事もしない人間だとレッテルを貼って、ご苦労さん、とひと声かけて、足早に通りすぎてしまう。沢井の気づかぬ間に、何回か声をかけようとしてためらったにちがいない。そこで今日、通りすぎた沢井の背中へ、勇気を出して大声で呼び止めたのだ。
(中略)小林のこんな気持もつかめないで、オレが嫌いなのか、それとも無口な男か、と一方的に決めつけてレッテルを貼ってしまった自分の固い心が、沢井は情けなかった。人間200名もいれば、オレを嫌う人が何人かいるのが当たり前と、自分に都合のよい言いわけをこしらえる。
何百人いたって、すべての人をこちらから好きになっていけるような人間になれないのか。砂だらけの汚れた顔のなかで、眼と歯を白く輝かせて、いきいきと話しかけてくる小林を見ながら、沢井は痛切な反省におそわれていた。SD(セルフ・デベロップメント・トレーニング)やTAを含めて勉強を積み重ねてきたつもりのオレが、この程度なのか。50年の人生、オレは何を勉強してきたのか。(『黒字浮上!最終指令』)