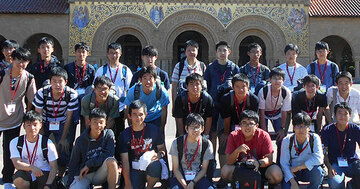『週刊ダイヤモンド11月2日号の第1特集は、「中高一貫 序列解剖」特集です。中学受験本番まであと数ヵ月、志望校選びも終盤戦に突入しています。大学入試改革が控えている上、それぞれに特色のある学校や公立中高一貫校の台頭などもあって、学校選びは格段に難しくなっています。そこで、歴史を踏まえた上で中高一貫校の最新序列を描き出し、今後有望な学校を探ってみました。
学区制度の変更で公立高校が凋落
代わって国立、私立が台頭
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
盛者必衰のことわり――。この有名な言葉が意味するところは、この世は無常であり、勢いの盛んな者もついには衰え滅びること。歴史をひもとけば、学校を取り巻く環境にも、この言葉がぴたりと当てはまる。
かつて優秀な生徒は、地域の最難関の公立高校に入った後、東京大学を筆頭とする難関大学に進学するのが常だった。
例えば、1950年代の東京都に住んでいたとすれば公立中学から都立日比谷高校に進学し、東大を目指すといった具合だ。当時、こうした“黄金ルート”に疑問を持つ人はいなかったはずだ。
ところが、この頃から全国的に学区制度やグループ選抜制度が導入されていく。特定の高校に優秀な生徒が集中することを避けるために始まった施策だ。
これぞ、まさに悪政だった。その後、坂を転げ落ちるように、公立トップ校が没落していく。
勉強に励んでも進学先の高校が自動的に割り振られてしまうからだ。そうした生徒たちが次に選んだ先は、国立大学の付属校や私立の中高一貫校だった。
その後、80年代に入り、私立の中高一貫校を舞台とした中学受験ブームが巻き起こる。それを仕掛けたといえるのが、公立高校の没落を商機と捉えた大手学習塾だ。