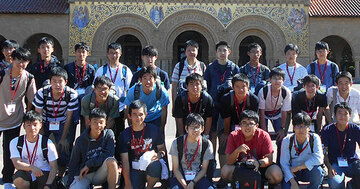男子御三家や女子御三家といった具合に、学習塾がさまざまな学校群をひとくくりにすることで、中学受験熱をあおったのだ。その熱は中間層にまで広がり、私立の黄金期につながっていく。
片や、国立の学校も恩恵を受けた。元々いた優秀層が公立高校に行かず、そのまま残ったことで進学実績が上がったからだ。
受験熱の高まりとともに、私立や国立を筆頭にした序列が確立。国立であれば、筑波大学附属駒場中学校であり、私立であれば、男子校の開成中学校、女子校であれば桜蔭中学校という具合だ。
こうした流れは首都圏のみならず各地で起きている。それぞれの栄枯盛衰については本誌特集でエリア別にまとめてあるので、ぜひご覧いただきたい。
10、20年後には筑駒、筑附が凋落し
公立中高一貫校の時代が来るか
では、今後も私立や国立が覇権を握り続けるのか。明快に言い切れるものではないが、答えは否と言わざるを得ない。
すでに各地の自治体は公立の復権に向けて学区制度を撤廃、公立中高一貫校の設立に向かっている。
日比谷が東大合格者数で50人を超え、都立復権と騒がれたのが2016年のこと。日比谷以外の実績はさほどでもなく、まだ復権と言い切れる段階にはないが、大きな一歩となったのは間違いない。
とはいえ、つぶさに見れば、都立をはじめとした公立復権の“萌芽”はそこかしこにある。その一つが、公立中高一貫校の台頭だ。
2000年代前半に、小石川中等教育学校を筆頭に11校が中高一貫校化し、快進撃を続けている。興味深いのは、「小石川に入学した後に高校から日比谷に行く生徒が増えていることだ」と、ある教育関係者は言う。かつての黄金ルートをほうふつさせる動きだ。
そして、公立王国の千葉県において08年、県立千葉高校が中高一貫校化した。2番手校や中堅校が中高一貫校化するのが一般的にもかかわらず、県千葉が動いたことで教育関係者の間に衝撃を与えた。