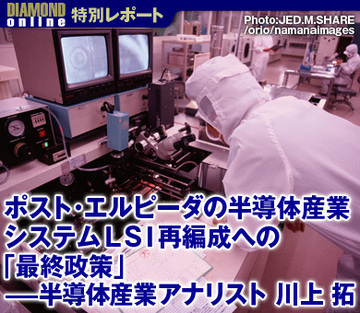前回までは、相次ぐ日の丸企業の凋落の原状と、日本の産業政策の基本となった「雁行モデル」の理念について検証してきた。雁行モデルとはアジアの技術力が伸長し日本に追いついてきたら、日本は彼らが作ることのできない製品をつくり、アジアを引き離せばいい、というものである。しかし、製品の性能向上は限界に近づいており、もはや日本が逃げ切れる余地はなくなりつつある。今回から2回にわたり、性能限界の中でも、理論限界と知覚限界について検証していきたい。両者の限界の意味を知ることが、戦略再構築のスタートとなるからである。
製品には宿命的な
性能限界がある
製造業は技術開発のために多額の資金を投じる。毎年優秀な大学の工学部から数多くの学生を採用し、何年もかけて一人前の技術者に育て上げる。たいていの会社は研究所を持ち、将来の製品の種となる基礎技術や、既存製品の商品力を高めるための研究にいそしむ。企業である限り、営業、管理などの部門もあるし、図面どおりに商品を生産する部門もあるが、新しい製品を開発する部門こそ製造業の競争力の根幹である。
どんなに経営状況が苦しくても、歯を食いしばってこうした部門を維持するのは、より高い性能の製品を開発することで、顧客により高い満足感を得てもらい、競争相手を引き離すためである。その営みが便利で快適な社会を築き、ダイナミックな市場の源泉となってきた。性能向上は尽きることのない製造業のミッションとも言える。
筆者もエンジニア出身だから、技術開発の重要性ややりがいはよく分かる。しかし、一生懸命研究したからといって性能は永遠に上がり続ける訳ではない。性能には理論的な限界があるからだ。理論限界に近づくと開発投資の効果は急激に低下し、後ろを飛ぶ雁(前回「雁行モデル」参照)からは前を行く雁のスピードが低下したように見える。