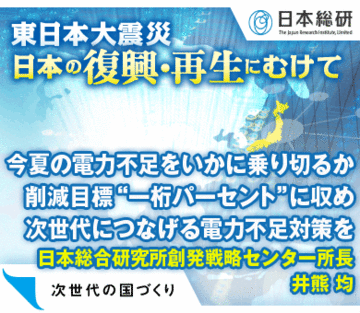井熊 均
第4回
政府は原子力発電を「基盤となる重要なベース電源」と位置づけた。これは国民の期待に応えたものとは言えない。事故の原因が究明されていない上、根本的な見直しに関する議論が国民にわかりやすい形で行われていないからだ。
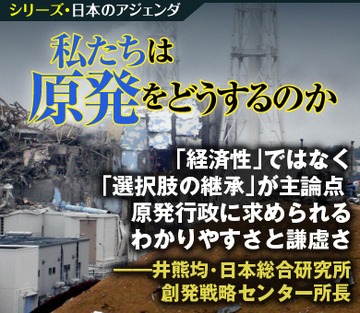
第11回
「組み合わせ」発想で日本産業を再興するためには、「組み合わせ」発想のできる次世代技術者を育成すると同時に、政府がビジネス環境を整える必要がある。その両輪がそろってこそ、日本産業は再生の途を進み始める。
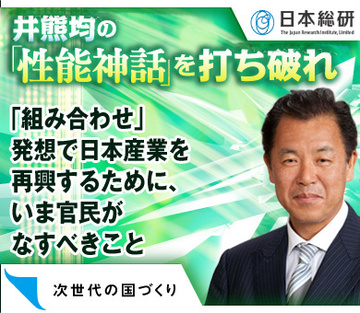
第10回
スマートシティ市場で日本は、前門の欧米、後門の中・韓に挟まれている。だからこそ日本は、エネルギーシステムを仕込み、組み上げ、事業として立ち上げることが求められる「中流」過程を狙うべきなのだ。
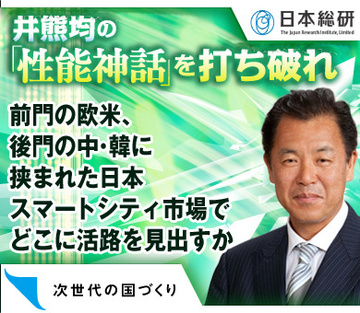
第9回
スマートシティは次世代インフラ市場の宝庫。ここに日本企業が参入する際には、強みである「組み合わせ」の力が発揮できるフロンティア分野へ挑戦することが必須だ。ダイナミックに動く新興国のスマートシティに対し、スピード感をもってソリューションを提示したい。
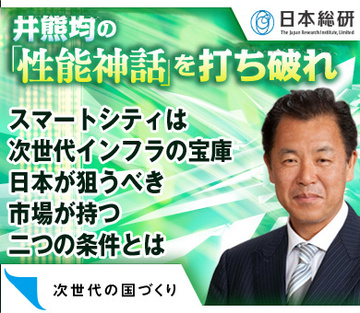
第8回
今、国内では様々な業種が参画し、スマートハウスを住宅街として展開する「組み合わせ」の連鎖が始まっている。日本の広い産業基盤がこの「組み合わせ」ビジネスを可能にしている。今必要なことは、こうした状態をポジティブに捉え、世界市場を見据え成功に向けて戦力を集中することだ。
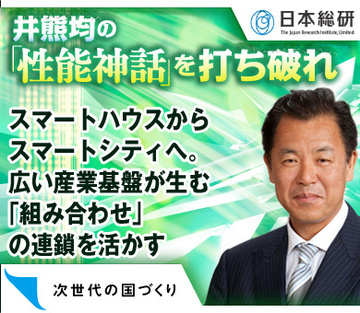
第7回
日本企業、特にトヨタは自動車業界という大市場で新たの流れの最先端を走っている。自動車にまつわる夢空間の創出は、低迷する日本に光をもたらす動きになりえる。日本はこうした夢のある世界を、政策や戦略に変える議論をポジティブに行っていくべきだ。
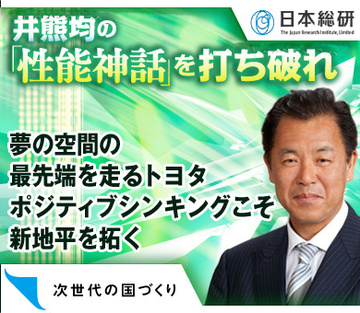
第6回
ハードウェアに頼った組み合わせは、「組み合わせという単品」を生むだけだ。組み合わせ戦略に活路を見出すために、市場に向けて価値を生み出すという原点に立ち返ることが必要だ。今、日本が時代を先取りし、組み合わせによる新しい価値を提供できるのは自動車業界といえるだろう。
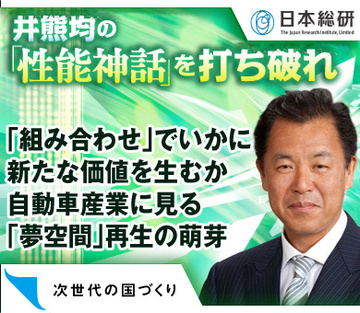
第5回
成功体験に根差した呪縛を解き放って、目の前にある壁を乗り越えるには、性能への期待を頭から払拭することが必要だ。そこで、「手中にある技術の性能はもう上がらない」と考えた上で、新たな「組み合わせ」の発想で戦ってはどうか。
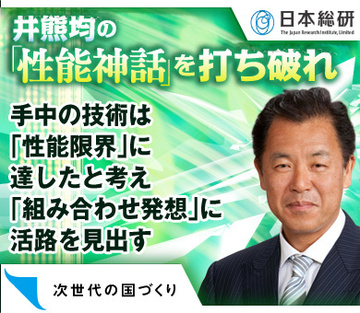
第2回
今、原子力発電を巡る意見の対立は社会に深い溝を刻もうとしている。その理由は、日本がエネルギーシステムという社会の基盤をいかにガバナンスするか、という視点が欠けているからだ。原発、需要サイドの変化、ガバナンスの3点から、日本が直面している問題について論じたい。
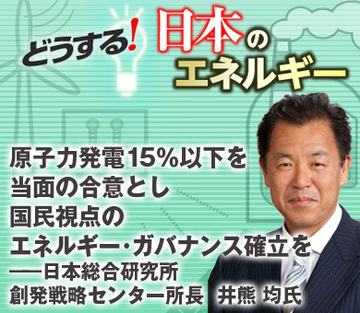
第4回
前回は「性能には理論的な限界がある」という話をした。今回は「知覚限界」の壁について考えてみる。性能が上がっても人間の方が違いを知覚できなくなったり、使いこなせなくなったりする。この知覚限界が製品開発にどのような影響を及ぼしたのだろうか。
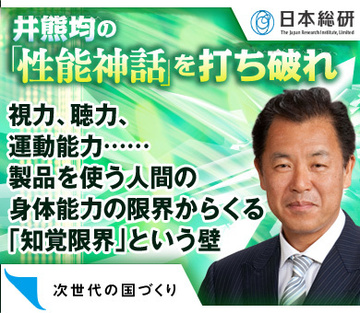
第3回
日本が追求してきた製品の性能向上は限界に近づいており、これによって逃げ切れる余地はなくなりつつある。今回から2回にわたり、性能限界の中でも、理論限界と知覚限界について検証していく。両者の限界の意味を知ることが、戦略再構築のスタートとなるからである。
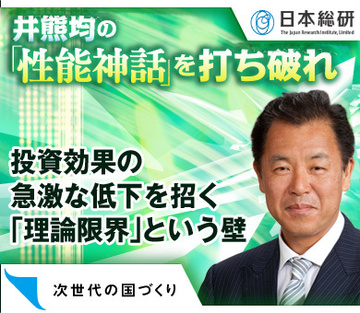
第2回
日本を先頭にアジア諸国が後に続くという雁行モデルはもはや崩れた。にもかかわらず、まだ日本は性能の向上で逃げ切れると考えている。競争力回復の第1のカギは、製品の性能は永遠に上げ続けることはできないことを、認識することから始まる。
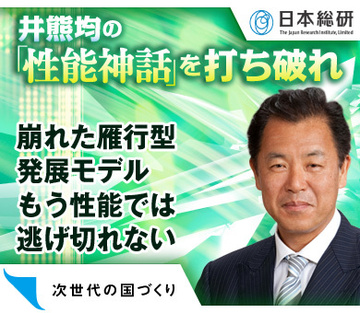
第1回
日本企業の苦戦が続いている。中でも、半導体、薄型テレビと先端産業の凋落が目立つだけに、将来に不安が広がっている。凋落のパターンも似ている。連載第1回目では、凋落の理由はどこにあったのかを考えてみる。
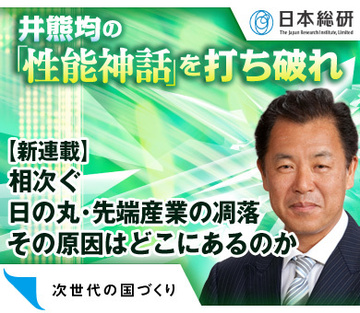
第6回
原発事故を契機に日本の将来のエネルギーシステムに関する議論が盛り上がっている。その際、原発か再生可能エネルギーか、という狭い視野に留まってはならない。そこでここでは、「需要家主導のエネルギーシステム」を提唱したい。
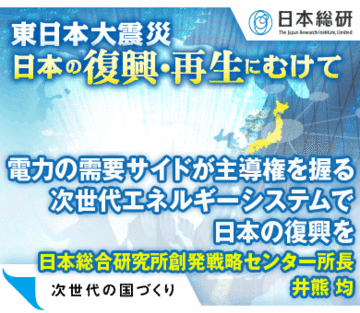
第2回
今夏の電力不足対応として政府は15%の節電を呼びかけている。ただ、現状の施策は三つの点が不足している。対策の手順を明確にするなど、三つの対策を実施すれば、節電目標を一ケタ台にできると同時に、低炭素社会実現への足がかりとすることができる。