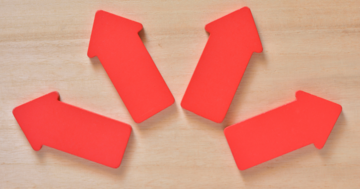みなさんが指摘していたとおり、《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》で特徴的なのは、その「色」です。
従来の絵画では、「色」は描く対象物の固有色を表したり、世界を目に映るとおりに描き留めたりするために使われてきました。
つまり、本物そっくりに描くための1つの手段として「色」が扱われていたのです。
しかし、マティスの妻の鼻すじは、まさか緑色ではなかったはずです。眉毛が青や緑だったとも思えません。そう、マティスは「目に映るとおりに描く」というこれまでの発想から離れて、「色」を純粋に「色」として自由に使うことを試みたのです。
さらに、各所に残る「荒々しい筆の跡」や「いびつな形」「太くてくっきりとしたアウトライン」などからも、それまでのアートからの決別への意志が感じられます。
マティスは《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》によって、「目に映るとおりに世界を描く」という目的からアートを解放しました。
ですから、あなたがこの絵を見たときに「うまい絵だなあ!」と思わなかったとしても、それは無理もありません。
この絵は、決して「うまさ」や「美しさ」から評価されているわけではなかったからです。
マティスは「アートにしかできないことはなにか?」という問いをめぐって「探究」を進めました。
その結果、「目に見えるものを描き写す」という従来のゴールから離れて、「色」をただ「色」として使うという「自分なりの答え」を生むに至りました。
マティスが「20世紀のアートを切り開いたアーティスト」といわれ、《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》が「すばらしい絵」だとされているのは、この「表現」を生み出すまでの「探究」の独自性ゆえでもあるのです。
ここから、まるで霧が晴れるようにアートの世界の視界が広がっていきました。
これまで、「表現」の出来栄えばかりに注目が集まり、「探究」や「興味」が十分に顧みられていなかったということに、アーティストたちが気づきはじめたのです。
それ以来、アーティストたちの活動は、「他人から与えられた課題」からではなく、「自分自身の興味」から「探究」をスタートさせるという「アート思考」の領域に、大きく軸足を移していきました。
その意味で、《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》は、「アート思考の幕開け」ともいえる1枚なのです。
末永幸歩(すえなが・ゆきほ)
美術教師/東京学芸大学個人研究員/アーティスト
東京都出身。武蔵野美術大学造形学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育)修了。
東京学芸大学個人研究員として美術教育の研究に励む一方、中学・高校の美術教師として教壇に立つ。「絵を描く」「ものをつくる」「美術史の知識を得る」といった知識・技術偏重型の美術教育に問題意識を持ち、アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を、都内公立中学校および東京学芸大学附属国際中等教育学校で展開してきた。生徒たちからは「美術がこんなに楽しかったなんて!」「物事を考えるための基本がわかる授業」と大きな反響を得ている。
彫金家の曾祖父、七宝焼・彫金家の祖母、イラストレーターの父というアーティスト家系に育ち、幼少期からアートに親しむ。自らもアーティスト活動を行うとともに、内発的な興味・好奇心・疑問から創造的な活動を育む子ども向けのアートワークショップ「ひろば100」も企画・開催している。著書に『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』がある。