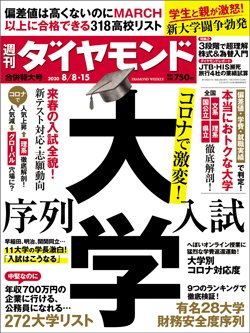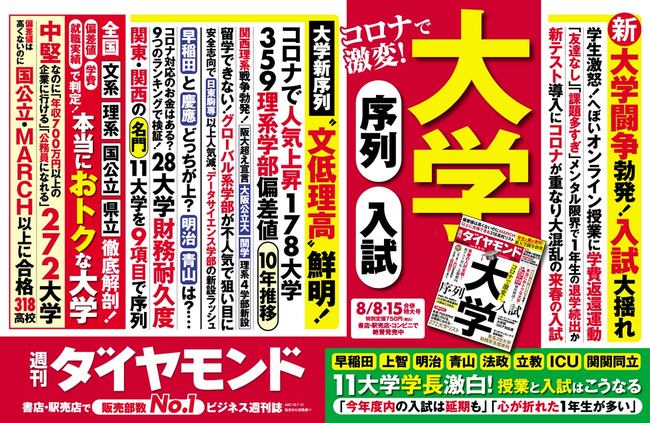まず、小中高に比べて、構内にいる学生数が時には万人単位となるなど桁違いに多いこと。次に、講義ごとに頻繁に教室を移動するため、学生同士の接触頻度が高いこと。そして、学外での学生の行動範囲が広いことだ。実際、大学発のクラスターは、サークルでの会食やクラブ活動などを通じて一気に広がっている。
ここで大学関係者の頭に浮かぶのは、3月末の京都産業大学の学生発のクラスターだ。しかも、京都市長が京産大の学長を伴う形で会見を開き、謝罪する事態に追い込まれた。
3月上旬から中旬にかけて、欧州に卒業旅行に出掛けた京産大生がクラスターの発端となったわけだが、出国時点では旅行先に入国禁止措置は出ていなかった。
だが、帰国後に特段の症状がないからといって卒業祝賀会などに出席したのがまずかった。ここで一気に感染が広がったからだ。
京都市長は外務省などのアナウンスには従ったなどと学生をかばってみせたが、その後、京産大生に対して「火を付けてやる」「感染している学生の名前や住所を教えろ」といった脅迫行為や、京産大生というだけでアルバイトを解雇されてしまうなど、ヘイトまがいの行為が横行したという。
「大学生の行動はコントロールできない。うちも京産大のようになるかもしれない……」
こうした思いが大学関係者の心に刻み込まれた。故に、大学は門を開くことにちゅうちょしているというわけだ。
だが、大学側にこうした事情があるにせよ、一番割を食っているのは学生たちであり、不満が大きく渦巻いている。
「どうしてこんなに課題が多いんだ。まるで課題地獄だ!」
今、多くの学生たちはこうした怨嗟の声を上げている。無理もない。5月ごろから本格的に始まった、対面授業の代わりのオンライン授業で出される課題の多さに、学生たちは振り回されている。
(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)
10段落目:だが、帰国後に感染が判明したにもかかわらず、特段の症状がないからといって卒業祝賀会などに出席したのがまずかった。→だが、帰国後に特段の症状がないからといって卒業祝賀会などに出席したのがまずかった。(2020年8月26日 0:43 ダイヤモンド編集部)