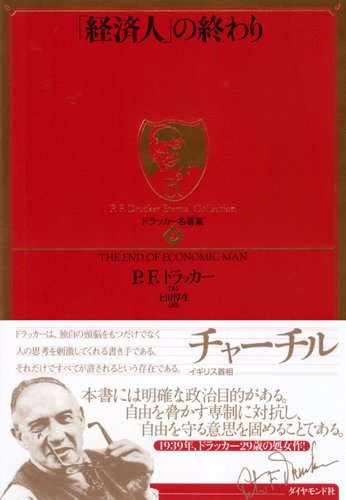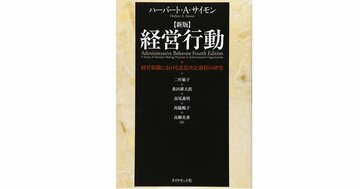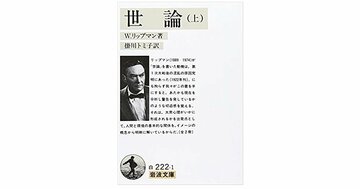第一次世界大戦後、ヨーロッパはファシズム(全体主義)に襲われる。『「経済人」の終わり』はファシズムとはなにかを解説したもので、ファシズムが進展する1939年に出版された著者ドラッカー29歳の処女作である。単なる現象の解説や診断ではなく、ファシズムの原動力と本質、すなわち人の価値観の変化と人間の本性から天地万物及び社会における人間の位置を見抜き、その運動の必然的な帰結を予測(断言)した。すでにドラッカーのドラッカーたるゆえんである洞察力に満ち満ちている。そして、今の時代だからこそ読むべき本と言っていい。なぜ今読むべきなのか、本書の論旨をかいつまみながら解説していく。
ドラッカー29歳の処女作
『「経済人」の終わり』を今こそ読むべき理由
『「経済人」の終わり』というタイトルだけ見て、従来型の資本主義が行き詰まり、混乱のさなかにある現状のことかと思われた読者もいるかもしれない。アメリカは異常ともいえる混乱状況にあるだけではなく、従来型の資本主義が行き過ぎた結果として引き起こされた矛盾や格差の拡大、社会の分断があらゆるところで問題になっている。かたや中国のような共産主義体制国家の巨大化、独裁政権による弊害が引き起こす問題も無視できない。
実は、今からおよそ80年~90年前の1930年代にも、世界は同様の事態に陥っていた。本書を読むことは、今の混迷の時代を読み解くヒントになる。
まず、なぜタイトルが『「経済人」の終わり』なのか。近代ヨーロッパでは、おおざっぱに言えば、王侯貴族が牛耳る階級社会に対して市民革命が起こり、産業革命によって一般市民の一部が資本家(ブルジョア資本主義、以下仮に資本主義とする)として台頭。すると今度は資本家に牛耳られた労働者が共産主義革命(マルクス社会主義、以下仮に社会主義とする)を起こした。
つまり、貴族や階級をつぶして自由になるため、経済の力でのしあがったのがブルジョア資本家であり、資本家から自由になろうとしたのが社会主義である。社会主義は、資本家には反対していても貴族ではないので、資本家と同じく根本では経済の力という自由を得る手段によって成立している。
「あらゆる社会が、人間の本性およびその社会における位置と役割についての概念を基盤として成立している。~中略~ まさに、人間を経済的動物(エコノミック・アニマル)とする概念は、完全に自由な経済活動をあらゆる目的を実現するための手段として見るブルジョア資本主義およびマルクス社会主義の基盤である」(以下、「」内の引用文はすべて『「経済人」の終わり』〈ダイヤモンド社〉)
資本主義と社会主義という当時のヨーロッパの2大思想はいずれも、人が経済的動物(経済人)であるという前提で成立していると書かれている。なぜなら経済の力を使って貴族や階級から自由になろうとしていたからである。つまり経済人は、ヨーロッパで尊ばれてきた「自由」と「平等」を実現するためという目的で正当化できるし、そのために生まれた概念だとドラッカーは言う。
「社会秩序および信条としてのブルジョア資本主義は、経済的な進歩が個人の自由と平等を促進するという信念に基づいている。マルクス社会主義はそのような社会は私的利潤を廃止することによってもたらされると期待する。これに対してブルジョア資本主義は、自由で平等な社会は、私的利潤を社会行動の規範とすることによってもたらされると期待する」