
秋山進
営業もサービスも、かつてより確実に質が落ちている――そう感じながらも、多くの顧客は声を上げず、他社へも移らず、低い期待のまま関係を続けている。そんな現代に登場したAIの存在は、社会でどんな役割を担っていくだろうか。

プルデンシャル生命の社員・元社員107人が総額31億円の金銭詐取をしていたという報道を見て、正直なところ会社の規模にしては「少ない」と感じる。しかし、ここまで「袋叩き」にあっているワケはなんだろうか。数字を冷静に見れば、この事件は単なる「不祥事」として片付けられる話ではない。問われているのは限界を迎えたビジネスモデルそのものだ。
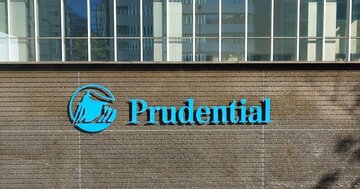
AIが進歩し、日々の業務のデータは簡単に履歴として残り、精査される時代になった。便利ではあるが、昔はなんとなく許された雑な経費処理は今後許されない時代になる。過去のミスは事細かに簡単に発見できるようになり、自ら社会人としてのステータスを大きく揺るがす事態になり得る。
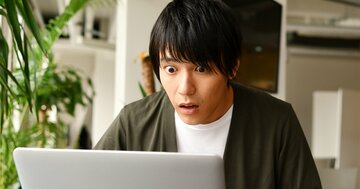
今年こそ解決したいなと思うのが、エスカレーターの片側あけ問題である。長年議論されているが、なかなか2列に並ぶようにならない。一体どうやったらこの「習慣」が変わるだろうか。

なぜJALは賞賛され、フジは叩かれたのか?他人事じゃない「昭和な企業」の末路
2023年末の週刊誌報道を発端にフジテレビ、芸能界、そして社会を大きく揺るがした「フジテレビ問題」。問題が明るみになってから約1年が経とうとしているが、未だフジテレビは混乱の中にある。ただ日本の多くの企業においても、同様の事案が起きてもおかしくない。

今年の漢字は、「熊」となった。もとになったのは、東北を中心に今年相次いだクマの出没と人的被害だ。ただ、クマの出没が増えることは予想に反していたかというとそういうわけでもない。2025年は「起こることがほぼ確実な事象に対して、人がいかに準備を怠るか」という、人間(国や自治体)の残念な一面を示す問題が、クマ被害以外にもいくつも起こった。

何かというと文句ばかり言う人があなたの会社にもいないだろうか。“文句ばかり言う人”が持つ不満の裏には、会社がまだ見ぬ「構造的な課題」が隠れていることが多い。にもかかわらず、彼らの声は「ネガティブ」「面倒」として切り捨てられ、組織はその貴重なセンサーを失ってしまう。では、この“文句ばかり言う人”を「洞察力ある人材」に変えるには、どうすればいいのか。

「代行」「代理」多すぎ!誰に決裁権があるの?…誰も責任を取らない国の末路
幹事長代理、支店長代理、部長代行……世の中には「代理」や「代行」といった肩書があふれている。しかし、実際、代理や代行がどういった責任を負っているのか明確に説明できる人は少ない。これらの役職・肩書の背景を考察すると、「不健康な社会」が見えてきた。

人気連載『組織の病気』の著者、秋山進氏が防衛省出身でサイバーセキュリティの専門家であり、『ウクライナ企業の死闘』の著者でもある、NTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子氏との対談後編。

「台湾有事の前哨戦」はもう始まっている?日本がウクライナに学ぶべき戦争への備え方
人気連載『組織の病気』の著者、秋山進氏が 防衛省出身でサイバーセキュリティの専門家であり、『ウクライナ企業の死闘』の著者でもある、NTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子氏と対談。前後編の前編では、ウクライナはロシアからのサイバー攻撃をどう防いだか、戦時に狙われるインフラ企業の実態、日本の安全保障の問題点から、台湾有事に際してどのような教訓を学べるかを語り合った。
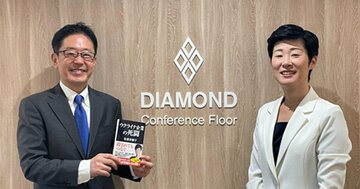
企業がインフルエンサーに無料で商品やサービスを提供し、SNS投稿されたにもかかわらず、広告であることを明示しないのは違法な行為だ。これはステルスマーケティング(いわゆるステマ)と言われるが、摘発されるのは大手企業や有名人、数万人のフォロワーがいるインフルエンサーで、自分は無関係と思うかもしれない。しかし、ステマはもっと身近なものになってきているようだ。

カスハラが昨今問題になっていて、法的整備も進んでいる。一方で顧客の逆鱗に触れるような、「逆なで」対応というのもまた厳然として存在する。顧客を怒らせてしまう対応をなぜしてしまうのか。そして、「逆なで」しないためには、どうすべきか考えた。

2025年も残り100日だ。下期が見えてきた今こそ、これからの社会変化を予測し、何を今すべきなのか考えたい。
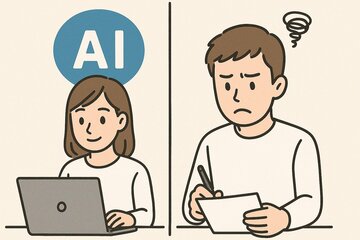
甲子園における内集団びいきは無害だ。むしろ「郷土愛」の表現として肯定的に見られる。地元代表を応援する気持ちは誰にでもあるし、地域も個人も盛り上がる。だが、この心理が企業に持ち込まれると事態は変わる。

会議や研修、講演、さらにはパネルディスカッションや対話イベントにおいて、「参加者」は決して一枚岩ではない。いったいどうすれば「多様な聴衆」を巻き込み、納得と共感の場を作ることができるのか。

オフィス街のカフェに行くと、オンライン会議を堂々としている人たちによく遭遇する。企業の機密情報や個人情報が「ダダ漏れ」なわけだが、なぜベラベラと話してしまうのだろうか。

メールが遅い人は仕事ができないと昨今よく言われます。現代はスピード重視で、メールのやり取りのスピードについても厳しくジャッジされるのです。しかし、問題なのは、メールの早さだけではありません。何を伝えたいのかわかりにくい文面を書くと「仕事ができないのではないか」と判断される傾向があります。なぜ、伝わりづらいビジネスメールを書いてしまうのか、そしてどうやったらわかりやすいメールをすぐに書けるようになるのでしょうか。

スキャンダルでも「許される人」と「叩かれる人」の決定的な違い
ビジネスや政治、芸能の世界では、さまざまな不祥事が日々報じられているが、似たような問題行動であっても「猛烈に糾弾される人」と「なんとなく許されてしまう人」がいる。この「差」はいったい何に由来するのか。

「時間がなくて」「やる気なくて」部下に言い訳された管理職はラッキーである、意外だけど納得の理由
「言い訳するな」と切り捨てられることが多々ある。しかし、私たちはこの言葉のもとで何が失われているかをそろそろ見直すべき時期に来ているのではないか。

もし自分の息子や娘がフジテレビに内定し、「入社したい」と言ってきたら、あなたは賛成しますか?それとも反対しますか?リクルート事件を経験した著者が、フジテレビという企業を題材に、不祥事を起こした企業に入社することの是非を考えました。
