究極は、患者と家族の問題
後閑:先日、あるがん患者さんが、「自分はがんでそんなに時間が残されてないとわかってる、だからこれからこうしていきたい、こういう準備をしておきたい、という話を家族としようとすると家族に逃げられてしまう」と言っていたんです。これからのことを話したいのに家族が聞いてくれない、だから孤独を感じると。それを聞いていたまわりのがん患者さんが、うちもうちも、といった感じで。
柏木:そういうことはよくあります。僕なりの解釈ですが、家族自身もつらいんだと思うんですよね、家族ケアをすることがまず最初だと思うんです。
ぼくはあまり患者さんをかわいそうだと感じることはないんですが、ぼくが唯一、これはかわいそうだなと思うのが、本人は自分の状況に向き合うし、向き合う力があるのに、そのことを誰も信じてくれない、特に家族が。「いやいや、本人はもう家に帰るのは無理なので」と家族が言うから「本人と話し合ったんですか」と聞いたら、「いや、話し合ってはいないけれどわかるんです」という感じ。多くの患者さんは僕よりも年上で、何十年も過ごされてきた方を赤ちゃんのように扱うようなシーンだけはかわいそうに思ってしまいます。
そういうときは、ワントライはします。「本人がどう感じられているかが大事だから、やっぱり聞いたほうがいいと僕は思いますがいかがですか」「怖いですよね、でもご家族だけで話をしてほしいというわけではなく、ご本人と話し合う時に僕らも参加して一緒に聞けたらいいなと思いますがどうですか」とか。
この辺りというのは、家族自身のつらい状況に対する対処方法や、何十年単位の人間関係だったりもするので、たとえば1週間で亡くなるような状況で、その1週間で全部リカバリーできるかと言ったら医療者に全部ができるわけではないけれど、「1回はトライしてみる」を僕のルールにしています。
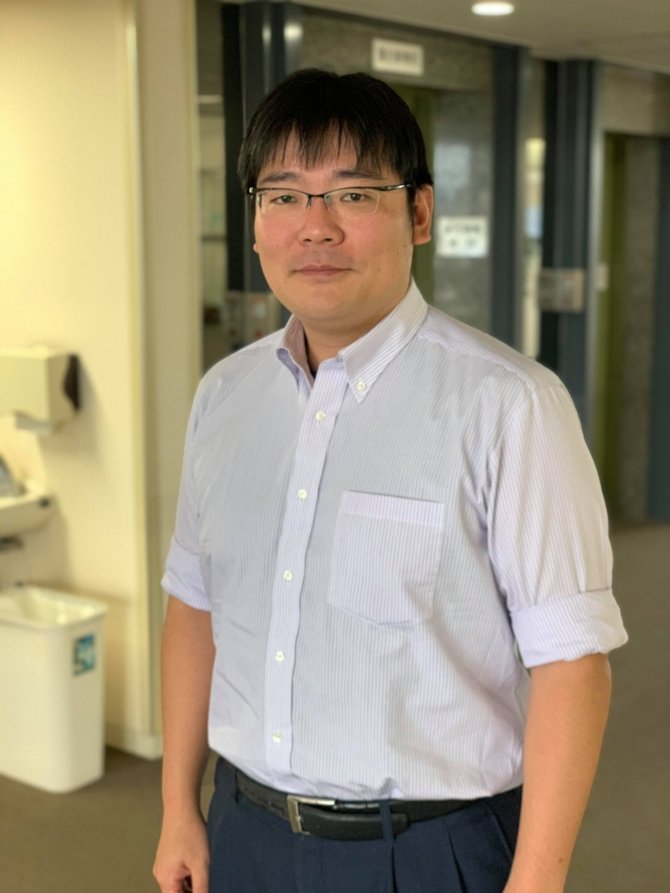 柏木秀行(かしわぎ ひでゆき)
柏木秀行(かしわぎ ひでゆき)飯塚病院 連携医療・緩和ケア科部長・地域包括ケア推進本部副本部長・筑豊地区介護予防支援センター長
1981年生まれ。2007年筑波大医学専門学群を卒後、飯塚病院にて初期研修修了。同院総合診療科を経て、現在は連携医療・緩和ケア科部長として研修医教育、診療、部門の運営に携わる。グロービス経営大学院修了。
後閑:いま入院中のがんの患者さんが「おれは死ぬのか」って家族に言ったんです。そうしたら家族が看護師に「本人に弱気になるようなことを言ったんですか」と怒ってきたんです。「本人がおれは死ぬのかなんて弱気になっているから、そんなこと言わないでって私が否定しておきました。もう弱気になるようなことは言わないでください」と言うんです。正直、患者さんをかわいそうに思ってしまいました。こちらももちろん「もう死ぬよ」なんて言ってはいないんですが、明らかに時間はもうないんです。弱っていく一方だから、本人もわかっているんです。本人は弱音を医療者には言わない。ようやく家族に本音を言えたんだと思うんですけれど、その家族に否定されてしまい、つらいだろうな。
柏木:ぼく社会福祉士の資格を取ったんですが、対人援助のスキルを勉強した時に、支援のあり方を集中的にインプットした時期があって、今の話を聞いて思い出しました。人を支援するってどうするかというトレーニングを医療者自身も受けているわけではないし、家族はなおさらですから、「自分がつらくないように」を優先するんです。
おそらく、自分は死ぬのだろうかと家族に聞いた患者さんも、家族でなければ聞けないなんらかの心情があったのだと思うんです。それに対して、励まさなきゃいけない、ポジティブにしないと病気が悪くなる、あとはその話題に触れたくないから閉じ込めておきたい、とかね。ですが、支援の本質ではないような対応しかできないというのが家族の状況なのでしょう。

