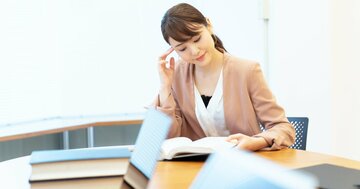『独学大全──絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』が20万部を突破! 本書には東京大学教授の柳川範之氏が「著者の知識が圧倒的」、独立研究者の山口周氏も「この本、とても面白いです」と推薦文を寄せ、ビジネスマンから大学生まで多くの人がSNSで勉強法を公開するなど、話題になっています。
この連載では、著者の読書猿さんが「勉強が続かない」「やる気が出ない」「目標の立て方がわからない」「受験に受かりたい」「英語を学び直したい」……などなど、「具体的な悩み」に回答。今日から役立ち、一生使える方法を紹介していきます。
※質問は、著者の「マシュマロ」宛てにいただいたものを元に、加筆・修正しています。読書猿さんのマシュマロはこちら
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
[質問]
資料を後世に残す意義は何だと思いますか?
遅ればせながらスゴ本さんと読書猿さんの、映画『ニューヨーク公共図書館』の対談を読みました。
資料を残さなくてはならない、そして“We must have everything!”といって検閲(?)に対抗した図書館のがんばりが特に印象に残りました。
正直言って、私達の社会は資料を残さない社会だと思います。「水に流す」という言葉があるように、都合の悪いことは隠してしまおう、燃やして事実ごと消してしまおう、昔のことなんていつまでも覚えている方がおかしい、という人が少なくないのだと思います。
私はそれはおかしいと思うのですが、どうしてそうなのか、うまく言葉にできないでいます。
読書猿さんは、資料を後世に残す意義は何だと思いますか? ぜひお考えをお聞きしたいです。
大切なのは未来の私たちに期待し判断を委ねること
[読書猿の回答]
資料を残すということは「未来の私達は現在より賢くなれるかもしれない」と期待することです。
現在の私達が下す「こんな資料は残す必要がない」という判断は、未来永劫正しいとは限りません。
人は誤りを犯し得る存在であり、また自分の愚行を認めることに強い反発を覚える生き物です。その資料は、現在の価値観では「くだらない、後世に残す価値がない」ものに見えるかもしれません。あるいは、あまりにひどい愚行の証拠や証言は忘れたいし、残したくないのも人情というものです。
しかし、その資料を後世に残すことで、事の判断を未来の人たちに委ねることができます。いつか歴史の再審にかけることで、それはやはり愚行であったのだと分かったならば、未来の人たちはその愚行に学び、それを知恵にできるでしょう。
私達は、自分が愚かな振る舞いをするかもしれないと知る程度には、知的な存在です。
そして楽観的すぎるかもしれませんが、未来の私達は、現在の私達が知らないことを知り、気付かなかったことに気付いてくれるかもしれません。
繰り返しになりますが、資料を残すことは、人類の知に対して信頼することであり、「未来の私達は現在より賢くなれるかもしれない」と期待をかけることなのです。