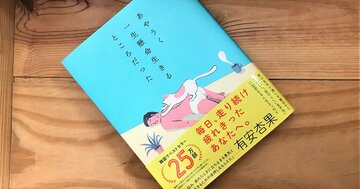声をかけられるのはいつも彼女のほうだった
彼女の顔が一瞬、大きく映った。その顔を見て私はハッとした。いや、違う。これは違う。彼女は悲しいわけでも怒っているわけでもない。これは……この顔は……。
走馬灯のように、その顔を見たときのことが蘇ってくる。そうだ。あれは中学生の頃だったか。当時一番親しかった友人は、とても華がある子だった。目立つ。学年の人気者。明るくて、ちょっと気分屋なところがあるけれど、それでも愛される。先生からもよくいじられる存在。見た目もかわいい。男にもモテる。そういう子だった。
私はその子ととても仲が良くて、学校帰りにも休みの日にもよく渋谷に遊びに行った。カラオケや買い物をしたり、ゲーセンでプリクラを撮ったりして遊んだ。彼女は本当に魅力的な子だった。小悪魔的、と言ってもいいのかもしれない。ちょっとわがままで、無意識に人を振り回すようなところがある。でもそんなところも、人を惹きつける要素の一つに過ぎなかった。
私も彼女に惹かれていた人間の一人で、話していてとても楽しかったし、人として大好きだった。彼女といつも一緒にいた。人気者の彼女と一番仲が良いという事実がなんだか誇らしかった面もあった。
彼女と私のペアは最強なんじゃないかと思っていた。街を二人で歩いているとよく声をかけられたし、「どっかみんなで遊ぼうよ」と男二人組に声をかけられるなんてこともあった。私は彼女と仲良くなったことによって自分も華のある人間になれたような気がして、嬉しかった。
でも、あるとき突然気がついた。
話しかけてくる人たちがいつも、私のことを見ていないことに。
私一人だと、誰にも声をかけられないことに。
「ねえねえ、これからどこに行くんですか?」
そうやって声をかけられるのはあくまでも私ではなく彼女のほうだった。いつも人が来るのは彼女の側だった。それは私がツンとした顔立ちで、声をかけづらいからなのだと言い聞かせていたけれど、違うのだ。彼らの視界に、私ははじめから入っていなかったのだ。
彼らが声をかけたかったのは「彼女」であって、その隣にいるのは誰でもよかったのだ。私でも、別に他の友達でもよかった。私は、「女二人組」でいることによって話しかけやすくするという要素の一つに過ぎなかった。
話しかけられているのは、「私たち二人」ではなく、「彼女一人」なのだ。
もちろん、そのことに気がついてから、私は動揺した。なんで彼女ばかりが声をかけられるのだと思った。理不尽じゃないか。失礼じゃないか。女二人いるのなら、両方に話しかけるべきだ。一方を無視するなんておかしい。平等に接するべきだと思って憤慨した。
でも、そんなことが繰り返し繰り返し起こるうちに、私の中に諦めの感情が芽生え始めていた。
これは、仕方のないことなのだ、と。
世の中には華がある人間と、華がない人間がいて、そのどちらかに一度分類されてしまったら、もう一つのカテゴリーに移ることはできないんだと、気がついたのだ。
でも、理解してからは、早かった。「そういうもの」だとわかっていれば、「目立たない存在」として落ち着いていられる。彼女のように目立つわけではないけれど、実はきちんと状況を把握できている人間。そう、叶姉妹で言えば叶美香さん的存在。彼女がエキセントリックな恭子さんだとすれば、私は落ち着いて姉を支える堅実な美香なのよ。そう自分に言い聞かせていた。それで精神を保っていた。
そして、テレビ画面の向こうの彼女も、そんな顔をしていた。
「大丈夫、いつものことよ」と、彼女は自分自身に、言い聞かせているような気がした。悟った顔をしていたのだ。何かに焦っていたり、イライラしていたり、動揺していたりする様子はない。「別に大丈夫」、そんな落ち着いた顔。そう、まさに叶美香さん的顔だ。
ああ、きっとこの子も、いつもこの目立つ女の子と一緒にいて、こういう現象には慣れきっているのだろうなと私は思った。なんということだ。この子は健気じゃないか。私はあの頃の自分を思い出し、彼女と重ね合わせて涙が出そうになった。