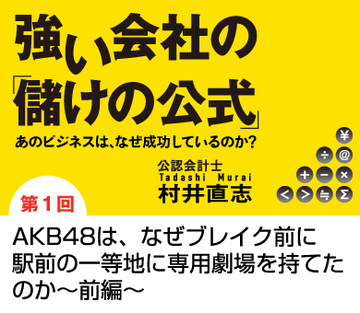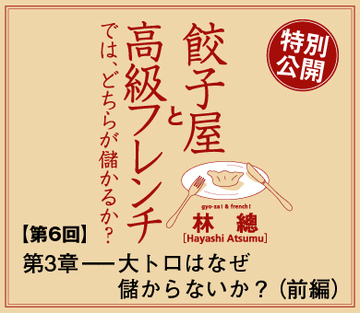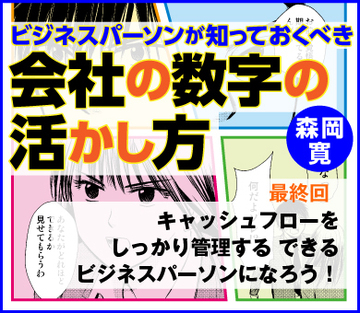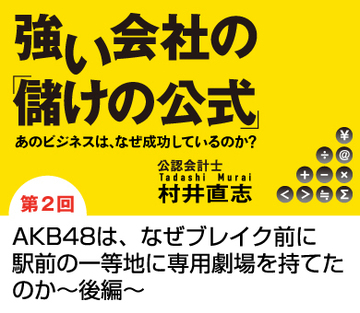街中の生花店の「稼ぎ頭」である
胡蝶蘭、仏事用の菊の花を売らない理由
では無駄をなくし利益を出すために必要な「経費戦略」という観点から、逆境の中でも利益を出せるヒントを探してみましょう。
普通、花屋といえば、法人用、個人用、冠婚葬祭用という具合に、さまざまな花を用意します。
法人の慶事用に、開店記念として良く利用される「胡蝶蘭の鉢物」。これは『笑っていいとも!』に出演したタレントに、お祝いの意味を込めて贈られることでも有名な花です。
でも、これを青山フラワーマーケットは扱いません。個人のお客様が普段使いに用いる花だけを扱う、ここに特化しているのです。
そもそも鉢物は単価が高くなりがちです。胡蝶蘭は、安いものでも5000円くらいはします。景気が落ち込む中で、なかなか大量に売れるものでもない、と割り切ったわけです。(ちなみに、買った後の花を楽しめる期間を考えれば、本当は安いのです。切り花は1週間程度、胡蝶蘭だと1カ月程度は花を楽しめます。1日あたりの単価では、胡蝶蘭のほうが断然お得です。)
そして次に、普通の町にある生花店の稼ぎ頭である「仏事用の菊」も扱いません。こういったものは定期的に売上が見込めるのですが、菊=仏様に供える花として日本人のDNAに組み込まれていますので、その一角だけ華やいだ雰囲気とかけ離れてしまうからだといいます(まったく仏事に対応していないわけではなく、抑え目の色合いの花を仏事用として販売しています)。
こうした発想は、パリのマルシェにある花屋のイメージから来ています。パリジャンが彼女のために、パリジェンヌが家族のために、普段使いで花を買い求める、こうした店がニッポンにあってもいいんじゃない?花を小脇に抱えるサラリーマンって、格好良くない?買い物袋から少しだけ覗かせる花を持つ女性って、可愛らしいよね?
そういった、花のあるリアルなシーンを想定して雰囲気のある店作りをしているのが、井上社長のビジネスの成功の秘訣なのです。ちなみに、井上社長のモットーは『花を売らない、花屋』だそうです。