『独学大全──絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』を推してくれたキーパーソンへのインタビューで、その裏側に迫る。
今回は特別編として、日本最高峰の書評ブロガーDain氏と読書猿氏のスゴ本対談「世界史編」が実現。『独学大全』とあわせて読みたい世界史の本について、縦横無尽に語ってもらった。(取材・構成/谷古宇浩司)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
嫉妬する気も起きないほどすごい「新書」
読書猿:以前Dainさんとの世界史対談で、スゴ本として『岩波講座 世界歴史』を取り上げたんですが。
その後、この本の編者である小川幸司さんが編者として、またとんでもない本を出されたので、ぜひご紹介したいなと思って持ってきました。岩波新書の『世界史の考え方』という本です。
 『世界史の考え方』(岩波新書)
『世界史の考え方』(岩波新書)
Dain:副題は「シリーズ歴史総合を学ぶ①」。2022年4月から高校で新しい科目「歴史総合」(これまでの世界史に比べ、日本史と世界史関連性を重視する)の授業がスタートしたことを踏まえた新書なんですね!
読書猿:はい。この本、「新書」の範疇を完全に飛び越えています。
①この本一冊(全5章)で初期近代から現代まで、「歴史総合」でやる範囲をカバーしている「網羅性」
②歴史認識を更新する知的営為としての歴史学、という熱い「テーマ」
③このテーマをただ論じるのでなく、いわば紙上実演する、鼎談という「構成」
コンセプトと構成と内容が、きまりすぎてる。もうちょっと、嫉妬もできないレベルです。新書のサイズにするために、ちょっとまとめすぎなところもありますが、それでも、とんでもない本です。
Dain:具体的に、どんな内容なんですか?
読書猿:内容は章ごとに「3冊」を取り上げて鼎談形式で進みます。
3冊のうち、最初の1冊は、大塚久雄とか丸山眞男の著作なんです。戦後の第一世代から始めて、2冊めは、第二世代の名著。そして、3冊目が、最近の著作。この最新の1冊については、書いた本人(著者)を、ゲストに呼んでいます。こうした3冊3人の読書会が、1章~5章まで、5回分入っている。鼎談を読んでいくと、自然に歴史の「縦」の流れも掴めるようになっています。
各章の3冊ずつの選書も素晴らしい。
1冊目に選ばれる往年の名著は、時代的にいろいろ限界があるんで鼎談の中でも批判的な指摘があがるんですが、でもその内容って、ぼくらの歴史観のベースというか、常識をつくっているものなんです。1冊目を検討する中でぼくらの歴史観が問い直される。
2冊目は『砂糖の世界史』みたいな、ぼくらが感動して読んできた新しい歴史書です。
でも、これで終わらない。3冊目があって、さらにその著者が鼎談に、参加してるという。例えば第一章の3冊目『東アジアの「近世」』、山川リブレットの小さな本ですが、ぼくらの近世観を書き換えるような、とんでもない本です。世界的な銀の流通が地域世界をかき回し、この流動的な状況に対応しようと台頭してきたのが和寇であり、やがて清を建てるヌルハチたち女真族であり、国性爺合戦のモデルとなった鄭成功である、と。
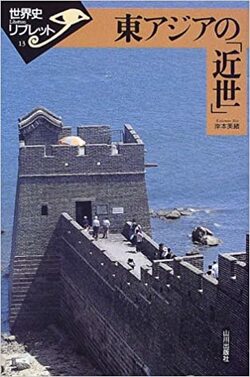 『東アジアの「近世」』(山川出版社)
『東アジアの「近世」』(山川出版社)
歴史学が変わり、授業も変わっていく
読書猿:以前の記事で、歴史の授業で教える内容が変わっていく話をしましたが、その源はいうまでもなく、歴史研究の発展と変化です。「人間の歴史」だけではなくて、気象や食料、感染症を切り口とした歴史研究もたくさん蓄積されています。
一方で、もっと「人間くさい部分」つまり「人がどんな風に歴史を紡いでいくのか」(歴史の構築性)にもメスが入れられています。「作られたもの」としての歴史批判というか。昔の歴史家は嫌がる話ですけれど……。
Dain:歴史の構築性とは、歴史はどう「作られて」きたか。つまり、よその国に行けば歴史の見え方が変わる……ということですか。
読書猿:はい。かつては王朝が「公式の歴史」を編纂して、歴史は政権の正当化の手段のひとつだった。アカデミックな歴史研究はそういうものを批判して登場したので、限られた史料の中でできるだけ客観的な史実を確定しようとする。それでも「何を取り上げるか/取り上げないか」というところに歴史家の主観、それに影響を与える時代やその社会の価値観が反映してしまう。
しかし忘れてならないのは、他の時代や社会にも「他の主観や価値観」に基づいた歴史記述があり、しかも、そうしたものと我々は無関係ではいられない、ということです。
そもそも歴史学はなぜ、あるのか? 勝者が勝どきをあげ、自身のアイデンティティを捏造し、敗者に沈黙を強いるためにあるのではなく、お互いの記憶を冷静に見つめ直し、異なる見方や記憶があり得ることを承認し、自分と違う歴史を生きる人たちと対話を始め続けるために、そうした対話を通じて自分の歴史認識を更新するために、歴史学はあるのだと、少なくともそうなろうとしているのだと、言いたいと思います。
もちろん実際のところどうだったのかを突き詰めるのは大切です。でも歴史に向かい合うことは、それ以外のものも含んでいる。そこも含めて議論する。
Dain:「パブリック・ヒストリー」という言葉がありますよね。開かれた対話によって積み上げられた歴史。
読書猿:パブリック・ヒストリーを巡る議論では「記録」と「記憶」の対立は避けられません。研究者にとっては記録の方がえらい。記憶はイメージや感覚が入り混じったものだから。記憶から神聖性を剥ぎ取るのが歴史家の務めとアナール学派のピエール・ノラはいっています(注1)。人々の記憶に宿る熱狂性に対して、歴史家は距離を取り、時には冷や水を浴びせる。
そのこと自体は大事だけれど、いつもいつも、記録の方が正確で記憶の方が歪んでるとは限らないし、「正しい記録にひれ伏して記憶の方は黙ってろ」と抑圧したら、収まる話も収まらないでしょう。だって他人から見て歪んで間違った記憶でも、当人にとっては人生そのものだったりするんですから。
誰かに沈黙を強いる「正しさ」を振りかざす代わりに、自分たちとは違う記憶を抱える人とも話を続けることが大切なんじゃないでしょうか。
そんな風に議論を重ねて、後で紹介する『世界の中のフランス史(Histoire mondiale de la France. Paris: Seuil)』のような、多面的な視点を生み出す方がいいかもしれないと思うんです。
「『記憶』とは個人や集団によって担われるもので、思い出を聖性の中でとらえて『記念する行為』(コメモラシオン)を伴うのに対し、『歴史』とは記憶を解体し、その聖性を剥ぎ取る営みである」
ヨーロッパには「隣の国と話し合ってつくる教科書」がある
読書猿:それぞれの立場から見ると別の歴史がある。この話でいうと、ヨーロッパでは、隣の国と話し合って同じ教科書を作ろうじゃないか、という試みがあるんです(注2)。
もっと最近の、ECとかEUの影響で始まったのかな、と思ってたんですが、実は第一次大戦が終わった頃から。それまで、あまりにも一国中心的というか、はっきり言うと愛国主義的な歴史教育をした結果が、この戦争なんじゃないか、という反省があって。
国際連盟の、知的協力国際委員会(ICIC)で1925年にカサレス決議という、歴史教科書をお互いに検討しようじゃないかというものが採択されて、1930年代にもフランス・ドイツ関係教材を作る試みがありました。
これはナチスの台頭でポシャってしまうんですが、第二次大戦後、今度はICICを引き継いだユネスコ(国連教育科学文化機関)が支援して、1950年にはドイツとフランスとの間で「ドイツ・フランス国際歴史教科書対話」というのが始まってる。その後も何度も頓挫と再開を繰り返して、21世紀になってようやく、ドイツとフランスの間で教科書がまとめられました。日本語訳も出版されている『ドイツ・フランス共通歴史教科書』(注3)というものです。
面白いのは、ドイツ的には「悪いことをしてごめん」という態度で隣国へ話し合いに行くけど、それだとむしろ相手国の思いと噛み合わなかったりすることです。
そういうことが端的に表現される数字が死者の数です。
第二次世界大戦中の出来事について、戦後のドイツとチェコがやった話し合いですがドイツ側は「あなたの国の人を20万人殺したと思うけど」と伝えたところ、チェコ側から、「いやいや死者数は2万5千から3万人で、その内チェコ側(身内)の暴力による犠牲者も6千人いました」との答えが来たと……。
つまり、被害を受けたチェコ側が「あんたらの言うほど、あんたらは殺してないし、自分たちもこれだけ殺した」と言っている。
こうした議論を繰り返すことで、各国ごとに、ある程度の共通認識に基づいた歴史の教科書ができていきます。
実は日本の歴史家も韓国、中国の歴史家との間で、顔を突き合わせて、こういうことをやっているんです(注4)。それでもまだ、お互いの国の歴史認識の問題は、外交のカードに使われています。
フランスでは新しい世代が、フランスという国の歴史がいかによその国とのかかわり合いの中でつむがれていったかを示した、『世界の中のフランス史』という歴史書(注5)を書いています。
たとえば、フランス革命というのは、ワシントンと一緒にアメリカ独立戦争を戦ってた青年貴族の帰国をきっかけに始まったとか、ベルギーやオランダやイタリアから来てた亡命者がどうやってこの「革命」を出身国に持ち帰ろうと苦心したとか……。
この本はフランスでベストセラーになり、成功を受けて、イタリアやスペインだけでなく、フランドル地方、カタルーニャ地方、シチリア地方を対象に同じ方法で歴史書が書かれています。
ヒストリーからナラティブへ
Dain:そういえば、今回の読書猿さんとの「世界史対談」は最初、大英帝国の悪口から始めようとしていました。世界史を学べば学ぶほど、イギリスの悪行が目につきますから……。
たとえば世界で一番やっかいな紛争と言われているパレスチナ問題があります。世界史の教科書を読むと、これはイギリスの三枚舌外交が種を蒔いたんじゃないの? と思えてきます。この問題について、他ならぬイギリスの教科書では何て書いてあるのだろう……と疑問に思って、ニューヨーク公共図書館のレファレンスサービスに問い合わせてみました。
そこで教えてもらったのが、テルアビブ大学がまとめたワーキングペーパーです(“A Critical Survey of Textbooks on the Arab-Israeli and Israeli-Palestinian Conflict” The MDC for Middle Eastern and African Studies,Tel Aviv University,April 2017)
パレスチナ問題を扱っている教科書や副読本を並べ、その透明性や客観性について横並びにレビューしています。
どう記述しても危険な、政治的地雷原ともいえるテーマですが、一つ面白いことに気づきました。そこには、物語(narrative:ナラティブ)という言葉が非常に数多く出てくるのです(検索してみたら、全68ページの中で、historyは150回、narrativeは155回出てきました)。
読書猿:ヒストリーよりも、ナラティブが多い。
Dain:はい。お互いの宗教的な背景やイデオロギー、プロパガンダを「歴史」という形では、とてもじゃないけど記述できない。だから、イスラエル、パレスチナ、そしてアラブ諸国のそれぞれの国の「物語(ナラティブ)」という形で理解しあおう、という意図でナラティブという表現が使われています。いまは同意はできないけど、まず互いに理解するための、方法としての物語なんです。歴史の記述方法としての物語。これもまた、歴史の1つなのでしょうか。
読書猿:他国の歴史について「同意はできないけど、理解はする」という話はいいですね。
「歴史の記述にはナラティブも大事だ」となった時に、じゃあ、どうやって客観性を保つかという問題が出てくる。ただそれだけじゃなくて、そもそも客観的とは言えないような事柄について歴史学はどうアプローチしていくのか、できる限りの実証を重ねていくのか、という話もあります。
たとえば、ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』は、まさにそういう方向性の典型的な成果といえるのでは。
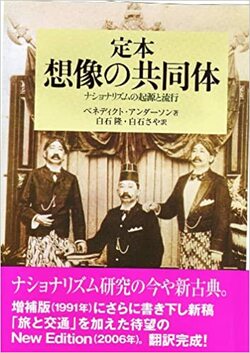 『定本 想像の共同体』(書籍工房早山)
『定本 想像の共同体』(書籍工房早山)
彼はニュースペーパー(新聞)などの資料を使って、どんな風にネーション(民族、国民)というものができていったか、その成り立ちを追いかけたけれど、本当に描きたかったのは民族の奥にある、ネーションを成立させるようなマインドというか集合的な心象でしょう。それは、例えば国家の公的な記録を調べるだけでは見えてこないんです。
確かに、権力闘争を勝ち抜いた者は、資料(記録)だけではなく、場合によっては記憶についても捏造したりできる。そうやって権力者の恣意的な選択によって残された記録や記憶で構成された「公的な歴史」が、あるべき歴史の姿かどうかはわからないし、実のところ、国家や権力者の「自画像」にすらならないんです。
権力者のやり方に人々がどう反応したか、なぜ受けいれたか/反抗したのかを理解するためには、起こった事実をまとめた「出来事の歴史」だけじゃなく、その時代を生きた人々の感情なんかを掬い上げることも必要不可欠なんですよ。
昔の歴史学では史料として使われなかった、参照されても重視されてこなかったようなもの、たとえば、新聞とか日記の断片とか絵画とか流行歌とか、どうでもいいものとして捨てられていた記録や記憶から素材を拾い集めて、時代の全体像を再構成するように、歴史学も進んできた、ということです。
Dain:歴史というか、歴史「学」の変化について、違和感があるのです。昔から、「歴史とは勝った方が書く」ものだと考えていました。だから、いま主流の価値観や集団に焦点を当てるのが普通だと思っていました。それぞれの時代の権力者が、自分の正統性の証(あかし)を過去に求め、上書き保存してきたのが、歴史叙述というわけです。現代の国ごとに歴史叙述が違っていたり、共通の歴史認識が持ちにくい出来事があるのは、そのせいだと思っています。
読書猿さんが言う通り、「権力者だけの歴史」だけではなく、その時代を生きた人のマインドや感情を扱うようになっています。いわゆる感情史とかサバルタン(疎外された人々)の歴史ですね。
こうした変化で違和感があるのは、何のための(誰のための)歴史なのか? という点です。
昔は、時の権力者が自らの権力基盤の正当性を誇示するために歴史家に「歴史」の執筆を命じました。今は? 疎外された人々や、記述から省略されていた部分に光が当たり、より多様な歴史記述になるのは、(読者であるぼくにとって)嬉しいことだと思います。ですが、その記述者はどんな動機付けがなされるのかが、分からないです。
卑近な喩えで言うなら、昔の歴史家は、自分の首が飛ばないために歴史を書きました。少し前なら、自分が属する国や民族のためでしょう(アイデンティティを守るため?)。じゃぁ今は? と考えるわけです。岩波の『岩波講座 世界歴史』と『世界史の考え方』は、こうした歴史学の変化への違和感も抱きつつ、読んでみたいです。
書評ブログ「わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」管理人
ブログのコンセプトは「その本が面白いかどうか、読んでみないと分かりません。しかし、気になる本をぜんぶ読んでいる時間もありません。だから、(私は)私が惹きつけられる人がすすめる本を読みます」。2020年4月30日(図書館の日)に『わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる』(技術評論社)を上梓。



