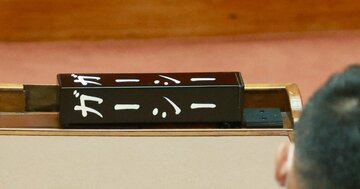2022年7月に行われた参院選の開票記者会見に、オンラインで登場したガーシー議員 Photo:JIJI
2022年7月に行われた参院選の開票記者会見に、オンラインで登場したガーシー議員 Photo:JIJI
ガーシー議員が本日3月15日に正式に「除名処分」となる見通しだ。個人的にはガーシー氏を肯定的に評価する気持ちは全くないが、除名は本当にいいことなのだろうか。筆者の中には、スッキリしない二つの違和感が残る。(経済評論家、楽天証券経済研究所客員研究員 山崎 元)
ガーシー氏個人を支持しないが
スッキリしない点が二つ残る
ガーシー参議院議員の処分が「除名」となるようだ。3月14日、参議院の懲罰委員会は同氏が議員資格を失う「除名」とする処分案を全会一致で可決した。15日の本会議で可決される見通しだ。
ガーシー議員が除名されることは、本当に適当なのだろうか。現在の法と制度において適当であることには何の異議もないが、物事の理屈を考えたときにスッキリしない点が二つ残る。
筆者がガーシー議員除名に感じた違和感を説明する前に、ガーシー氏に対する筆者個人の評価を述べておきたい。筆者は、政治家としても個人の活動としても、ガーシー氏を肯定的に評価する気持ちは全くない。手あかの着いた古い表現だが「1ミリもない」という語感がぴったりだ。以下で「除名」処分に対する違和感を説明することの目的が、ガーシー議員の応援にあるわけではないことを、ここではっきりさせておきたい。
個人のプライベートの暴露は、国民に秘した政府の密約を暴くような公益性がある場合を除いて、単に悪趣味であり、下品で迷惑だ。これは、ガーシー氏が行っても、『週刊文春』が行っても同じだ。