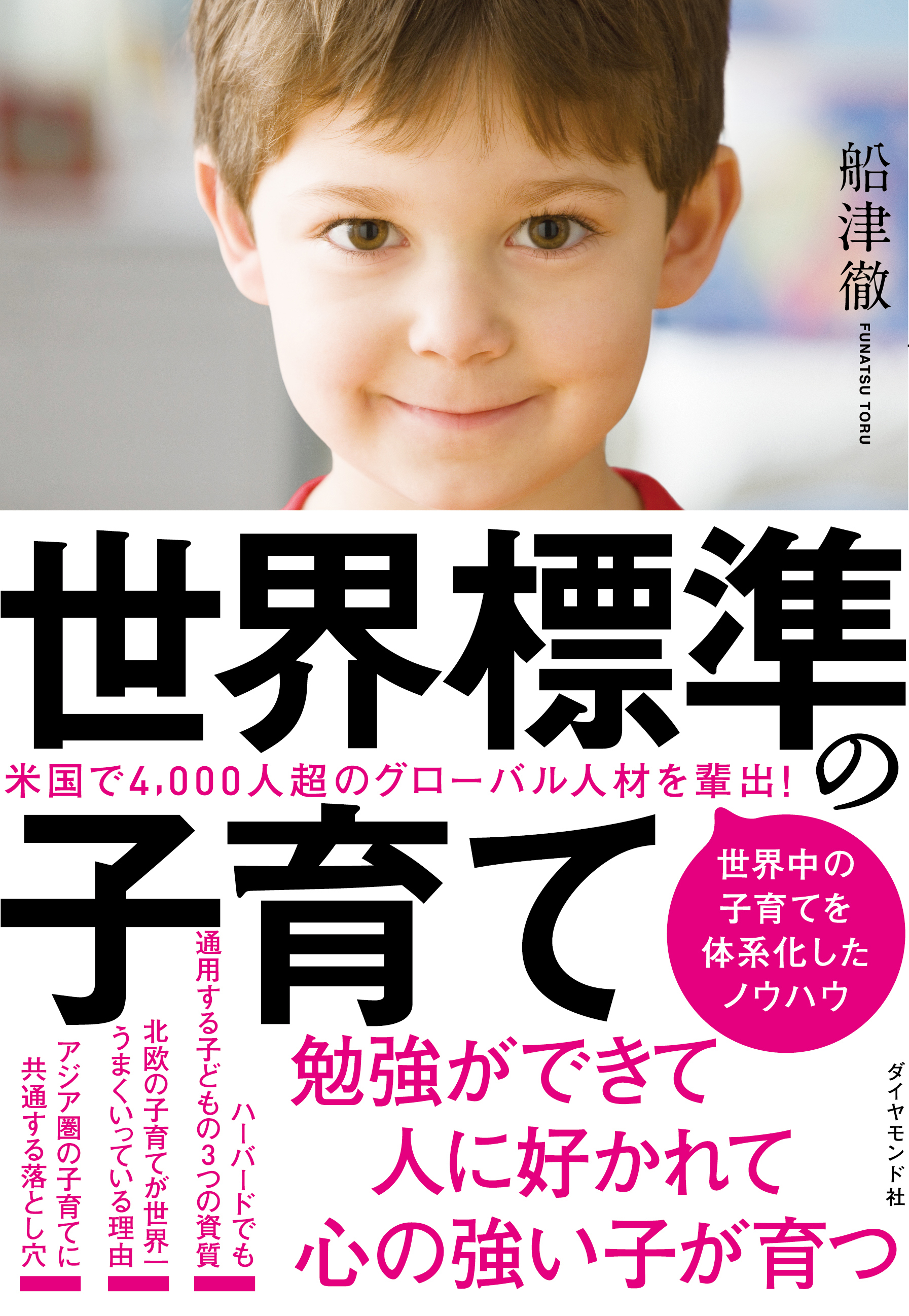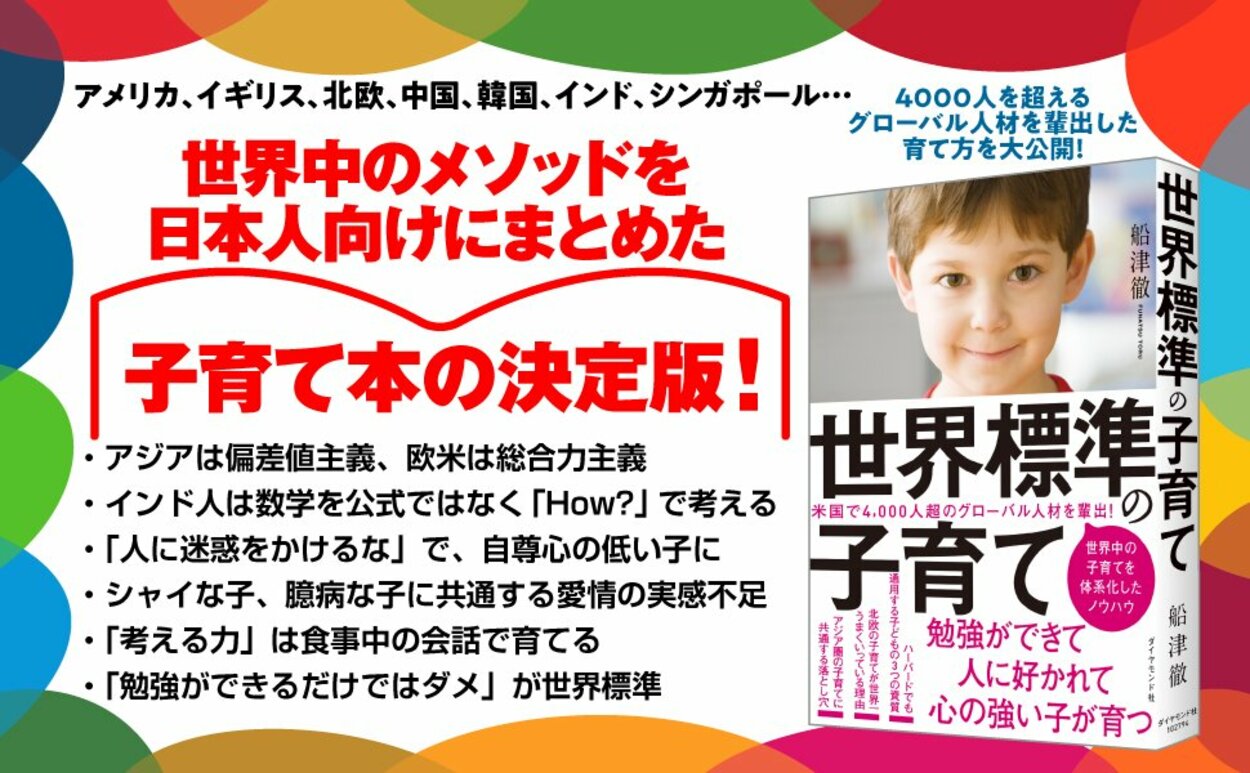子どもたちが生きる数十年後は、いったいどんな未来になっているのでしょうか。それを予想するのは難しいですが「劇的な変化が次々と起きる社会」であることは間違いないでしょう。そんな未来を生き抜くには、どんな力が必要なのでしょうか? そこでお薦めなのが、『世界標準の子育て』です。本書は4000人を超えるグローバル人材を輩出してきた船津徹氏が、世界中の子育ての事例や理論をもとに「未来の子育てのスタンダード」を解説しています。本連載では本書の内容から、これからの時代の子育てに必要な知識をお伝えしていきます。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
新しい環境に子どもを入れる時には
子どもが2~3歳になり、地域社会(公共の場所、友達の家など)や集団社会(保育園や習い事など)への参加が始まると、いろいろなルールにぶつかります。
それまで家庭で自由気ままに過ごしてきた子どもを、いきなり社会に出し、ルールに従わせようとしてもうまくいきません。
新しい環境に子どもを入れる時は、必ず「前もって」どこに行き、何をするのか、また、何をしてはいけないのかを言葉で説明してあげてください。
ある日突然親子教室に連れていき、「先生の言うことを聞いてね!」と言っても、子どもはどう行動していいのかわかりません。
だから不安になって泣き出したり、場所をわきまえず騒いだりするのです。
大人だって何の説明もなく、見知らぬ場所に連れて行かれたら不安になりますね。子どもにも必ず説明してあげましょう。
「今日は親子教室に行くよ。そこではお友だちと歌をうたったり、先生と体操したり、お絵描きをしたり、楽しいことをするよ。お教室では先生のお話を聞くのがお約束。◯◯ちゃんは守れるよね?」と説明すれば、2歳児でも必ず理解できます。
押しつけではなく、自分で考えさせる方向に
しつけの目的は「みんなと楽しく快適に過ごす方法」を伝えることです。
しつけがうまくいかないと悩んでいる親の多くはしつけでなく「押しつけ」をしてしまっています。
「いけません!」「ダメ!」「こうしなさい!」では子どもは動きません。それよりも、「どう行動すればまわりの人と楽しく過ごせるのか」を子どもに考えさせることにフォーカスしてください。
そうすると、子どもが適切な行動を自分で選べるようになるからです。
たとえば、子どもにあいさつを覚えさせたい時。
「あいさつしなさい!」と強制されても、子どもは「なんで知らない人にあいさつしなきゃいけないの?」と思います。
そこで、「笑顔であいさつすると自分も相手も楽しい気分になるよ!」とあいさつの意味を子どもに教えます。そして、親子で「笑顔であいさつ」を練習するのです。
「人に会った時は笑顔であいさつします。一緒に練習しよう? ◯◯ちゃん、こんにちは!」と、親子で練習したら外に出て実践します。
「今日はお友だちの家に遊びにいくよ。お友だちに会ったら笑顔で元気にあいさつしてね」と伝えておきます。
きちんとあいさつすると、「◯◯ちゃんは元気にごあいさつできてえらいね!」と周囲の人が褒めてくれます。
すると、「笑顔であいさつすると自分も楽しく明るい気分になること」を子どもが実感できるのです。
ママ友たちと協力して、子どもが笑顔であいさつできるように、お互いの家を訪問して練習させるのも良いでしょう。
上手にあいさつできたら「◯◯ちゃんはあいさつできてすごいね!」と大げさに褒めることを決まりごとにしてください。
また、家庭では親が率先して「笑顔であいさつ」を実践してください。
子どもが朝起きたら「○○ちゃんおはよう、よく眠れたかな?」と言って子どもを抱きしめます。
子どもはそれだけで明るい気持ちになります。親がいつも笑顔であいさつを心がけていれば、子どもも自然とあいさつができるように育ちます。
子どもがしつけを受け入れない時は、まず心を満たす
「何度叱ってもいうことを聞かない!」「わざと物を投げる!」「かんしゃくを起こす!」「床に寝転がってしまう!」と嘆くお母さんがいます。
そもそも「しつける」とは、子どもの「あるがまま」への介入であり、習慣変更を迫るものです。
これを受け入れるかどうかは、その時の子どもの「心の充足度」によって決まります。
子どもの情緒が不安定だったり、心が十分に満たされていない時に「しつけ」を伝えようとしてもうまくいきません。
子どもに情緒不安定の症状がある時は、しつけは一休みしましょう。そして子どもの心を充足させることを優先してください。
心を満たすには、添い寝をしたり、一緒にお風呂に入ったり、抱っこしたり、肌と肌とのふれあいを増やすことが一番です。
心が充足すればしつけを受け入れる余裕が生まれます。