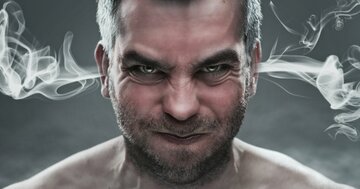「病気になりたくない」というのは、すべての人に共通する願いです。しかし、病気にならないためにどんな行動をとるべきなのかは「よくわからない…」という方が多いのではないでしょうか。
そんななか、「科学的に正しい」健康習慣の身につけ方を明かした、公衆衛生学者・林英恵さんの最新刊『健康になる技術 大全』が話題を呼んでいます。最先端のエビデンスをベースにした「健康に長生きする方法」を伝授する本書に、読者からは「健康関連本としてはブッチギリのベスト」「一家に1冊置いておくべき」と激推しの声が続々と届いています。
本稿では、本書より一部を抜粋・編集して、日本人の「食」で気をつけるべきことを明かします 。
監修:イチローカワチ(ハーバード公衆衛生大学院教授 元学部長)
*書籍『健康になる技術 大全』の「食事の章」はケンブリッジ大学疫学ユニット上級研究員 今村文昭博士による監修
 Photo:Adobe Stock
Photo:Adobe Stock
塩分のとりすぎは危険
塩分のとりすぎは、日本人の死亡率を上げる要因のランキングで第6位、食品の中では第1位に位置づけられています(*1)。塩分のとりすぎが高順位に来てしまうのは日本に限ったことだけではなく、世界でも同様です(*2)。塩は、多くの料理に欠かせないものだからこそ、上手につきあわなくてはなりません。
 『健康になる技術 大全』P.46より
『健康になる技術 大全』P.46より
日本人の食文化において、味噌や漬物、梅干しなどの伝統的かつ健康的だと思われるような食事には塩分が多く含まれています。魚や納豆を食べたりなど、健康的な食品をとろうとする際にも、醤油をつけたり、塩分が含まれているものと一緒に食べることが多いのではないでしょうか。
日本人の食事と塩は密接に結びついているからこそ、何をどのようにしたら良いのか、戦略的に考えていかないといけません。
塩分摂取の推奨基準は厳しくなっている
塩に関する知見が積もり、その懸念が高まるにつれ、摂取基準も年々厳しくなっています。日本では、長い間、成人では1日10g以下といわれてきました。2005年には、女性のみ8g未満が推奨されていました(*3)。これは女性の方が、塩の摂取量による血圧などの影響を受けやすいためです(*4)。
そして、2023年には20歳以上の男女の食塩摂取量の目標値として男女1日あたり7.0g未満とすることが発表されました。(*5)。ちなみに、WHO(世界保健機関)では、さらに厳しく、1日5gを推奨としています(*6)。
胃がん・心臓病などのリスクが上昇
最近の調査では、平均で男性は11.0g、女性は9.3g摂取していることがわかっています。先ほどの基準に合わせると、男性も女性も推奨の量よりも超えて摂取しています(*7)。この10年では減少傾向にありますが、それでもまだ目標にしたい摂取量には達していません。
昔から人々の生活に欠かせなかった塩ですが、過剰摂取が与える健康への悪影響で悩ましいのは、血圧を上げることです(*8)。さらに関連して慢性腎臓病(*9,10)、心臓病や脳卒中のリスクが上がると考えられています(*11-13)。さらには骨粗しょう症(*14,15)、胃がんとの関連性(*16-20)も指摘されています。
予防のためにできること
予防のためにできることとして、まず、今、自分がどのくらい塩をとっているのかを知ることが大切です。
料理をする人であれば、1gがどのくらいの量か、食塩を含む食品をどのくらい食べているかを知った上で、普段どのくらい塩を使っているかを予想してみると良いでしょう。
買ったものを食べることが多い場合は、パッケージに塩の量が表示されているものもあるので、塩分が多そうなものを中心に想定してみましょう。コンビニエンスストアのおにぎりなどにも、塩は多く含まれています。
塩分量が、ナトリウムで表示されているものは、インターネット上で簡単に換算してくれるウェブサイトもあるので、利用すると良いでしょう(計算式は、食塩相当量(g)=ナトリウム量(mg)×2.54÷1000)。
外食が多い人は、店によってどのように塩を使っているかが異なるので、なかなか難しいと思います。そのような場合は、食べた食品を選ぶと一般的な食塩の量を教えてくれるウェブサイトがあるので活用しましょう。
(本稿は、林英恵著『健康になる技術 大全』より一部を抜粋・編集したものです)