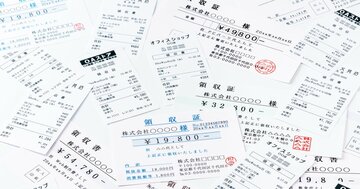定年前後の決断で、人生の手取りは2000万円以上変わる!マネージャーナリストでもある税理士の板倉京氏が著し、「わかりやすい」「本当に得をした!」と大人気になった書籍が、2024年の制度改正に合わせ改訂&パワーアップ!「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」として発売されます。本連載では、本書から抜粋して、定年前後に陥りがちな「落とし穴」や知っているだけでトクするポイントを紹介していきます。
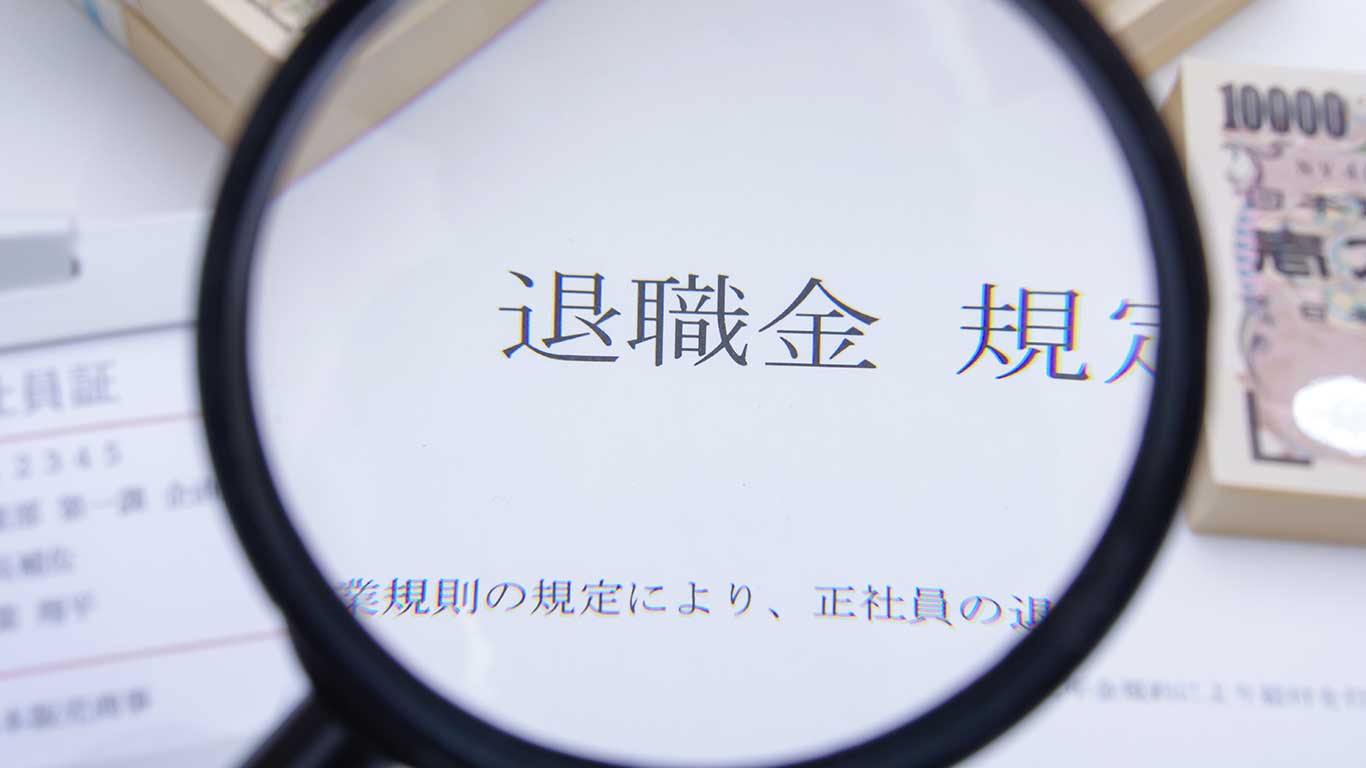 photo:Adobe Stock
photo:Adobe Stock
「確定拠出金」と「退職一時金」が両方あったら
もし会社の退職金制度に「確定拠出型年金」があった場合、節税のチャンスです。「確定拠出型年金」とは、会社側が掛金は出しますが、運用は従業員自身が行う年金です。運用がうまくいけば退職金は増え、失敗すると減ります。
会社側が運用した「退職金」(普通の退職金や確定給付型年金)の場合は「一時金」として受け取るか「年金型」で受け取るかは選べますが、基本的には「一時金」の受け取り時期を変えることはできません。それに対して従業員が運用していた「確定拠出型年金」の退職金は、基本60歳以降75歳までの間で好きな時に受け取ることができます。
一時金の退職金に加えて、「確定拠出型年金」の退職金もある場合、これをいつどのように受け取るかによって、退職金にかかる税金が大きく変わってきます。
65歳で辞めるなら、60歳で「確定拠出型年金」を、65歳で「退職一時金」をもらう
確定拠出型年金と退職一時金は基本的に年をずらしてもらったほうがオトクです。受け取る年をずらすことでそれぞれに低い税率が適用され、結果として「同じ年に受け取る」よりも税額が小さくなるからです。また「確定拠出型年金」は運用によって、受取金額も変わりますので、損が出ている時は、受け取らず運用を延長することもできます。一時金と確定拠出型年金の合計額が、退職所得控除額よりも低い場合は、まとめてもらっても税金はかかりませんから、分けてもらう必要はありません。
ただし、65歳以降に退職する人は、「確定拠出型年金」を先にもらえば非常にオトクになります。ちょっと難しい話なので、詳細な説明は割愛しますが、退職一時金と確定拠出型年金は受け取る期間が4年超空いていた場合は、退職金を受け取った時と確定拠出型年金を受け取った時の両方に「退職所得控除」を使うことができるので、税金が断然安くなります(確定拠出型年金の「退職所得控除」は掛金を拠出した年数で計算します)。
たとえば、勤続年数38年のAさんの場合。退職一時金が2500万円(退職所得控除2060万円)、確定拠出型年金が650万円(拠出年数18年、退職所得控除720万円)としましょう(実際には確定拠出型年金は市況によって額が変わりますが、同じだとして計算します)。
もし、65歳で合計3150万円を一緒に受け取るなら、退職所得控除は2060万円となり3150万円から2060万円を引いた額の2分の1の、545万円が課税対象額となり、所得税額は66万2500円となります。
ところが、60歳で確定拠出金650万円を受け取り、65歳で退職一時金2500万円を受け取るとすると、両方に退職所得控除が使えるのです。60歳で受け取る確定拠出金の650万円は退職所得控除720万円の中に納まるので税金はゼロとなります。また65歳で退職一時金を受け取る時も退職所得控除は2060万円なので、2500万円から2060万円を引いた2分の1である220万円が課税対象となり、所得税額は12万2500円となります。
5年ずらしてもらうだけで、40万円以上も税金が変わってくるのです。
つまり、65歳で定年退職する人であれば、60歳で「確定拠出型年金」を受け取り、65歳で「退職金」を受け取れば、OKです。この場合、気を付けるのは先に「確定拠出型年金」を受け取ることです。
先に退職一時金をもらった場合でも、19年超間を空ければ両方に「退職所得控除」を受けることができますが、「確定拠出型年金」は75歳までに受けとらなければいけないことを考えると19年も間を空けるというのは、あまり現実的ではないかな、と思います。
*本記事は「知らないと大損する!定年前後のお金の正解 改訂版」から、抜粋・編集したものです。