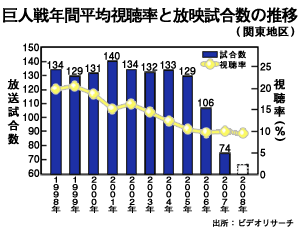一人勝ちの東京に対する
関西の誇りと気概の象徴
阪神タイガースのスポーツワールドは、そうしたもろもろの人々を包み込む。そのカギとなるのが応援団だ。タイガースのスポーツワールドには、正式なメディアとファン組織という、実質的には二つのメディアがある。そして、グラウンド上での試合と関西全域の公的、私的な空間をつなげ、タイガースに熱を上げている人も、そうでない人も巻き込んでいく結合組織としての応援団の重要性は、正式なメディアに勝るとも劣らない。
甲子園のファン(あるいはタイガースファンを論じる人々)は、よく“祭り”という名詞と“盛り上げる”という動詞を使ってスタジアムの雰囲気や流儀を説明する。祭りは日本の信仰生活、あるいは地域の社会組織の根幹を成す行事だ。神社仏閣が関連していることが多く、特に年に一度の祭りは寺社が中心となって盛大に執り行なわれる。キリスト教のさかんな地域で行なわれる聖人の日の祝い事と同様、パレードや饗宴、祈祷が伴い、パレードでは神様を安置した神輿が男たちの肩に担がれ、地域を巡回する盛大なものになる。みながよく知る踊りが始まると、厳粛な雰囲気は一転して賑やかな、ほとんど荒々しいものになる。その目的は、参加者の心を掴み、その瞬間に夢中にさせることだ。
盛り上げるとは、祭りの雰囲気をつくり出し、維持することを指す。
甲子園の試合と祭りが似ているのは明らかであり、そしてその意味は存外に深いと感じる。寺社での祭りと同様、球場はスポーツの聖域たるグラウンドと社交の場たるスタンドの融合した空間であり、観客の関心は、プレイとおしゃべりの両方に向いている。応援歌やユニフォーム、ジェスチャー、一体感が、なじみ深い祭りの雰囲気をつくり出していく。リーダーや太鼓叩き、ラッパ吹きは、祭りで神輿を担ぐ男たち、あるいは踊り手たちと同じ重要な役割を担っている。リーダーはほかの観客を代表して声を張り上げるのではなく、試合に没頭することを求めて音頭を取る。
そして、お祭りムードは失意の中でも維持される。甲子園の観客がむっつり押し黙ることはほとんどない。試合内容に関係なく野次を飛ばすだけの者もいるが、応援団は常に大挙して甲子園を訪れ、悲惨なシーズンの最後の月まで足を運び続ける。率先して盛り上げ、グラウンドのチームに失望させられることはあっても、自分たちはスタンドを失望させたりはしないという姿勢を示す。おそらく彼らは、チームのためというより阪神タイガースというもっと大きな存在のために行動している。
甲子園の体験を関西全域へ波及させるうえで、最後にもう一つ重要なのが、関西の派手好きな文化の介在だ。応援団や売店の店員のはっぴスタイルに、食べ物、横断幕、応援のパターン、グラウンドへ降り注ぐきつい関西弁の野次などは、どれも関西文化の彩りであると同時に根幹でもある。
高度な組織と自主性を備えた応援団が70年代から80年代にかけて発展したのは、荒くれ者やヤクザ、賭け屋といった体験を台無しにする連中から球場を取り戻すためだった。その後、応援団はテレビの要求に応じながら派手で元気な、しかし規律正しい観客の在り方を示し、野球中継の人気拡大に一役買った。無意識のうちに、関西の目立ってなんぼの文化を応援や行動に取り込んでいった。彼らの独立性を、チームとフロント、親会社はよく思わなかったが、それでも渋々ながら球場と観客をまとめ、時間を管理する役割を応援団に任せた。90年代には、球場とフロントもスタジアムMCやマスコット、チアガール、そして電光掲示板など、自分たちなりの仕掛けを導入したが、応援団にはかなわなかった。
その自主性は、主導権やアイデンティティー、当事者意識、チーム愛の面で、言い換えるなら応援団が阪神タイガースのスポーツワールドに居場所を確保するうえで重要だった。また、球場体験を地域に波及させるためにも欠かせなかった。日本語には“一体感”という言葉がある。自宅で、夜の宿直室で、街のあらゆる場所でナイトゲームを視聴していると、アナウンサーの実況と解説者の分析の向こうからファンの発する音が聞こえてきて、それが遠くのファンをプレイや観客とつなげていく。
しかし、そうしたつながりがあるからタイガースは特別なのではない。特徴的な球場と観客、球団の歴史的事情という土台、そして域内に広く浸透した派手好きな文化などが組み合わさることで、このスポーツワールドは、ファンが重要な役割を担う特徴的な構造を成している。
わたしは冒頭で、スポーツファンのアイデンティティーには、スポーツの性質に根ざした矛盾する二つの側面があり、それが決定的に重要な意味を持っていると述べた。ホームとロードという大会の構造と、ホーム球場が一か所に固定されている事実が、チーム間のライバル関係と地元愛を強める。
チームを応援すれば地元愛は増すが、逆もまた然りだ。観客は、自分が大阪人で、タイガースが大阪のプライドの担い手だからという理由でファンになることもあれば、タイガースファンになることで大阪人としての誇りと自覚を深めていく場合もある。応援団も、メンバーと知り合いだったからという理由で入団する人もいれば、応援体験を通じてメンバー間の絆を深め、維持する人もいる。
そうしてタイガースは、一人勝ちの東京に対する関西の誇りと気概の象徴になってほしいという、人々の膨大な想いの受け皿となっていった。残り二チームはどちらも成績はよかったが、パ・リーグの所属ゆえ、タイガースのように年に何十回もジャイアンツと対戦することがなかった。60年代以降の日本の情勢を語るうえで欠かせないのが、関東と関西のパワーバランスの急変、特に関西が経済の主導権を東京へ譲り渡し、政治経済の両面で存在感を減じていったことだ。そのなかで、地元の識者も、一般のファンも、さまざまなレトリックを駆使して両者の対照性を示し(東京VS大阪、お上VS地元の商人、国の冷淡さVS地元の誇り、巨大な有力企業VS脆弱な小企業)、そしてそれが象徴的に凝縮されて表れたのが、タイガースとジャイアンツのライバル関係だった。
その対抗意識は、敗北の克服というスポーツの普遍的課題への回答にもなる。試合では選手とファンの半分が、シーズンでは一チームの選手とファンを除いた全員が負ける。であるなら、それだけ頻繁に“負ける”ものに自身のアイデンティティーを委ねるのはなぜだろう。これもタイガースに深く関わる問題だ。何しろこのチームは、(ジャイアンツとは逆に)50年にわたって手ひどく失敗し続けてきた。タイガースが成功を収めていたプロ野球黎明期の30年代や40年代は、大阪そのものが東京と対等だった。しかし戦後の数十年で大阪の力は目減りし、合わせてタイガースの運命も暗転していく。多くのファンが、それを必然であると同時に不当だと感じた。だから、リーグを席巻するジャイアンツ(つまり東京)への敵愾心を強め、さらにジャイアンツに挑む気骨も、財力も欠けているように思える阪神電鉄も批判した。タイガース応援団の特徴である保守的な自主性は、そうした複雑な感情から生じていたのだ。(次回に続く)