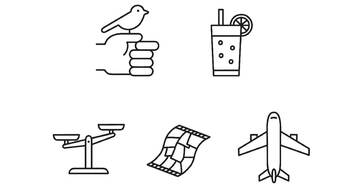2001年に経営学分野で最高峰の学術雑誌『アカデミー・オブ・マネジメントレビュー』上で発表されて以来、アントレプレナーシップや価値創造など幅広い領域に大きなインパクトを与えてきた「エフェクチュエーション」についての日本初の入門書、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』が発売されました。多くの人にとっては耳慣れない「エフェクチュエーション』という概念について知っていただくため、本連載では同書の一部を紹介していきます。
第7回は、「5つの原則」のうちの1つである「許容可能な損失」について解説します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
熟達した起業家は「命がけのジャンプ」をしたりはしない
あるアイデアを着想した場合に、本当にそれを実行するのか。あるいは、複数のアイデアがある場合には、一体どれを実行するのか。
こうした意思決定に際して、「コーゼーション(causation:因果論)」に基づく発想では、一般的に期待できるリターン(期待利益)の大きさが、判断基準として用いられてきました。つまり、行動の結果として、投下した資源以上の大きなリターンが期待できるならば実行すればよい、と考えるのです。複数の行動の選択肢がある場合にも、最も期待利益の大きいもの、つまり最も成功しそうなものや儲かりそうなものを選ぶべきだと考えられます。
ただし、環境の不確実性が極めて高い状況では、どれほど精緻に期待利益を予測しようとしたところで、それが得られる保証はどこにもありません。
だからこそ、こうした高い不確実性に繰り返し対処してきた熟達した起業家は、事前に予測された期待利益ではなく、逆にマイナス面、うまくいかなかった際に生じる損失可能性に基づいて、行動へのコミットメントを行う傾向がありました。将来得られるだろう大きな期待利益のために大胆なリスクを取るという、ハイリスク・ハイリターンに賭ける一般的な起業家のイメージとは異なるかもしれませんが、熟達した起業家は、不利な面を十分に認識したうえで、避けられるならば絶対にリスクは取るべきではない、と考えていたのです。
実際に、エフェクチュエーションの発見に至った意思決定実験に協力をした27名の起業家の誰一人として、リターンの可能性を予測するために特別な努力を払ったり、それに基づいて投資水準を決めたりしませんでした。そのかわりに、「失うことを許容できる範囲(afford to lose)」においてのみ資金を使おうとする傾向や、出費をできるだけ抑えようとする傾向が見られました。
つまり彼らは、予期せぬ事態は避けられないことを前提としたうえで、最悪の事態が起こった場合に起きうる損失をあらかじめ見積もり、それが許容できるならば実行すればよい、という基準で意思決定を行っていたのです。これがエフェクチュエーションを構成するもう1つの思考様式である、「許容可能な損失(affordable loss)の原則」です。
「許容可能な損失」の範囲で行動する利点
ここでいう起こりうる損失のなかには、行動のために投資されたあらゆる資源が含まれます。当然資金以外にも、費やした時間や労力、協力者からの期待、犠牲にした別の機会などが、うまくいかない場合の損失になりうるでしょう。それがどのような種類の損失であれ、起業家が、どこまでなら損失を許容できるかの推定に基づいて意思決定をすることで、予測に頼らなくても済む状態を作り出すことができます。
期待利益を計算する場合には、未来の売り上げや資本コストに関するリスクなど、さまざまな「予測」に基づく評価を伴いますが、許容可能な損失を計算する場合には、現在の財務的状況と、最悪のケースに備えた心理的コミットメントの評価を知るだけでよいのです。
損失が許容できる限りにおいてコミットメントを行うことには、いくつもの利点が指摘されます。第一に、うまくいかない可能性が事前に考慮され、なおかつそれを自分が受容できることがわかっているため、新しいことを始める心理的ハードルが低くなるといえます。第二に、最悪の事態が起こった場合に失うものに対して、事前にコミットメントを行うため、成功するかどうかの予測に無駄な労力を費やす必要もなくなります。そして第三に、うまくいかなかった場合でも失敗が致命傷とはならないために、再度別の方法でチャレンジすることが可能になるのです。この最後の点は特に重要ですので、少し説明を加えたいと思います。
不確実性が高い環境では、思い切って行動を起こしたところで期待通りの結果が得られないことは往々にしてありえます。そうした結果は、いわゆる「失敗」と呼べるものですが、失敗することそれ自体が問題であるわけではありません。失敗が問題になるのは、それが許容不可能な損失を発生させた結果、起業家がそれ以上取り組みを継続できなくなり、諦めざるを得なくなるためだといえます。
逆に、起業家の行動が「許容可能な損失」の範囲に収まる限りにおいては、失敗といわれる結果が致命傷を生まないため、再度別の方法でチャレンジすることができます。そして、再チャレンジの際には、先の失敗経験からの反省が何らかの形で活かされることでしょう。つまり、許容可能な損失の基準で行動する限りにおいては、過去の失敗経験はむしろ、後の成功確率を上げてくれる学習機会と見なせるようになります。
「失敗は成功のもと」という言葉の通り、先行する失敗経験からの学びが、その後の成功をもたらしたと考えられる事例は多く存在しています。たとえば、アップル社の歴史のなかで失敗事業とされるものの1つに、同社が世界初のPDA(個人用携帯情報端末)として1992年に発売した「Newton(正式名称:Message Pad)」シリーズがあります。
ジョン・スカリーCEOのもと1987年に開発に着手し、スタイラスペンによる手書き認識機能を初めて搭載した革新的な製品として1993年8月にリリースされたものの、高額な価格や手書き認識機能のトラブル等の要因により売り上げが伸びず、創業者のスティーブ・ジョブズがCEOに復帰した翌年1998年に完全な事業撤退がなされました。ただし、このNewtonの失敗経験からの学習が、その後に発売されて大ヒットした「iPhone」や「iPod touch」といった製品の開発にとって何らか活かされたのではないか、と想像することは難いことではありません。