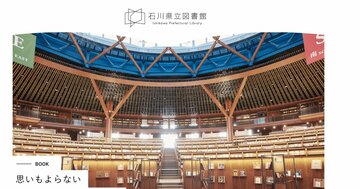学校より図書館に通った菊池寛
下足番に抱いた強い印象
1908年、上京してから足繁く帝国図書館に通った人物に菊池寛がいた。「半生を学校へ通うよりはもっと熱心に図書館へ通った男」を自任する彼は、高松から上京して、「私は東京の何物にも感心しなかったが、図書館にだけは、十分驚きまた十分満足し、これさえあればと思った」と回顧している(菊池寛「半自叙伝」)。
菊池の小説「出世」は、帝国図書館の下足番に光を当てて当時の図書館利用を描いている。田舎の中学校を出て上京した主人公の譲吉だったが、学生時代の生活は貧しく、窮乏するなかで図書館通いをしていた。それは彼にとって「一番みじめな事」でもあった。
帝国図書館に入館するには地下で下足を預け、上草履と交換する必要があったが、あるとき譲吉は履いていった草履があまりにみすぼらしいという理由で、下足番から預け札の交付を拒否された上、嫌味を言われてしまう。意地悪で無口な下足番に対し、譲吉は反発を覚えるが、同時に一生この地下で仕事をする彼に内心で同情を抱いた。
数年後、大学を卒業し、自ら職を得て図書館を訪問した譲吉は、下足番がいないか探してみたところ、何と閲覧券売場の係に「立派に出世」しているのを発見したという話である。
「出世」は、図書館がエリートたちの地位上昇の足場の1つだったことを背景とした作品であるが(日比嘉高編『図書館情調』)、全ての利用者と顔を合わせる下足番は、帝国図書館の司書よりも利用者にとって印象を残す存在だったといえる。
この下足番にインタビューを試みた新聞記事もある。それによれば、下足番の仕事は請負で、日当は30銭、夏場は15時間ちかく座りどおしで、900人近い利用者の下足を捌さばかねばならず目が回りそうなほど忙しいことが語られている。
また容易にトイレにも行けず、しかも閲覧者に渡す上履は図書館が支給するのではなく、請負業者側の負担であることなど、過酷な労働環境が知られる(「下足番」『東京朝日新聞』1908年11月30日)。
「マナー問題」の歴史は100年以上
閲覧席での居眠りと私語は300件超え
帝国図書館にはマナーの悪い不届きな利用者もいたようである。故意に書籍を毀損する者や、カード目録に悪戯をして汚す者、勝手に心棒を動かしてカードを抜き取る者、壁に落書きする者まで見られた。
そこで帝国図書館側は1906年5月、万一このような行為に及ぶ者がいたら係員に「密告」すること、密告者に対しては「相当ノ謝儀」を与えるという掲示を出した。帝国図書館内には巡視がおり、居眠りや私語などを厳しく注意して回っていた(西村正守「上野図書館掲示板今昔記その2」)。