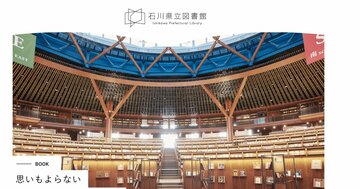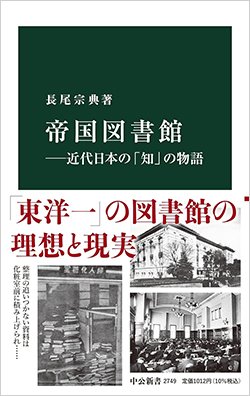 『帝国図書館 近代日本の「知」の物語』(中央公論新社)
『帝国図書館 近代日本の「知」の物語』(中央公論新社)長尾宗典 著
明治末から大正初期にかけて、お茶の水高等女学校の生徒として帝国図書館に通った作家の宮本百合子は、「上野の図書館は決して愉快なところでもなければ、図書館として充分利用出来る便利な処でもなかった」といい、その雰囲気は「役所くさい、うるおいのない調子だけで親しみ難かった」。出納台に至っては、「あんなに高い、絵にある閻魔の大机のようなのなどは寧ろ愉快な滑稽だ」と語る(宮本百合子「蠹魚」)。
何度か利用するなかで違和感がうすれていく利用者もいただろうが、それは居眠りや私語、閲覧室内の飲食、持参品のインキ壺、閲覧証の記入方法に至るまで微細に注がれる管理の視線を受け入れたともいえる。
しかしそれは、利用者が常に従順だったことを意味しない。たとえば当時の帝国図書館内の落書きを書き留めた随筆によると、地下室食堂の壁には、「下足の老父今少し丁寧にす可し(但し一銭やればおせじを云う)而し気の毒な者なり」「売店の菓子店に言う菓子を安く売れ十七八年の女を入れろ」などというのがあり、さらに館外玄関の正面板は、満員で待ちぼうけを食った利用者が「自暴自棄半分に」大量の落書きを残していたという。
曰く「図書館は勉強家の来る所に非ず」「亡国の気象を図書館養生し」「三十人待つのに三時間かかった」「待つ人の心も知らぬ馬鹿俗吏」「立ん坊養生所」「満員で待って居る時は館員どもをぶんなぐってやりたい」「駄小説などと首引して貴重なる時間を徒費してる青年は早く出ろ」「こんなにまたす図書館があるか」「気長の養生所」「速に増室を望む」等々(鵜の目鷹の目生『落書の東京』)、図書館への憤懣が綴られている。
落書きをそのまま利用者の「生の声」と解釈するのは一面的だが、帝国図書館文書の『閲覧室掲示其他閲覧室に関する事項』に綴じられた注意喚起の掲示を見る限り、一向にマナーが改善された形跡がない。
食堂備え付けの新聞紙や灰皿を暖炉に投入するとか、ゴミを屑籠に捨てないとか、持参した弁当を無断で備え付けのストーブに置いて温め異臭騒ぎを起こすとか、帝国図書館は結局のところ始終このようなしたたかな利用者を抱え込んだのであり、監視の視線と利用者の要求は絶えずせめぎあっていたといえよう。