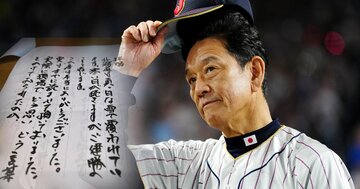京セラ創業、KDDI躍進、JAL再建――稀代の名経営者、稲盛和夫は何を考えていたのか?
2つの世界的大企業、京セラとKDDIを創業し、JALを再生に導きますが、稲盛和夫の経営者人生は決して平坦なものではありませんでした。1970年代のオイルショックに始まり、1990年代のバブル崩壊、そして2000年代のリーマンショック。経営者として修羅場に置かれていたとき、稲盛和夫は何を考え、どう行動したのか。この度、1970年代から2010年代に至る膨大な講演から「稲盛経営論」の中核を成すエッセンスを抽出した『経営――稲盛和夫、原点を語る』が発売されます。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
「トップは孤独だ」
私は一九五九年に、中京区西ノ京原町で宮木電機の倉庫をお借りして二八人で京都セラミックという会社を始めました。
当時宮木電機の専務でいらっしゃった西枝一江さんをはじめ、社長の宮木男也さんや、常務の交川有さん等々に出資していただいて、資本金三〇〇万円をつくっていただきました。さらに西枝専務は、京都銀行にお願いされて、自分の家屋敷を担保に一〇〇〇万円のお金を借りられて、運転資金として私に使わせてくださいました。
資本金の三〇〇万円と西枝さんが個人的に京都銀行から借りられた一〇〇〇万円、合わせて一三〇〇万円を元手に京セラは始まったのです。
会社を始めて、最初に遭遇したのはトップの重責でした。つくったその日からものを買うにしても、給料を払うにしても、部下があらゆることについて私に、「これはどうしましょう」と相談に来ます。それを一つひとつ、「やっていい」「ダメだ」と私が判断をしなければならない。
そのたび、たいへん困りました。私は立派な家柄の生まれではなく、立派な経営者が親戚にいたわけでもありませんので、人を頼ることができません。私自身にもちろん経営の経験はありませんから、経験則を頼ることもできません。また、工学部の出身で、経済も経理も勉強したことがありませんから、知識を頼るわけにもいきません。
そういう無い無いづくしの私が、会社のトップを務めなければならない。トップとして「やっていい」「ダメだ」と、キリキリ胃の痛むような判断をしなければならない。
「自分の判断がもし間違っているなら、会社の存続に響くかもしれない。深く考えずに決めようとしているけれども、それは実は会社の命運を決める事柄なのかもしれない」と思うと、あまりの責任の重さに、眠れない日が続きました。
そのときに「トップは孤独だ」という言葉を本で見つけ、「なるほど」と思いました。経営者は、番頭さんにも、奥さんにも、周囲の人にも相談ができない。本当にぎりぎりのところで決断を迫られる。一〇万円、一〇〇万円の日常茶飯の決裁をするにしても、それは自分の責任で決裁をしなければならない。
その決裁をするにはぎりぎりまで悩まなければならない。それも、相談ができない孤独さの中でものを決めていかなければならない。
「経営者というのはすごくたいへんなんだな」と私は思いました。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「人間として正しいこと」
どのようにして物事を決めていくべきか、散々悩んだ挙げ句、「会社経営を知らないんだから、人間として何が正しくて、何が正しくないのかということに基づいて決めよう」と思いました。つまり、物事を判断するには基準が要るわけですが、その基準をもっていないので、私はそう考えたのです。
小学校しか出ていない私の両親や祖父母が子どもの頃から私に、「あれはやってはいかん」「これはやっていい」「人間としてそんなことでは困る」と言って教えてくれた、本当にプリミティブな、人間として正しいこと正しくないことや、小学校、中学校、高校のときに、修身の先生に教わった、やっていいこと悪いこと、そういったものを判断基準にしようと思いました。
それしか私には方法がありません。大学の哲学科を出たわけでもなければ、心理学科を出たわけでもありません。私にはそれしかありませんから、両親や学校の先生に教わった何が正しいのか正しくないのかを判断基準にしようと決めました。
ただし、「それをそのまま社員に言うと、ばかにされるかもしれない」と思ったものですから、私は「原理原則に基づいて判断をします」と言うようにしました。わけがわかったようなわからないような言い方ですが、つまりは、「人間として根本的に何が正しいのか、正しくないのかに基づいて判断しよう」と考えて経営を始めたのです。
考えてみると、会社をつくったときに経営の原点に据えた、このプリミティブな判断基準のおかげで今日の京セラがあると思います。
もし私に中途半端に経営の経験があったら、もしくは、三〇~四〇歳ぐらいまで大企業にサラリーマンとして勤めて、ある程度の経営の方法を知っていたとしたら、そして、うまく根回しをしたり、妥協をしたり、周辺の人に取り入ったりする社交術のようなものまで含めて経営の方法だと思い込んでいたとしたら、私はそういった経験則に基づいて経営し、失敗していただろうと思います。
(本原稿は『経営――稲盛和夫、原点を語る』から一部抜粋したものです)