とくに若者はそのコンテンツを消費するのにかかる時間を気にする傾向があり、映画にしてもYouTubeの動画にしても、何分で観終わるのかを事前に知ることがストレス軽減につながるようだ。
そのため、彼らにとってはコンテンツのおもしろさだけではなく、何分で終わるかという点も消費する判断材料になるのだ。
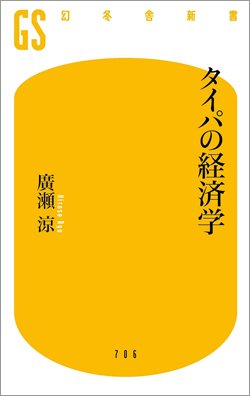 『タイパの経済学』(幻冬舎新書) 廣瀬 涼著
『タイパの経済学』(幻冬舎新書) 廣瀬 涼著
試合が何時に終わるかわからないというのは、試合視聴後の自身のスケジュールに少なからず影響が及ぶ。番組表に22時に試合終了予定と書いてあるから、22時に風呂に入ろうと段取りを組んでいたのに、結局試合が終わったのは23時過ぎで寝るのが遅くなった、といった類の経験を私たちは幾度も経験しているだろう。
どちらにせよ、サッカーにしても野球にしても、TikTokやTwitterなどSNS上でハイライト動画が拡散されることが一般的となった。その投稿のリプライ欄を見れば、そのシーンのポイントやその動画に関連する過去映像、活躍した選手の裏話などがファンによって解説されていて、一連の投稿を見るだけで知ったつもりになれるし、十分すぎるほどの情報を入手することができる。
また、SNSのタイムラインで友達が盛り上がっているときを見計らってチャンネルを合わせれば、ご丁寧にそのシーンのリプレイが流れている。
スポーツ観戦そのものがタイパが悪いというよりは、その試合のハイライトや、他の観衆が何に対して盛り上がったのかというポイントがリツイート数、「いいね」数、再生回数、コメント数といった形で計量化されるため利用しやすくなり、ノーコストで「観た状態になれてしまう」という市場環境が、相対的にタイパの悪さを演出してしまっているのだろう。
テレビにずっとかじりついていなくても、得られるコミュニケーションの質は同じだと感じているのかもしれない。







