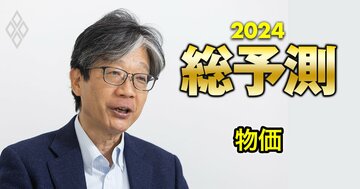だが中小企業の賃上げに向けた環境は昨年よりも整いつつある。賃上げの原資となる中小企業の売上高は23年1~9月で前年比+5.0%と、大企業の同+2.4%を上回った。また日銀短観では、中小企業の仕入価格判断DIは低下する一方で販売価格判断DIは上昇しており、価格転嫁が中小企業でも進んでいることを示唆する。
背景には、21~22年の輸入物価高を契機に企業の価格設定行動が積極化したことがある。そのため、原材料費に加え人件費の価格転嫁も進みやすくなった。大和総研の分析によれば、21年以降、人手不足感の強まった業種では販売価格をより引き上げる傾向がある。同様に人手不足に直面する中小企業でも、賃上げによるコスト増を販売価格に転嫁する動きが強まろう。
一方、価格転嫁が十分に進まず、収益が悪化するリスクも残る。大幅な賃上げを行う大企業は、コスト削減のため中小企業に過大な値下げを要求する可能性がある。政府は企業間の価格転嫁動向を監視するなど、適正な価格転嫁を促す取り組みが引き続き必要だ。
もちろん、中小企業自体が収益力を高めることも重要だ。製品やサービスの差別化、省人化投資や人的資本投資の拡大などによる生産性上昇を通じて、価格転嫁力を一段と向上させることが求められる。中小企業での大幅な賃上げの継続が、経済全体での賃金・物価の好循環実現への試金石となる。
(大和総研 シニアエコノミスト 久後翔太郎)