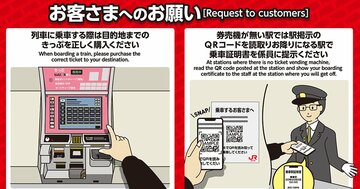運営会社の設立から
約20年でようやく開業
とはいえ、博覧会までの3年間では実現は困難で、オイルショックの影響もあって、計画は持ち越しとなったが、その間にも沖縄の道路事情は悪化の一途をたどった。
モノレール計画のその後を伝える『運輸と経済』1978年2月号によれば、1977年11月4日の那覇交通(現在の那覇バス)路線バスは、那覇市中心部の国際通り1キロで1時間の渋滞、通常1時間20分の路線が2時間45分を要したという。乗客はバスから降りて歩いて向かうありさまで、もはや公共交通は機能不全に陥っていた。
1978年の計画では、1972年の第2次案をベースに、首里から第1次案の終点だった石嶺を経由して浦添に至る路線となり、開業目標を1985年と定めた。1980年に都市モノレール法に基づく事業として採択され、1982年に運営会社として沖縄都市モノレールが設立されるが、その先が長かった。
導入空間を確保するための道路整備や、ルートの選定、路線バス各社との調整を経て1995年に軌道法に基づく特許申請。翌年に起工し、2003年に開業するが、会社設立から約20年が経過していた。
ようやく開業にこぎつけたものの、長らく鉄道が存在しなかった上、「ウチナータイム」と呼ばれる独特の時間感覚を持った沖縄の人々にモノレールは定着するのか不安の声もあり、沖縄都市モノレールは街宣車で開業をPRしていたほどだった。
だが、モノレールを中心としたまちづくりを進めたことで、2016年度の利用者数は、特許申請時の需要予測である1日当たり5万人を超え、単年度黒字化も達成した。2019年の延伸区間でもまちづくりが進んでおり、ゆいレールの存在感は今後、ますます高まっていくだろう。
構想から50年にわたるモノレール実現の取り組みは、開業から20年を経て立派な花を咲かせつつある。沖縄の事例は今後、新たに軌道系交通の導入を検討する各地の自治体にも大いに参考になるはずだ。