東京と地方の格差
大企業と中小企業との格差
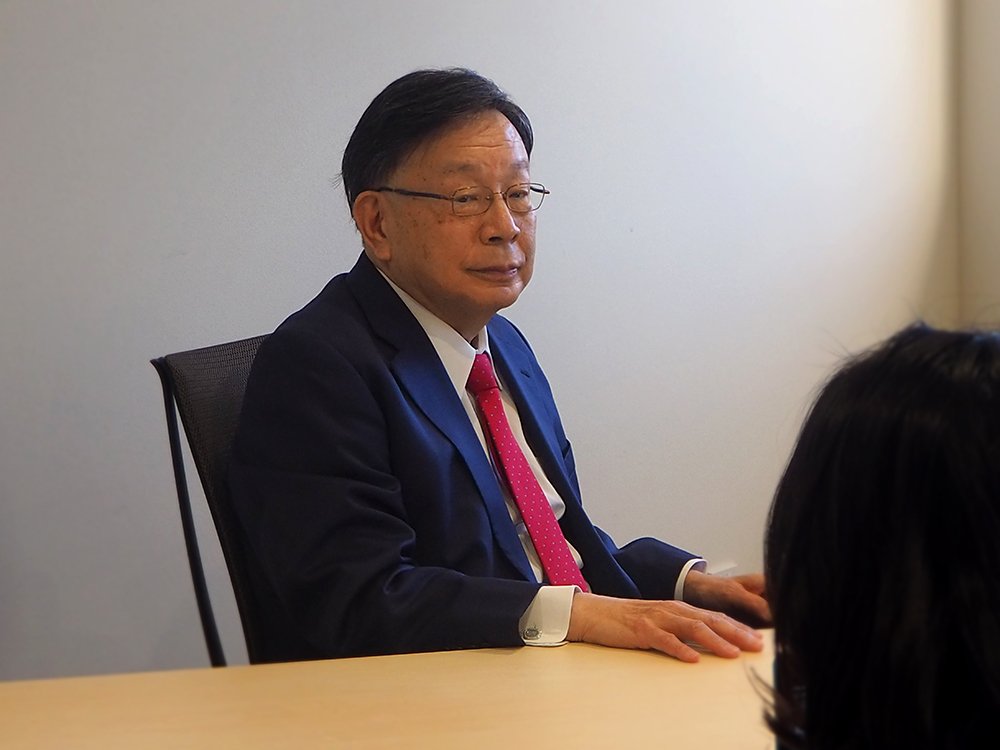 木村義雄(きむら・よしお)
木村義雄(きむら・よしお)政治家、元厚生労働副大臣。香川県生まれ。自由民主党所属。厚生労働副大臣(第1次小泉第1次改造内閣)、衆議院災害対策特別委員長、衆議院議員(7期)、参議院議員(1期)、香川県議会議員(1期)。議員歴30年。「外国人労働者等特別委員会」委員長など外国人材分野の最先端で、医療、福祉、労働といった諸問題、特に技能実習制度の上部構造である特定技能制度の原案作成に携わる。
木村 東京と地方では、最低賃金の格差があります。1時間で約200円違う。年間で約2000時間働くとして、1年で約40万円の開きが出るわけです。技能実習で3年間いると、約120万円の差です。
地方は人手不足で困っているのに、賃金が安いために地方には来てくれない。外国人の中には、日本への渡航費や生活費を工面するために借金している人も多い。それを早く返済するためにも、地方よりも東京で稼ぎたい。
そこへブローカーが実習生にコンタクトを取り、「手っ取り早く稼げるいい職場がある」と甘言で実習生を誘惑します。実習生の失踪者は毎年、数千人規模です。
渡部 それで、「難民申請をした人たちのうちの何割かは、技能実習制度から失踪した人」という構図ができてしまっています。
失踪の動機で多いのは、低賃金、賃金不払い、暴力など実習先での不適切な扱いです。失踪は、コロナ禍の前のデータで、全体の5%強ほどあったようです。
本来は、「母国での戦争や、迫害、人権侵害などから逃れて来た人」が日本政府に庇護(ひご)を求めるのが、難民申請です。しかし、「日本に残るための最終手段として、難民申請をする人」がいるのも事実です。コロナ禍では、難民が新規に来日し、難民申請することができなかったので、既存の技能実習生からの難民申請が25%ほどになった年もありました。2023年は難民申請全体の4%です。
私はおもに、アフガニスタンやシリア、アフリカなどから日本に来る難民の方々と関わる仕事をしています。日本は難民認定が厳格で、「難民」としての法的地位を得て、日本で生きられる道は、非常に狭いんです。
逆に難民認定は得られずとも、「移民」として合法的に働き暮らしていくという選択肢があれば、安心安全な場所で、彼ら・彼女らも活躍することができます。
木村 日本は人手不足といいますが、今でも、大企業が100人募集したら、1万人の日本人の応募があるでしょう。単に人手を解消したいだけなら、あえて外国人を採らなくてもいいわけです。一方で中小企業は、10人募集しても、1人来るかどうか。
本当に人手が欲しいのは、地方の中小零細企業であり、結局は、大企業と中小企業との格差問題をどうにかしないといけないんです。
 渡部カンコロンゴ清花(わたなべかんころんご・さやか)
渡部カンコロンゴ清花(わたなべかんころんご・さやか)NPO法人WELgee代表。静岡県出身。さまざまな背景を持つ子どもや若者が出入りする実家で育つ。大学時代は、バングラデシュの紛争地にて、NGO駐在員・国連開発計画(UNDP)のインターンとして、平和構築プロジェクトに参画。2016年、日本に逃れてきた難民の仲間たちと、WELgeeを設立。難民人材コーディネーションサービス「WELgee Talents」等を運営する。「Forbes 30 under 30」Japan / Asia選出。東京大学大学院総合文化研究科 人間の安全保障プログラム修士課程修了。
渡部 真剣に日本の人手不足を解消したいのであれば、企業や民間の努力だけではなく、国が本腰を入れて取り組まなければいけない問題なんです。
田原 移民問題というのは、大企業と中小企業との格差問題でもあるんですね。経団連はこの問題に対して動いていないのですか。
木村 大企業はよいとしても、その下請け工場で人が足りないため、経団連も、外国人労働者を受け入れるための仕組みづくりをしてほしいと言っています。安倍元首相にも陳情し、それで「特定技能」という制度ができたのですが、これがまだ道半ばです。
足りない人数分だけ、来てもらう形なので、来てくれた人がほかの職種やほかの場所に行くことは想定されておらず、融通が利かないんですね。
田原 地方で働いてほしい外国人が、東京で働きたがるなら、なぜ地方の最低賃金を上げないのでしょう。国や地方自治体が最低賃金を確保すればいいと思うのですが、何が障害になっているのでしょうか。
木村 最低賃金の差額を、地方交付税で補填したらどうかと、総務省の自治財政局幹部に提案したことがあります。しかし、逃げられましたね。財務省からお金がないといわれるに決まっているから、と。
渡部 転職の制限は人権侵害だという国際的な批判もあって、新制度では、転職の自由は一部認められました。これまで3年間は職場が固定されていたのが、条件さえ満たせば1年と、短くなりました。転職を防ぎたい中小企業からは、不安と悲痛の声が出ているようですが、たしかにそもそも根本的な課題である、賃金格差の解消に踏み込んではいませんね。
木村 これまでの制度を廃止して、先ほど田原さんがおっしゃった「育成就労」という制度が新設されることになりましたが、名前が変わっただけというか、これまでの制度を少しいじったぐらいですね。
渡部 そうですね。「廃止」のニュースは衝撃でしたが、結局、中身はほぼ踏襲されていますからね。
「働き方改革」が「働くな改革」へ
外国人労働者は味方がいない状況
田原 日本は島国で、もともと外国人労働者があまり入って来なかったので、これまでは移民問題は本格的な議論がされてきませんでした。
一方、アメリカは、賃金が高く移民に寛容だったので、移民がたくさん来た。ところが、それによって国内労働者の仕事が減るというので、移民抑制策を取った結果、人手不足になりました。イギリスもブレグジットによって同じく人手不足に悩んでいる。ドイツもメルケルが引退し、移民規制を強化しましたね。
渡部 欧米では、それまではどちらかというと移民を歓迎していましたが、今は一転して、バックラッシュ(揺り戻し)が起きていますね。世界全体が右傾化しているというか。
木村 人手不足というのは、移民の問題だけでなく、「働き方改革」の影響も深刻なんです。
田原 どういうことですか。
木村 残業を禁じて残業代をなくせば、経営者としてはコスト削減になるかもしれませんが、残業代がないとやっていくのが厳しい人にとっては深刻です。「働くな改革」になってしまっていて、稼げないとなると、特に清掃などのエッセンシャルな仕事に就く人が減っています。
今年(2024年)4月に労働基準法の3分野の追加改正が施行されたこともあり、これからもっと事態は厳しくなるでしょう。これが移民問題や難民問題と複雑に絡み合い、よりややこしくなってきています。
他方で、「日本は単一民族だ」と主張する人たちがいて、彼らは外国人が日本に来ることを認めない。かたや、企業の労働組合は、外国人労働者が増えることで、自分たちの給料が下がったり、職を奪われたりすることを懸念する。右派も左派も、両方が外国人労働者に対して厳しい。日本における外国人労働者は、味方がほとんどいない状況です。
渡部 技能実習制度では、例えば、「建設業で日本人だけでは何万人足りないから、建設業でその数だけ受け入れよう」と、あらかじめ決められているので、本来は、日本人と外国人労働者では、職の奪い合いにはならないような立て付けになっているはずなんです。
木村 一方で、その仕組みがまた障壁となって、ほかの職種へ移れなくなってしまっている。
渡部 そう。外国人労働者を、単なる「補足の労働力」としか見ていないので、簡単に転職できないような制度として始まりました。でも、日本に暮らし、働く中で、低賃金や職場の劣悪さに直面すれば、移動を望む人も出るでしょう。日本人と同様に「人間」なので。
田原 労働組合の話でいうと、1980年代ぐらいまでは、日本企業に非正規雇用者という形態は基本的にはなかった。ところが、小泉元総理大臣の時に、企業の人手不足を解消するため、非正規雇用をどんどん増やした。でもその時は、労働組合は反対しなかったんです。
なぜ反対しないのかと、当時、連合(日本労働組合総連合会)の会長に問うたら、われわれは正社員を守るための労働組合で、非正規雇用者はその対象ではない、といわれたことがあります。
木村 そういうことなんですよね。
田原 今、日本は人手不足で、しかも人口は減少していきます。今こそ、日本全体で移民問題を真剣に考えなければならないはずです。実習生というのは、今、日本に何人ぐらいいるですか?
渡部 実習生は約35万人です。
田原 外国人は今、日本にどのくらいいるのですか?
渡部 実習生や定住者も合わせて、現在、日本には約300万人を超える外国人が暮らしてます。日本の人口の約2.5%です。
これまでは、そこまで移民に頼らずとも、日本はやってこられたんです。でも、2100年には日本の人口は約半分になるといわれています。そこまで減らないよう、何とか人口8000万をめざすという提言が、民間の有識者や経済人などで構成される「人口戦略会議」で示されました(※)。そのためには、70年後までに外国人の比率を約10%にすることが必要だそうです。今は2%ですが、これを10%にしましょうと。
※参考:人口戦略会議提言書
「人口ビジョン2100」概要版 https://www.hit-north.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/02/02_gaiyo.pdf
「人口ビジョン2100」(本文) https://www.hit-north.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/02/01_teigen.pdf
「日本の人口を保つために外国人を入れる」、つまり、外国人の存在を人口増の手段にすることが正しいのかという疑問は個人的にはありますが、たとえそうしたとしても、それでも日本の人口は8000万人をぎりぎり保てるかどうかであり、高度成長期のような人口増加は今後も見込めないことは明らかです。
現在、日本に留学した人の約半数しか日本に就職していません。日本で学んだのに、カナダやオーストリア、香港などで就職する人も多い。実習生も、せっかく日本に慣れ、日本語や技能を身に付けて仕事を覚えたのに、制度上、望んでも定住できずに本国へ帰らざるを得ない。
田原 制度上とはどういうことですか?
渡部 定住するための道筋がないんですね。数年稼いで自国へ帰りたい人ももちろんいますが、一方で、できるなら日本で暮らして、働き続けたいという人だってたくさんいます。でも、これまでの制度では、「数年働いたら帰っていただく」という形になっていたので、長く日本にいたいと思っても、そういう選択肢が用意されていなかったんです。
日本企業からしても、新人研修を終えたら去ってしまうような短期のローテーションを繰り返しているようなもので、コスパの観点からもよくないですよね。
田原 実習生が日本で長期的に働けるよう、制度は変えられないのでしょうか?
渡部 それが、特定技能につながる今回の「育成就労」制度における変化でもあります。条件はありますが、事実上の定住も可能になりました。
ただ、ここまでの議論の中でも感じるのは、実習生が定住者になることに対して、日本の人々は強いアレルギーがあるのだろうということです。労働力はほしいけれど、定住はしてほしくない、という心理が、長らく前提として存在していたのだと思います。
田原 渡部さんは難民に関わるお仕事をされていて、そう感じますか?
渡部 短期的な観光の滞在だったり、期間限定の労働者としてなら歓迎する姿勢を見せていても、それが定住ビザに切り替わり、その人たちが家族を日本に呼び寄せ、継続的に納税をして、定住者として、日本社会の仕組みの中に入るとなると、この変化に抵抗を示す層は、やはり一定数、いると思います。
木村 日本はこれまで、異なる民族間の行き来があまりなくて、自分たちは単一民族であるというイメージが根強かった。さらに、戦後しばらくは何もしなくても人口が増えていた。そのため、移民に頼らざるを得ない状況は経験してきませんでした。でもこれからは人口が減り続ける。働き手が減り続ける。さて、どうしますか? というところが問われています。







