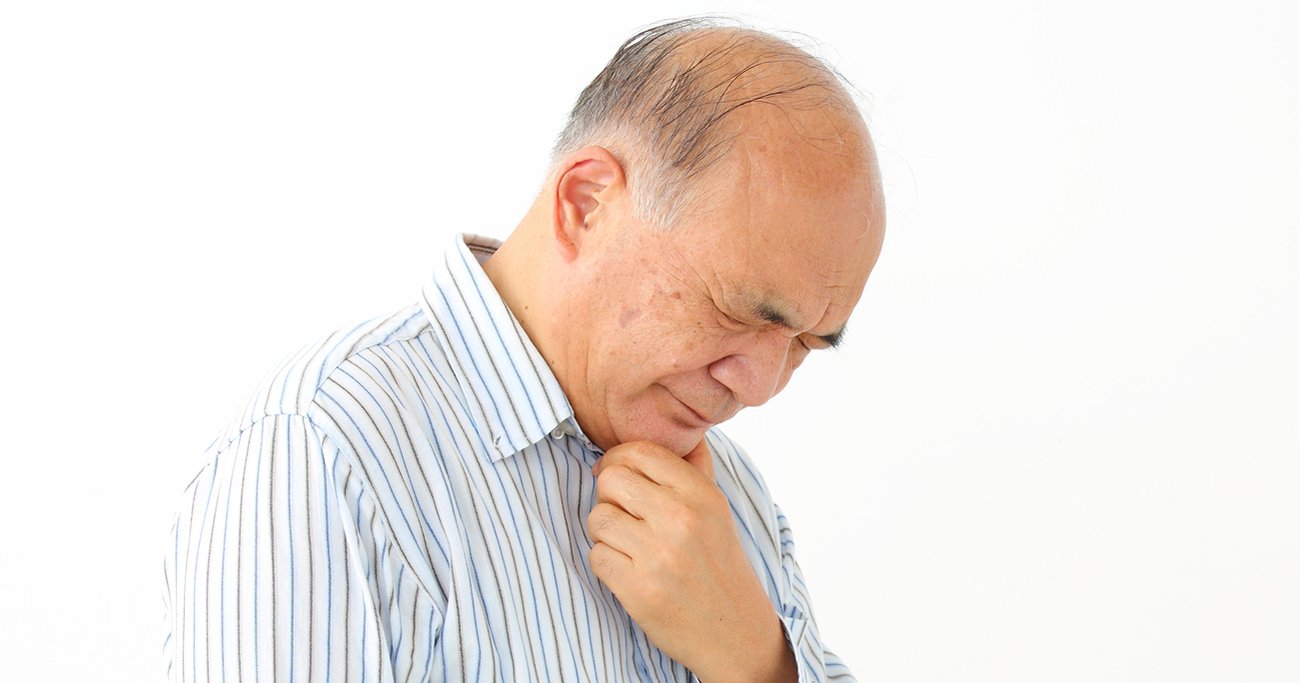 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
定年前後の500人以上にインタビューを続けてきた楠木新さん。豊かな時間の使い方をする人もいれば、「このまま死ぬのは、やりきれない」と吐露する人もいたと言います。後悔する人の共通点とは何か、ジャーナリストの笹井恵里子さんが取材しました。(著述家、元神戸松蔭女子学院大学教授 楠木新/構成 ジャーナリスト 笹井恵里子)
「こんな退屈な日々が続き、
このまま死ぬのはやりきれない」
私は、この10年間、定年前後の500人以上にインタビューを続けてきました。じっくり一対一で話を聞くこともあれば、図書館や書店、大型ショッピングセンター、スポーツクラブ、スーパー銭湯、カラオケ店、喫茶店などで声をかけることもあります。
例えば喫茶店のモーニングでは、「最近リタイアされたのですか?」と聞くと、「そうです。昨年退職して時々ここに来ています」「××の店ではおかわりまではできるが、こちらの店のほうが安いから」などと、簡単なやりとりができます。
そういった取材を通じてわかったことは、定年後の環境にスムーズに移行できない、何をしてよいのかわからないと戸惑う人がかなりの割合を占めます。
会社員時代からゴルフや釣りを楽しみ、「定年後は存分に遊ぶんだ!」と意気込んでいても、数週間もすれば興味を失ってしまいやすいです。「やらなければならないこと」の合間に気分転換でやることと、「自分の好きなこと」とは本質的に異なっているからです。
定年後の自由時間がどれほどあるのか、意識したことはあるでしょうか?
自由になる時間が1日11時間程度だとして、〈11時間×365日×15年(60歳から74歳まで)〉で合計約6万時間にものぼります。「74歳まで」としたのは、いわゆる後期高齢者に該当する75歳までは心身ともに健康な人が多いからです。
定年後の60歳から74歳までが、人生で最も裁量のある時間を持てる時期なのです。この期間を私は“黄金の15年”と呼んでいます。
もちろん75歳以降も健康を維持できれば、自由時間はさらに増えます。
65歳時点の平均余命は、男性で20年、女性で25年。男性であれば平均85歳まで生きる計算になりますから、健康度合いを加味し、75歳から84歳までは自由時間が半分になると仮定して〈1日5・5時間×365日×10年〉で約2万時間に。
黄金の15年の自由時間と合わせると、トータル約8万時間にもなります。女性の場合には寿命が長い分、さらに1万時間程度の自由時間が追加されます。
8万時間がどれほどの時間か。厚生労働省の発表によれば、年間総実動労働時間は2000時間に届いていません。仮に20歳から60歳まで40年間勤めたとして、総労働時間は8万時間に達しないのです。つまり、定年後は今までの全ての労働時間よりも長い自由時間があります。
そのため、この長い自由時間を前に立ち往生してしまう人もいます。私がかつて勤めていた会社の先輩は「こんなに退屈な日々が続き、このまま死んでしまうのかと思うと、やりきれない」と話していました。一方で豊かに時間を使っている人もいます。この両者の差は大きい。「人生は後半戦が勝負」だと感じます。
そこで、定年後に後悔する人の共通点を挙げましょう。







