
楠木 新
定年前後の500人以上にインタビューを重ねてきた楠木新さん。老後も「人に恵まれる人」と「孤立する人」では、顔を見れば一発でわかる決定的な「差」があるという。ジャーナリストの笹井恵里子さんが話を聞いた。

AIを「活用できる人」と「置いていかれる人」の決定的な違い
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第18回は、「顔」にまつわる落語の噺から、未知のものに対する向き合い方について考えます。

定年前後の500人以上にインタビューを続けてきた楠木新さん。豊かな時間の使い方をする人もいれば、「このまま死ぬのは、やりきれない」と吐露する人もいたと言います。後悔する人の共通点とは何か、ジャーナリストの笹井恵里子さんが取材しました。
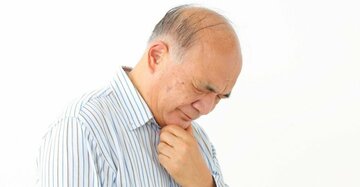
大人になってからも「気の合う仲間」ができる人、顔を見れば一発でわかる決定的な特徴
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第17回は、人間関係の始まりにおける「顔」の役割について考察します。

定年前後の500人以上にインタビューを重ねてきた楠木新さん。老後も「人に恵まれる人」と「孤立する人」では、顔を見れば一発でわかる決定的な「差」があるという。ジャーナリストの笹井恵里子さんが話を聞いた。

一緒に働いているのに心がバラバラ…仕事仲間との距離が一気に縮まる「3つの質問」とは
現在は著述家として活動している楠木新さん。大学卒業後は生命保険会社に入社し、休職期間を含めて60歳の定年まで「会社員」として勤務していました。その経験や、これまで取り組んできた「働く人」への取材を踏まえて「コミュニケーション」の真髄について語ります。

「運を引き寄せる人」が毎日やっているたった1つのシンプルな習慣とは?
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第16回は、楠木さん自身も「顔」によって見出された体験をひも解いていきます。

50代で会社を辞めて「うまくいく人」は何が違う?転身でチャンスが広がる人の共通点とは
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第15回は、楠木さん自身の「人生の転機」を振り返りながら、会社員から独立して「いい顔」をしている人の秘密について考察します。

14
「自分にいい影響を与える人」を見つけるコツ、たった1つの注目ポイントとは?
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第14回は、自分に好影響を与える人物を探すアンテナとして“いい顔”を活用する術について論じます。

13
「話した覚えないのに…」個人情報も、上司の悪口も筒抜け!?すごい「新技術」とは?
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第13回は、AI時代の顔認証技術が向かう先と、そのリスクについて考察していきます。

12
初対面の男女でも会話が盛り上がる「魔法の5文字」とは?
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第12回は、コミュニケーションにおける「いい顔」について、考察していきます。

2024年度に「ダイヤモンド・オンライン」で会員読者の反響が大きかった人気記事ベスト10をお届けします! 第2位はこちらの記事です。
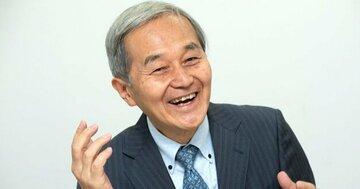
11
三島由紀夫も驚いた、遠藤周作が「狐狸庵」を名乗った理由、 「もう一つの名前」で広がる人生の可能性
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第11回は、いくつかの「顔」を使い分けることで、生き方を楽にするコツについて考察していきます。

10
藤井隆氏と濱田マリ氏に共通する、「聞き上手」になるためのシンプルな方法
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第10回は、コミュニケーションにおける機能的な「顔」の使い方について、持論を展開していきます。独自の視点から導き出した、聞き上手になる方法とは?

9
転身後に「収入が減っても満足」と言い切れる人が持つ共通点とは?
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第9回は、中高年以降に充実した毎日を過ごす「いい顔」を育むヒントについて、ビジネスでの経験を元に考察していきます。

8
定年後も「昔の名刺や肩書」にこだわる人が気付かない、価値ある人脈の作り方
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第8回は、「顔」よりも肩書きや役職が評価される企業風土がもたらす弊害について論じます。

7
警察官が見当たり捜査で注目する「顔のパーツ」年をとっても変わらないのは?
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第7回は、同一人を確認する“身分証明”としての「顔」の役割について考察します。

定年前後の500人以上にインタビューを重ねてきた楠木新さん。老後も「人に恵まれる人」と「孤立する人」では、顔を見れば一発でわかる決定的な「差」があるという。ジャーナリストの笹井恵里子さんが話を聞いた。

6
日本にこんな博物館があったとは!頭蓋骨がズラリと並ぶ「シャレコーベ・ミュージアム」に行ってみた
「生き方や感情は顔つきに現れる」と言う著述家の楠木新さん。多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。連載『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第6回は、数々の頭蓋骨が展示された「シャレコーベ・ミュージアム」を筆者が訪れ、体験したことや感じたことをお届けします。

5
マクドナルド「AI広告の美少女」はなぜ「不気味の谷」を超えられなかったのか?
「生き方や感情は顔つきに現れる」と言う著述家の楠木新さん。多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。連載『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第5回は、最近話題の生成AIが創り出す「顔」の功罪にアプローチします。
