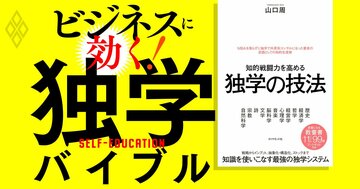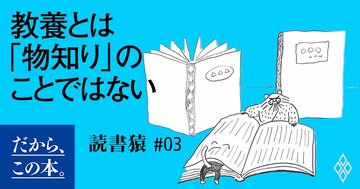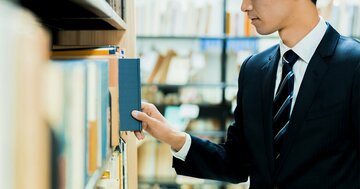『独学大全──絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法』著者の読書猿さんが「勉強が続かない」「やる気が出ない」「目標の立て方がわからない」「受験に受かりたい」「英語を学び直したい」……などなど、「具体的な悩み」に回答。今日から役立ち、一生使える方法を紹介していきます。
※質問は、著者の「マシュマロ」宛てにいただいたものを元に、加筆・修正しています。読書猿さんのマシュマロはこちら
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
[質問]
未熟な質問で恐縮ですが、「法律に書いてないことは何をやってもいい」を論破していただけないでしょうか。「いやいや、それは間違いだろ」と自分で納得できる理由をちゃんと持っておらず、それが勉強できる参考書も教えていただけないでしょうか。
「法律に書いていないけどやっちゃいけないこと」がないと法律が生まれません
[読書猿の回答]
まず、その法律はどこから来たのか、という話があります。
私達の社会では時々「法律が追いついてない」という言い方がされることがあります。
これは、問題のある行動が行われていてなんとかすべきという声が高まっている(つまり「やっちゃいけない」)のだけれど、それを禁止する法律がまだできていない(だから法律をつくるべき)という状態です。
もしも「法律に書いてないことは何をやってもいい」のが本当だとしたら、「法律が追いついてない」なんて状態はあり得ず、「新しい法律が必要だ」という話にもならないことになります。
同じことは、現行の(つまり過去に作られた)法律についても言えます。その法律が必要だとして作られたのは、「その時点ではまだ法律に書いてないけれど、やっちゃいけないこと」があったからです。
「法律に書いてあるからやっちゃいけない」のではなく、「やっちゃいけないこと(なのにやる奴がいて困る)だから法律として定めた」のです。
「やっちゃいけない」というのが先行しないと、そうした法律をつくることができません。
これを別の言い方で言い直すと、「やっちゃいけないこと」は、現行の法律よりも広い(「やっちゃいけないこと」の一部だけが法律化されている)、ということになります。
法律は、何かを禁止するものばかりではありませんが、分かりやすさのために、限定してお話しました。
もう少し使いやすいように言い直すと、「道徳(社会的規範)は法律よりも広い(道徳の一部だけが法律化されている)」となります。
この考え方は、法律を取り扱う場合の基本のひとつです。
例えば、法律には起こり得るすべての場合を書き込む訳にはいかないので、書かれていない事態について解釈が分かれたとき、どう判断するか。その判断の根拠に「法律に書かれていないけど、やっちゃいけないこと」は参照されます。
あるいは、問題のある法律を批判するとき、「法律だけど、これはあかんやろ」と言うためには、法律の外に「やっちゃいけないこと」がなくてはなりません。
もし政治家やそれに近しい人が「法律に書いてないことは何をやってもいい」などと言い出したら、悪法を作って悪いことをしたい、という無自覚の告白なのかもしれません。
いやむしろ、そういう暴言を言っても「そうだそうだ」と喝采するうっかり者ばかりならワンチャンいけるやろ、と思って上げる、暴言の形をした「観測気球」なのかもしれません。
こういう反社会的な人物も、油断すると選挙に出たり政治家になったりするので、注意が必要です。
以下は蛇足です。
よく知られた話ですが、法律の中に「ヒトを殺してはならない」という文言はありません。
刑法には確かに殺人罪の規定(刑199条)がありますが、この条文は直接には、殺人罪とはどういうものかという犯罪の要件と、殺人という罪に対してどれくらいの罰が相当するのか、その刑罰の内容を定めているだけです。
このことを取り上げて「刑法は殺人を禁じていない」と吹き上がるお調子者もおられるかも知れないので、釘を刺しておきます。
刑法は、殺人罪の規定(刑199条)をもって殺人を禁じている、と法解釈学では理解します。つまり、禁じているからこそ、わざわざこのような規定を定めていると考えるわけです。
(井田良『基礎から学ぶ刑事法』〔第2版〕・33頁・一部編集)(井田良『基礎から学ぶ刑事法』〔第2版〕,有斐閣,2002年4月.)
乱暴に言えば、「ヒトを殺してはならない」のは当たり前なので、わざわざ書いてないのです。「ヒトを殺してはならない」ことは当然の前提として、書いてあるのは、どんなものが殺人とされるのか、殺人を犯した人にどのくらいの刑罰を与えるべきか、という規定です。これらが裁判に必要になることは容易に想像できます。
最後に参考文献を。以上のような話は、法学入門のような本(の最初の方)に必ず書いてあることですが、「やっちゃいけないこと」とは一体どういうものなのか、というところから理解するためには、倫理学を学ぶとよいかもしれません。
『ふだんづかいの倫理学』が大体何でも書いてあって便利です。今回お話したような法律と倫理道徳の関係もちゃんと書いてあります。