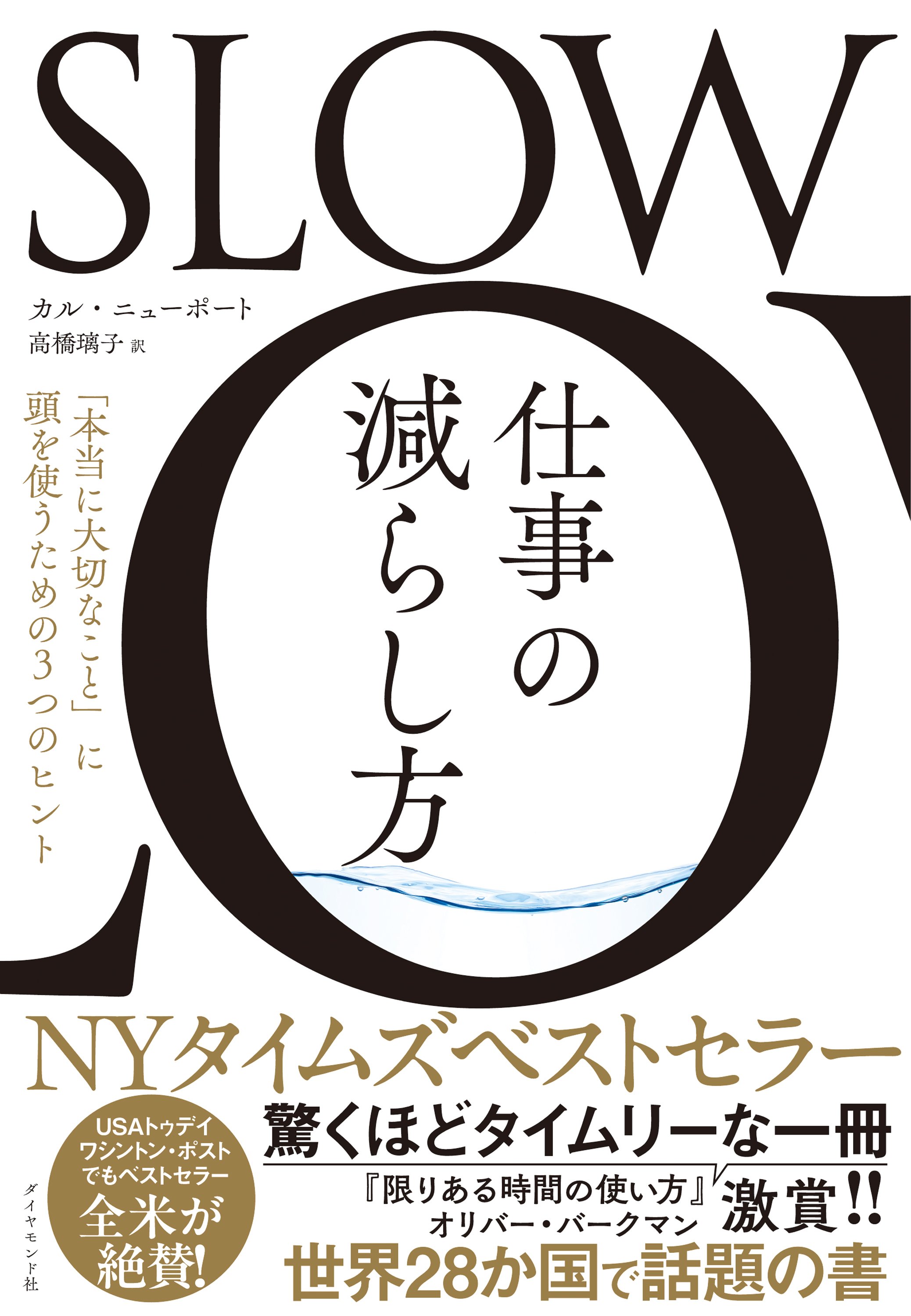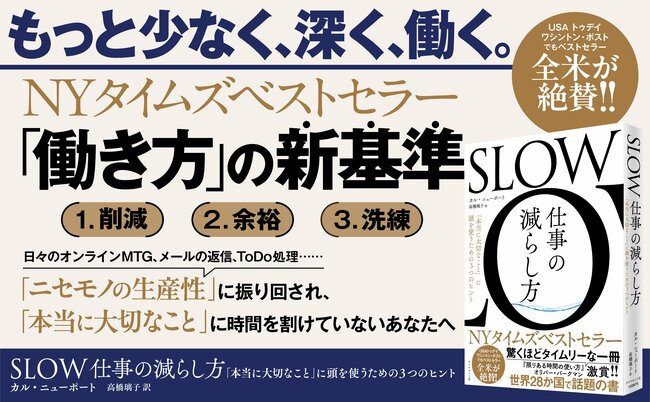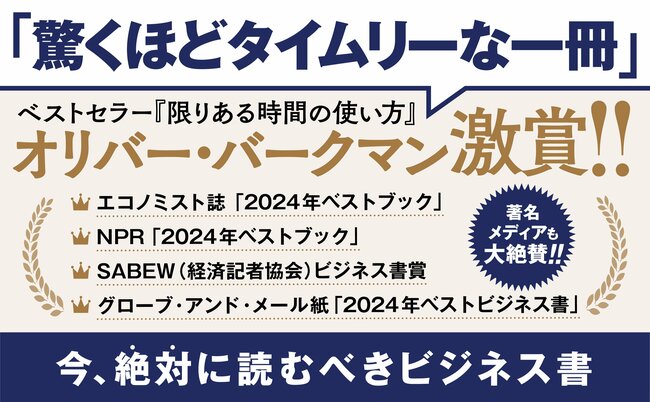やってもやっても仕事が終わらない、前に進まない――。そんな状況に共感するビジネスパーソンは多いはずだ。事実、コロナ禍以降、私たちは一層仕事に圧迫されている。次々に押し寄せるオンライン会議やメール・チャットの返信、その隙間時間に日々のToDo処理をするのが精いっぱいで、「本当に大切なこと」に時間を割けない。そんな状況を変える一冊として全米で話題を呼び、多くの著名メディアでベストセラー、2024年年間ベストを受賞したのが『SLOW 仕事の減らし方』だ。これからの時代に求められる「知的労働者の働き方」の新基準とは? 今回は、本書の邦訳版の刊行を記念して、その一部を抜粋して紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「自動運転モード」なら、ストレスフリーに仕事を進められる
20代の頃、学生向けの勉強術を書いていたときに勧めていたのが、スケジュールの〈自動運転モード〉だ。
毎週同じ曜日、同じ時間に、できれば同じ場所で、決まった課題に取りかかる。たとえば火曜日と木曜日の2限の授業が終わると、そのまま図書館へ行き、同じフロアの同じ席について、英語のリーディングの課題をやる。これは先延ばし癖を防ぎ、意思決定のコストを削減するのに効果的だ。
たいていの学生は、提出期限ぎりぎりにならないと課題に取りかかろうとしない。もう本当にやらないとまずい、間に合わない、という段階になってようやく意志の力を振りしぼって作業を始める人が大半だ。
一方、課題が自動運転モードの設定に入っていれば、やる気を出さなくても自然と課題に取りかかれる。最小限の思考で定期的な作業を実行できれば、脳がストレスフリーになり、大きな目標に注意力を向けられるようになる。
いつもの仕事を、毎週決まった曜日・時間にやってみる
やがて勉強術から仕事術に軸足を移した僕は、もっと仕事の現場に特化したハックに重点を置くようになった。しかし最近になって、自分の事務作業の量が急に増えてきたため、ふたたび自動運転モードを仕事に取り入れている。
やってみると、この作戦は知的労働の文脈でも非常に効果的だった。
学校の課題のかわりに、特定のジャンルの仕事を決まった曜日の決まった時間に割り当てる。フリーランスの人なら月曜の朝を請求書の発送モードにする、大学の教員なら金曜の午後一番に研究プロジェクトの報告書をレビューする、といった具合だ。
特定のタスクを同じ曜日の同じ時間にやることに慣れれば、タスクを実行するために必要な認知コストは激減する。
(本稿は、『SLOW 仕事の減らし方~「本当に大切なこと」に頭を使うための3つのヒント』(カル・ニューポート著、高橋璃子訳)の内容を一部抜粋・編集したものです)