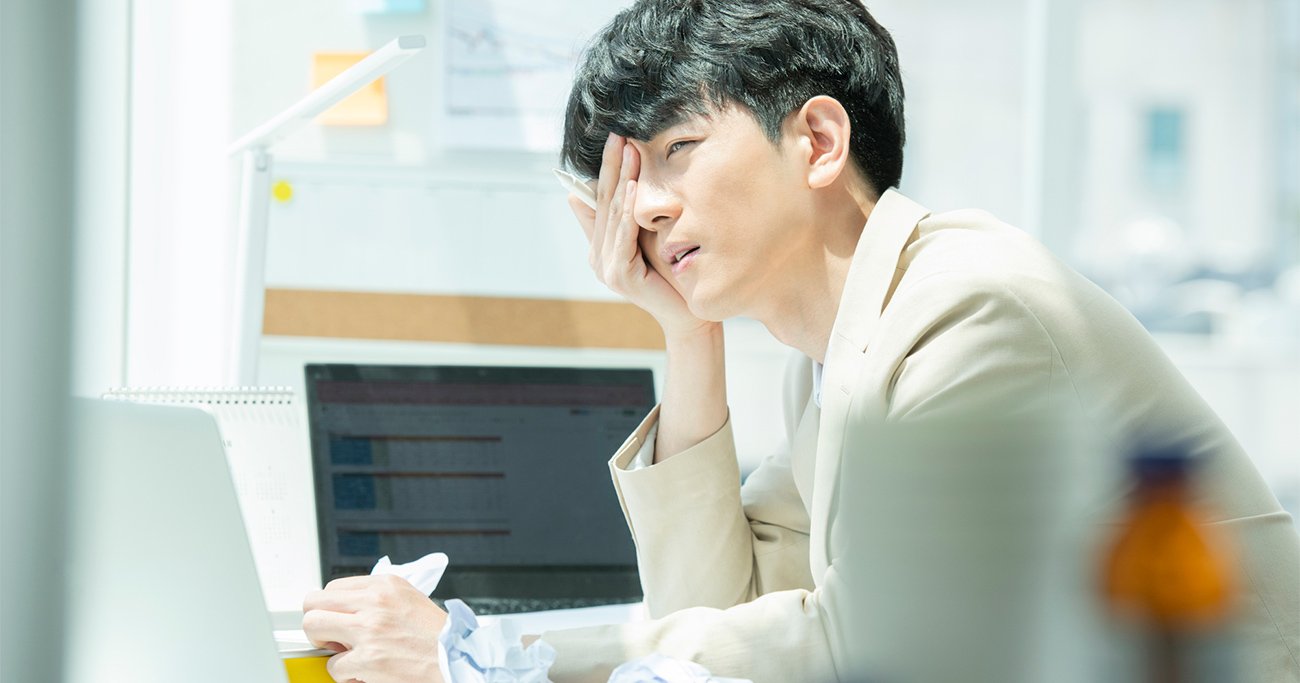 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
4月に新生活がはじまり、ゴールデンウィークを楽しく過ごしたのちに、会社や学校がはじまると体調を崩してしまう「五月病」。本人の怠け心の表れという印象を持たれがちだが、実際には新しい環境での負荷によって心身に不調が出てくる、適応障害の1つだという。適応障害を発症した過去がある産業医の薮野淳也氏が、自身の経験や患者とのエピソードを交えて解説する。※本稿は、薮野淳也(著)、橋口佐紀子(構成)『産業医が教える 会社の休み方』(中央公論新社)より一部を抜粋・編集したものです。
100人に1人以上はいる
メンタル不調の従業員
私は都内の企業で産業医として働くとともに、ビジネスパーソン向けの内科・心療内科のクリニックを開業しています。どちらも、相談に来られる方のほとんどがメンタルヘルスの問題です。
産業医として関わっている企業は、従業員1000人以上の大企業から中小企業、スタートアップ企業まで、規模も業種もさまざまですが、いずれの企業でも、一定数の方からメンタル不調を背景に休職の相談があります。
全事業所の1割以上で、ここ1年の間にメンタル不調が原因で連続1カ月以上休職または退職した労働者がいた、という調査結果(*)があります。この調査では、事業所の規模別にも結果を紹介しています。さらには全労働者のうちメンタル不調で連続1カ月以上休職した労働者の割合、メンタル不調で退職した労働者の割合も調べていて、次のような結果が出ています。
・1000人以上:91.2%/1.0%/0.2%
・500~999人:86.2%/1.2%/0.3%
・300~499人:74.1%/0.7%/0.2%
・100~299人:55.3%/0.6%/0.2%
・50~99人:28.2%/0.5%/0.2%
・30~49人:16.0%/0.4%/0.3%
・10~29人:7.5%/0.3%/0.2%
(*)…令和5年「労働安全衛生調査」より
500人以上では9割前後の事業所でメンタル不調による1カ月以上の休職や退職の労働者がいるわけですから、従業員が多いほど、メンタル不調で休職・退職する人も出てくることが分かります。
そして、全労働者のうち、メンタル不調で1カ月以上休職した人の割合は全体では0.6%、メンタル不調で退職した人の割合は0.2%です。合わせると0.8%なので、125人に1人です。学校でいえば、クラスに1人はいないかもしれないけれど、1学年に1人以上は毎年いるよね、というイメージです。こうした結果は、産業医、主治医としての肌感覚とも合っています。
上司、同僚、カスタマーなど
ストレスは人間関係から生まれる
働く人に増えているメンタル不調ですが、産業医、主治医としてそうした人たちに数多く接してきた経験から、そのほとんどは「適応障害」だと私は考えています。







