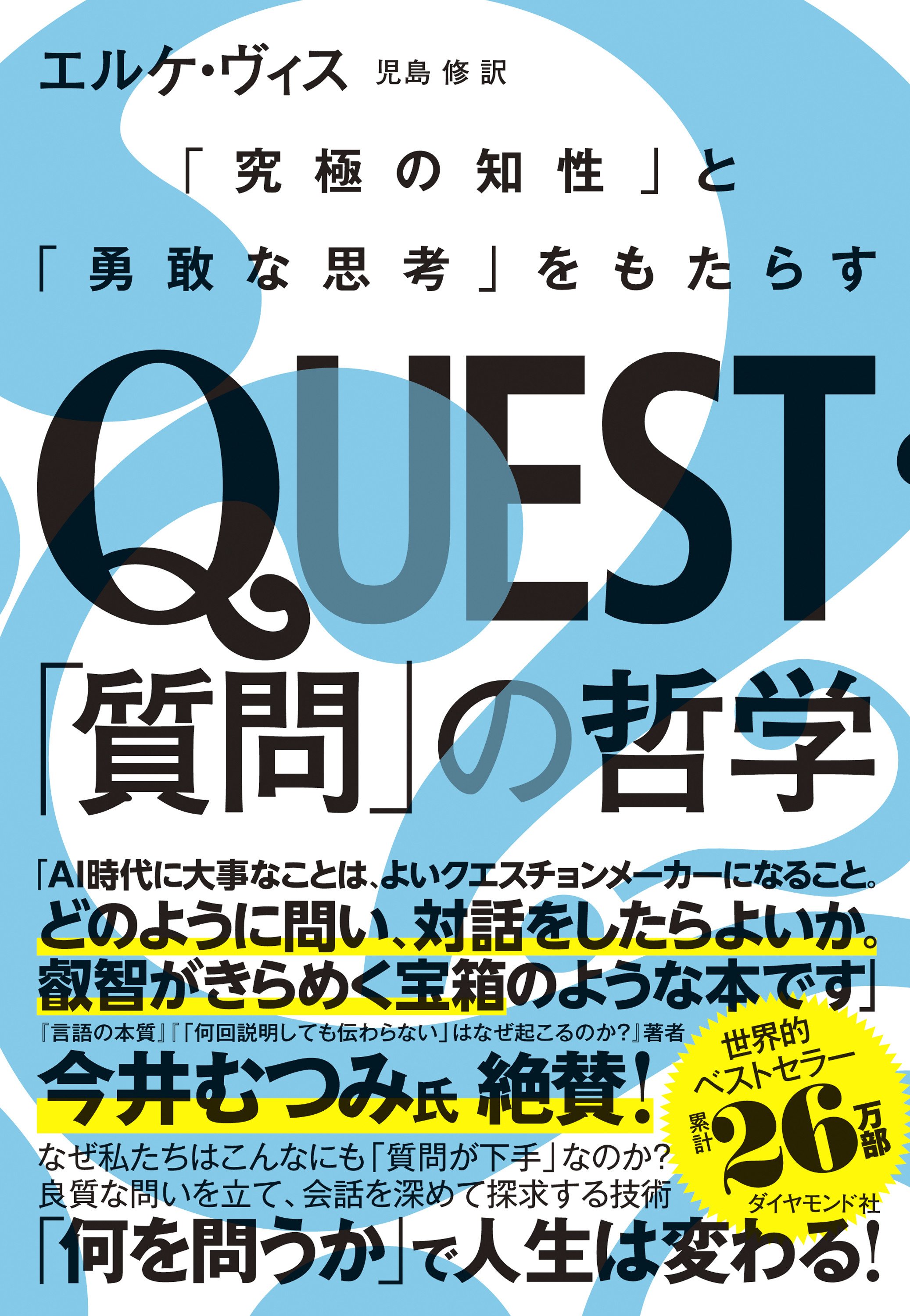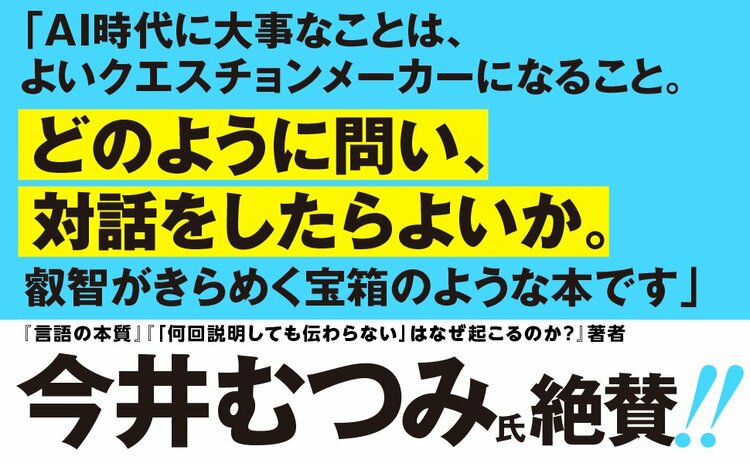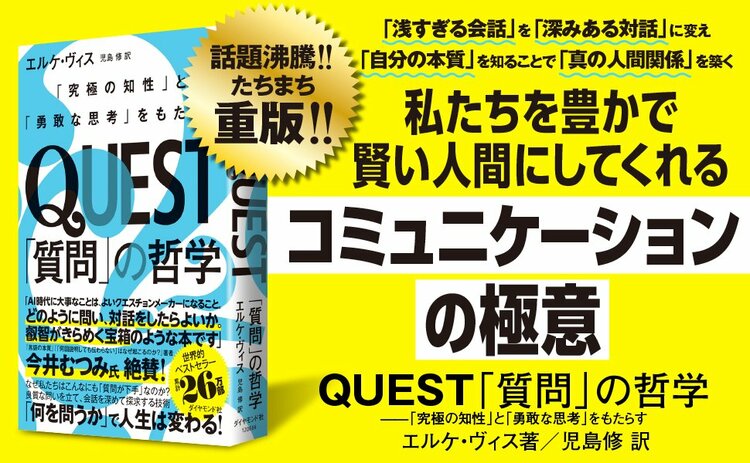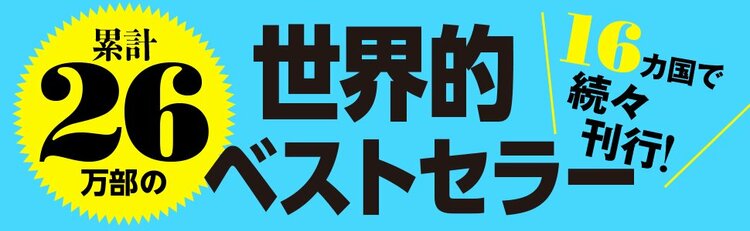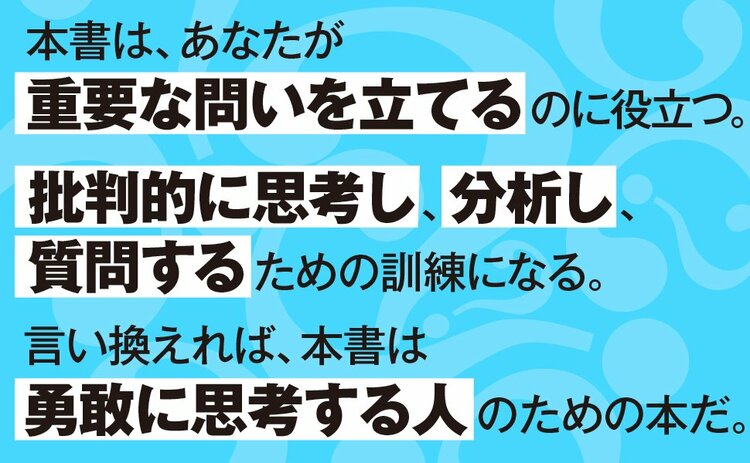「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「質問してもいいか」を事前に確認する
私はスニーカーを履いて表に出ると、現代に生まれ変わったソクラテスのような気分で、会う人会う人に矢継ぎ早に質問を投げかけた。
家族の団らんでも、自分の意見を述べずに相手の考えに疑問を投げかけ、ことごとく反論するような質問をして、みんなの神経を逆なでした。
友人たちは、恋人とのけんか話や職場の愚痴を私に打ち明けても、もはや共感も慰めもしてもらえず、冷酷な反対尋問に耐えなければならなかった。
販売担当者から、「街中の人たちが殺到するような値引き額でこっそりサービスしますよ」と売り文句を言われたら、発言の真偽を問う質問を浴びせた。
誰彼構わず質問攻めにしていたことで、当然ながら周りから鬱陶しがられるようになった。辛かったが、それによって私は学んだ。
自分が思い描いていた、より良い世界は、この方法では実現できそうにない。
私は少しトーンダウンすることにした。憑かれたように質問をするのはやめて、頭を冷やしたほうがいい。そうしなければ、友達が飼い猫のオルレだけになってしまう。
ソクラテスはよく、対話をする前に相手に問題を探求する意思があるかを明確に尋ねた。「質問してもいいかどうか」を事前に確認したのだ。
それには正当な理由があった。鋭い質問をする前に同意を得ておけば、対話は双方の責任のもとでなされることになり、どちらも真実の探求に真剣に向き合える。
この意思確認をせずに突き進むと、ソクラテス式の突っ込んだ質問は、相手にとって警察の尋問のように感じられてしまう。
「このテーマについて質問してもいいですか?」
「この問題を一緒に考えてみませんか?」
「このアイデアをあらゆる角度から見てみたいと思いませんか?」
このように話を切り出すことで、相手がこれから起こること(調査、突っ込んだ質問)についての心構えができる。
それが雑談のような気楽な会話にはならないことを予測でき、参加するかどうかを自分で決められる。
会話に参加するかどうかを自分で決められるという点は、特に重要だ。
突っ込んだ質問をするというあなたの提案に対して、相手が「ノー」と言う機会をもらっていると感じることが大切なのだ。
あなたがいくら望んでいても、相手にとってメリットになると確信していても、相手が積極的に関わってくれなければ議論は無意味になり、抵抗に遭うだけだ。
最初に明確な約束をしておくと、会話の途中でそれを思い出せるという利点もある。
会話の流れが厄介になり始めたり、危険な領域に足を踏み入れ始めたりしたと感じたら、双方に当初の合意がまだあるかどうかを確認できる。
相手はいつでも会話を中断できるし、こちらも相手がまだ会話を続けたいかどうかを尋ねられる。相手が、これ以上の会話を望まないときもある。
人生とはそういうものだ。
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)