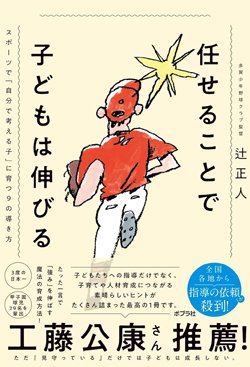こちらがそのスピード感を重視してミスをまったく気にしないので、実際に子どもたちも「失敗した」とは思っていません。そもそも捕れないのが当たり前。それを大前提として、ボールを捕ったときには「おお~!すご~い!」「メチャメチャ上手いなぁ!」「天才や!」などと全力で褒めます。
成功体験というのは、最初はすべて奇跡や偶然です。もしかしたら本人は目を瞑っているかもしれません。しかし、それでも全然構いません。「ボールを捕れた」という成功体験がその子の野球人生における土台になっていきます。
野球好きのお父さん方によくありがちなのは、自分の子どもといきなりキャッチボールをしたりノックをしたりするケースです。私は導入の部分で子どもたちの恐怖心を取り除くことが大事だと思っているので、「いきなりキャッチボールとかは絶対やらないでくださいね」とクギを刺しています。まずは捕る練習と投げる練習を別々に行い、そこで技術を身につけさせながら自信を持たせていくことが重要です。
ちなみに、バッティングは二の次です。もちろん子どもたちはバッティングが好きなのですが、じゃあ「バッティングのほうが喜ぶはずだ」といわれるとそうとは限りません。
バットを振りながら動いているボールを打つというのはそう簡単にできることではなく、最初はほとんど空振りで終わります。守備よりも失敗する確率が圧倒的に高いので、楽しさはそれほどでもないのです。
子どもたちが好きなのは「バッティングをすること」よりも「成功すること」だと思っています。
失敗した子どもに対する声掛けとは
そして、失敗したことを自覚させるのは、試合を経験させたときです。
個人で練習をしているうちは、失敗しても「はい、次」となるので挫折をしないのですが、試合になるとアウトかセーフか、点数が入ったか入らなかったか、チームが勝ったか負けたかという結果が見える。ここで初めて「失敗したんだ」ということが分かるのです。
ここから、子どもたちの心の中では格闘が始まります。
失敗したことが悔しくて、それを乗り越えようと必死に練習する子もいます。あるいは失敗が嫌だからと、最初からボールを捕りに行かなかったりバットを振らなかったりと、後ろ向きに考える子も出てきます。
そういう子どもたちに対して、私たちはまた個人練習で成功体験を積ませていきます。指導者が“奇跡待ち”をして、上手くいったときには「よっしゃ~!いいぞ!」とやはり全力で褒めて自信を持たせていく。その繰り返しによって、心の基礎体力をつけていくわけです。
塞ぎ込んでしまう人も多い世の中だからこそ、スポーツの存在意義というのはこれからもっと大切になってくるでしょう。
「どれだけ失敗しても最後は必ず成功する」
そう考えられる子どもが増えてくれるといいなと思っています。