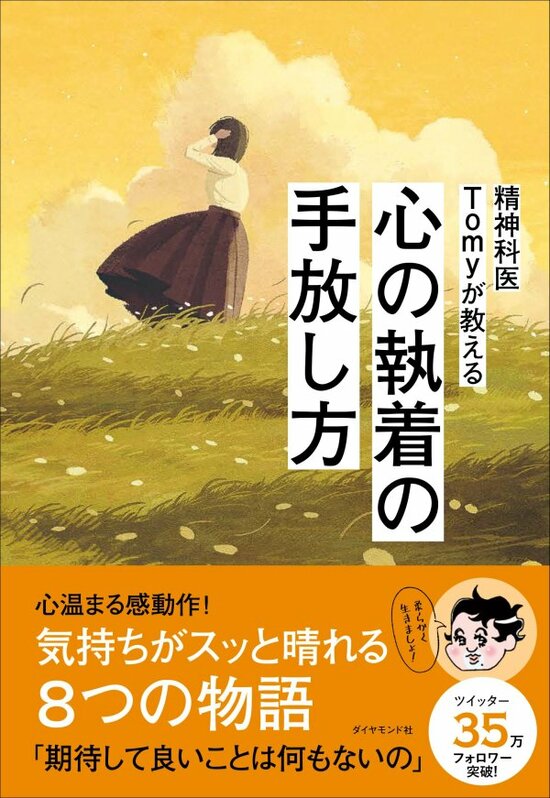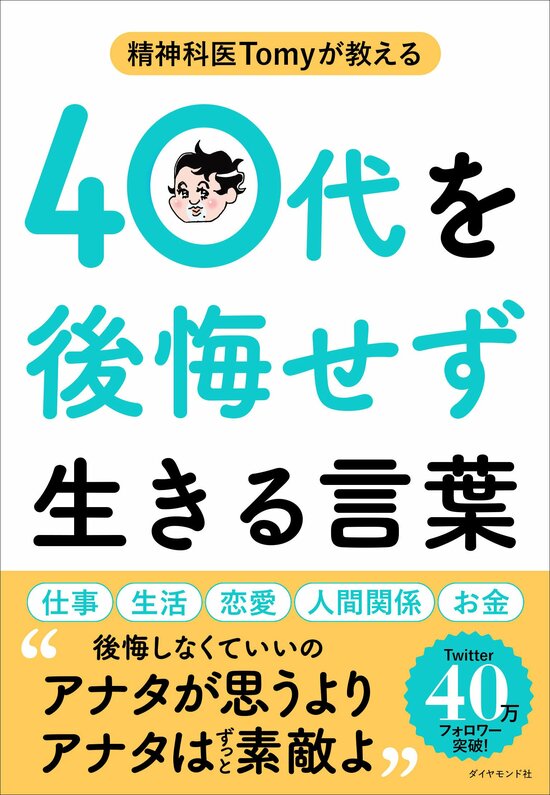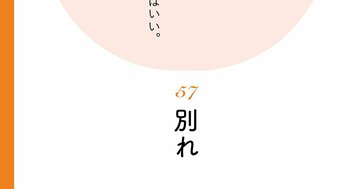自律神経が崩れると、人生が崩れる。眠り・やる気・メンタル…全部つながっていた
誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 30代を悩まず生きる言葉』(ダイヤモンド社)など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
自律神経とは?
「自律神経」は、内臓機能の調整、呼吸、心臓の鼓動など、私たちが意識しなくても体の機能を自動的に調整してくれています。この自律神経には、大きく分けて2つの種類があります。
副交感神経系:リラックスしたり、体を休めたりする時に働く神経。眠くなる時や食事の時など、体が休息モードになっている時に優位になります。
人間の体は、この2つの自律神経がバランスをとりながら、うまく調整されています。このバランスが崩れると、体調不良や精神的な不調につながることがあります。
自律神経の乱れとメンタルヘルス
メンタルの不調は、自律神経の乱れと深く関係していると考えられています。例えば、不眠の原因は、夜になっても交感神経が優位な状態が続いていることにある場合があります。
本来、夕方から夜にかけては、副交感神経が優位になり、体が自然と眠りの準備を始めるのですが、夜遅くに激しい運動をしたり、頭を使いすぎたりすると、交感神経が活発なままになり、眠れなくなってしまうのです。
逆に、朝、起きるべき時間にだるくて動けないといった状態も、自律神経のリズムが崩れていることが原因の一つとして考えられます。もちろん、精神疾患が自律神経のコントロールを難しくすることもありますが、多くの場合は、自律神経のバランスを整えることで、ストレスが軽減し、生きやすくなる可能性があるのです。
自律神経を整えるための生活習慣
自律神経を整えるためのポイントは、「自律神経のリズムに逆らわない生活を送る」ことです。
1. 規則正しい生活を送る
「規則正しい生活」とは、単に「しっかりしましょう」ということではありません。朝、午前中に交感神経が活発になり、活動的に過ごし、午後から夜にかけては徐々に副交感神経が優位になって、体を休めるモードに切り替えていくという、自然なリズムに沿った生活を送ることを意味します。
2. 夕方以降は交感神経を刺激しない
夕方以降は、心身を興奮させるような活動は避け、激しい運動や頭を使う作業を寝る直前に行うのは避けましょう。カフェインの過剰摂取にも注意が必要です。午前中は良いのですが、夕方以降に摂りすぎると、体が覚醒してしまい、眠りの妨げになります。
3. 昼寝は短時間で
昼寝は、副交感神経を優位にしますが、長時間すぎると夜の睡眠リズムを乱してしまう可能性があります。できれば30分以内、理想は15分程度に留め、午後3時以降の昼寝は避けるのがおすすめです。
自律神経は、私たちが意識しなくても体の調子を整えてくれている、とても大切なシステムです。そのリズムを意識し、応援するような形で生活習慣を見直すことは、あなたのメンタルヘルスを支える強力な武器になるかもしれません。
※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿です。