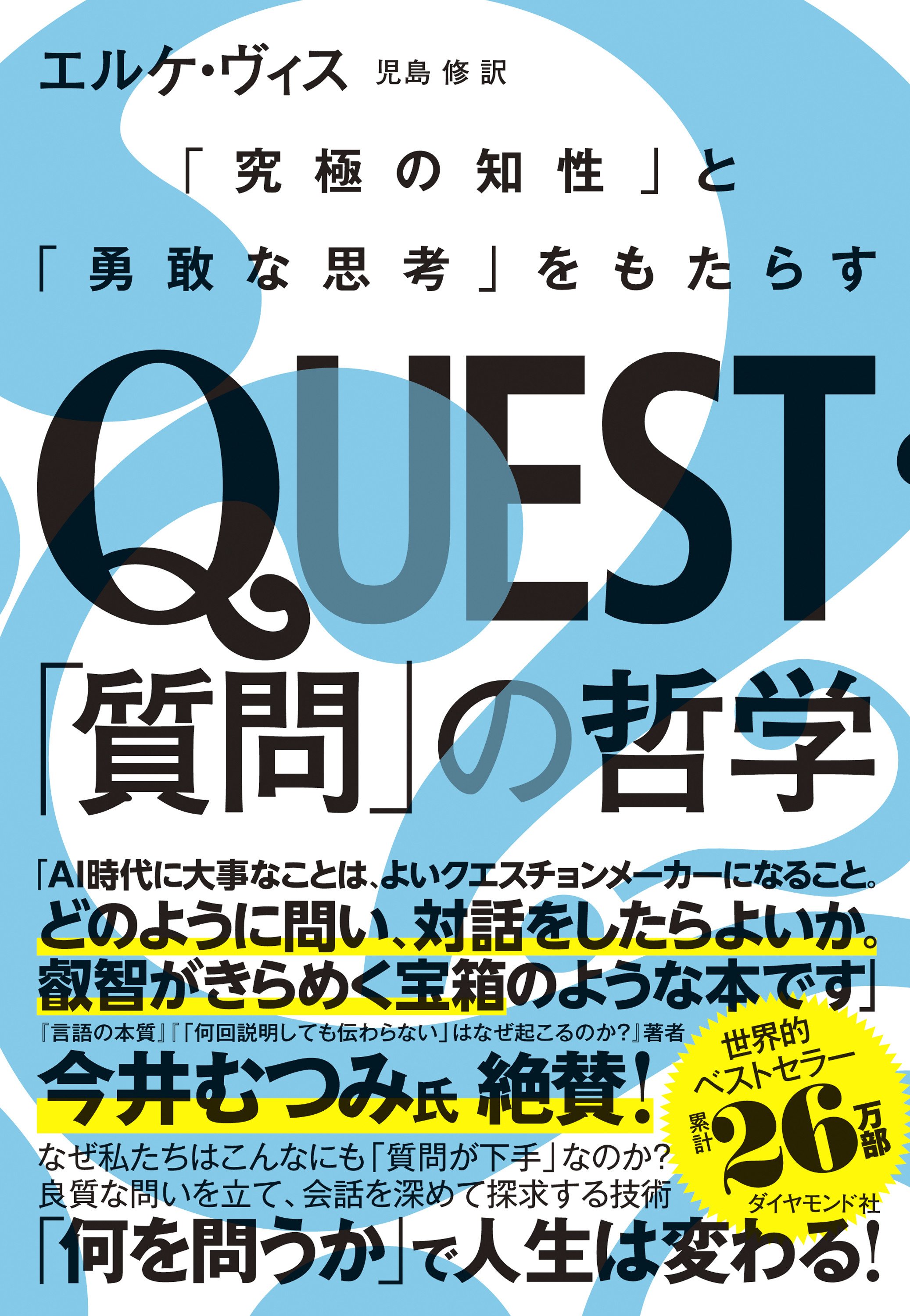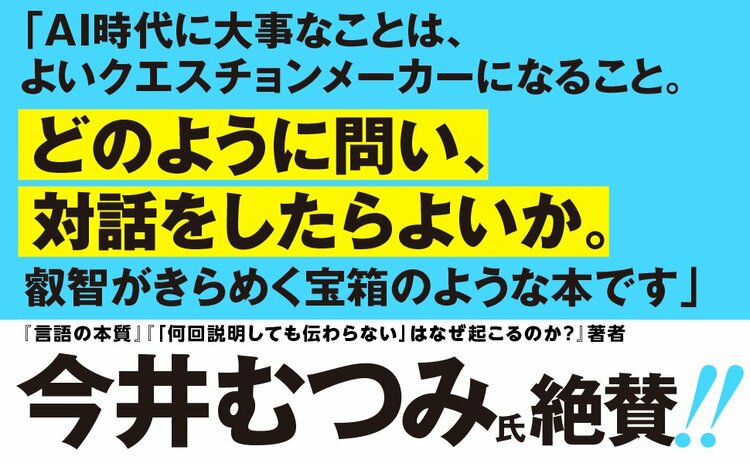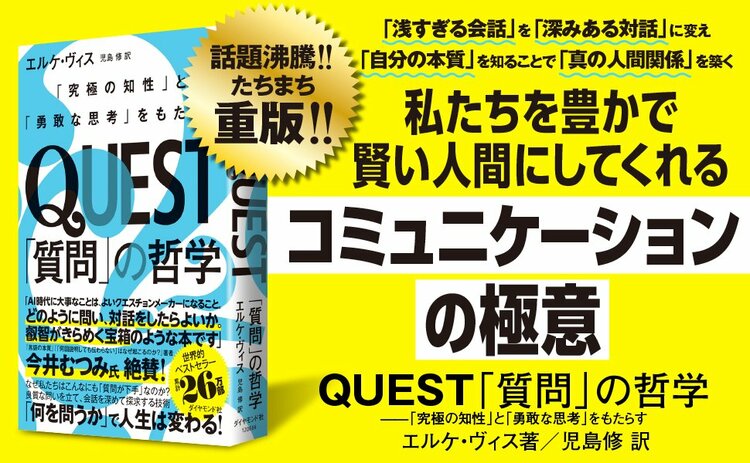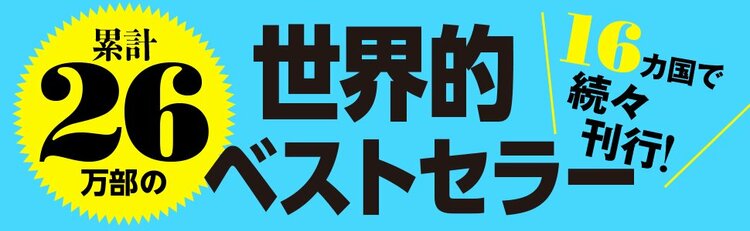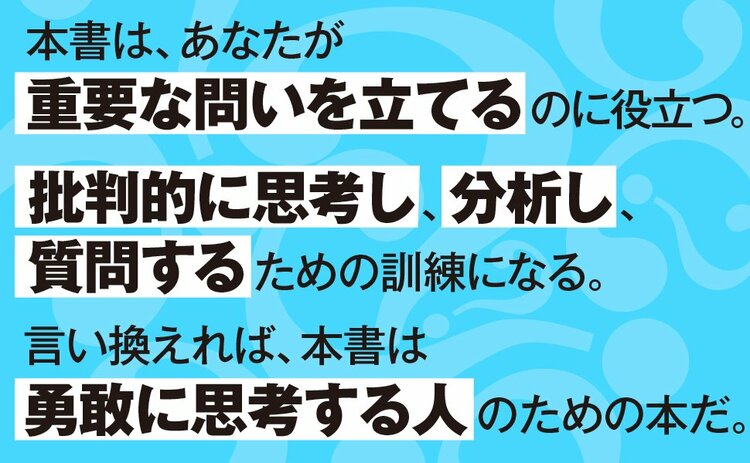「いつも浅い話ばかりで、深い会話ができない」「踏み込んだ質問は避けて、当たり障りのない話ばかりしてしまう」上司や部下・同僚、取引先・お客さん、家族・友人との人間関係がうまくいかず「このままでいいのか」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
世界16カ国で続々刊行され、累計26万部を超えるベストセラーとなった『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』から「人生が変わるコミュニケーションの技術と考え方」を本記事で紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
相手に仮説を押しつけない
質問とは何だろうか? 私たちは「質問」という言葉の意味を知っていると思いがちだ。
しかし、よく考えてみると、私たちが尋ねる質問の多くは、実は質問ではない。
たいていの場合、それは質問を装った、自分の意見や仮定、仮説の表明にすぎない。
「アリスが正しいと思わない?」
「つまり、こういうこと?」
「ベンの言うことにも一理あるよね?」
これらは、質問に見せかけた自分の考えであり、相手に確認を求める仮説である。
注意して観察してみれば、私たちが日常的にしている質問が、いかに本当の質問とは正反対のものであるかがわかるだろう。
オックスフォード英語辞典は、「質問」を「人から情報を引き出すために表現された言葉や文」と定義している。
これは質問とは何かについてのもっともな説明だが、その言葉や文がどのように扱われるべきか、その背後にある意図や相手への影響はどのようなものかについては触れられていない。
実践哲学の考えにしたがって「良い質問の技法」に焦点を当てる本書では、質問の定義は次のようなものになる。
・考え、説明し、研ぎ澄まし、深く掘り下げ、情報を提供し、調査し、つながることへの「招待状」である。
・明確であり、オープンで好奇心旺盛な態度から生まれる。
・常に相手とその話に注目する。
・相手の考えをはっきりさせたり、新しい発見を得たり、新しい視点をもたらしたりする。
・アドバイスをしたり、仮説を確認したり、考えを押しつけたり、意見を共有したり、提案をしたり、相手に「品定めされている」「追い詰められている」と感じさせたりするものではない。
最後のポイントは特に重要だ。
これは当たり前のことのように思えるかもしれないが、私たちが日常的に尋ねる質問の多くは、この「立ち入り禁止区域」に当てはまっている。
パートナーと激しい口論をした話をすれば、親友から「つまり、彼と別れようと思ってるってこと?」と尋ねられ、イタリア旅行の話をすれば、同僚から「1週間もパスタやピザばかり食べ続けたら飽きるでしょう?」と聞かれ、母親の健康が悪化していて心配だと伝えれば、友人から「介護するの? たいへんよ。私もしばらくは自分でやっていたけど─」と言われてしまう。
私たちは無意識のうちに、自己中心的な質問をしてしまう。
気づかないうちに、質問を通して自分のおそれや感情、考え、偏見、欲求を相手の話に投影しているのだ。
(本記事は『QUEST「質問」の哲学――「究極の知性」と「勇敢な思考」をもたらす』の一部を抜粋・編集したものです)