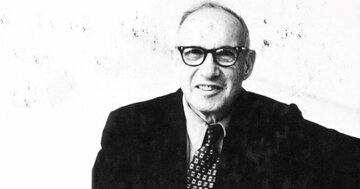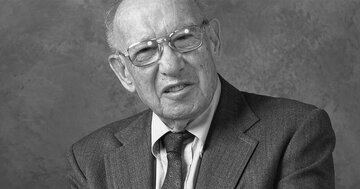Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「マネジメントの父」と呼ばれ、経営学の大家であるピーター・ドラッカー。マネジメントに携わる者ならば、一度は聞いたことがある名前だ。彼が体系化したマネジメントの本質は単なる組織運営ではなく「より良い社会」の実現にあるという。管理職養成の大人気講師である森岡謙仁氏が、5本指に例えてドラッカー流マネジメントの本質を紹介する。※本稿は、森岡謙仁『ドラッカーに学ぶ!管理職 養成講座』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。
マネジメントを体系化した理由は
戦争と恐慌をよみがえらせないため
ドラッカーが生涯を尽くして深化・発展させたマネジメントの目的は、大著『マネジメント』の「まえがき:専制に代わるもの」に書かれています。ドラッカーがマネジメントの体系化を通じて目指していたのは、「組織・チームで成果をあげること」だけではありません。
専制的・権威主義的な社会ではない、1942年発行の『産業人の未来』の中で説いた「自由で機能する社会」「より良い社会」(以下、本記事では「より良い社会」と記述します)を実現するために、「働き方・生き方の基本と原則」を体系的に述べようとしたのです。ドラッカーが語るマネジメントは職位を問わず、経営者、幹部、中間管理職、そして一般社員にとっても有用なものです。
ドラッカーがマネジメントを体系化した目的は、誤解を恐れずに言えば「魔物の再発防止」です。「魔物」とは、1939年発行の『経済人の終わり』の中で彼が戦争と恐慌を指して使った言葉です。ドラッカーは少年時代に第1次世界大戦を、青年時代に第2次世界大戦を経験しました。経済が不況に陥り、専制権威主義国家が戦争をしかけた時代を経験しています。「魔物」を2度とよみがえらせないという信念が、マネジメントを体系化した動機なのです。
マネジメントを支える
3つの普遍的価値観
「より良い社会」を実現するための基本と原則、最も重要なものとして、ドラッカーは価値観をあげています。
一般的に価値観とは、意思決定の基準のことです。何を食べようか、いつ休暇をとろうか、誰と会おうか、など意思決定や判断基準といってもよいものです。「お金のため」「自分のため」「何かに貢献するため」「世界の恵まれない人々に貢献するため」というのも価値観といえるでしょう。
しかし、ドラッカーが説いたマネジメントにおける価値観は、こうした一般的なものとは少し次元が違うものです。それは次の3つの普遍的価値観から成ります。これらは、『マネジメント』をはじめドラッカーの著書に繰り返し登場するところから、この3つをまとめて普遍的価値観と私が定義しました。