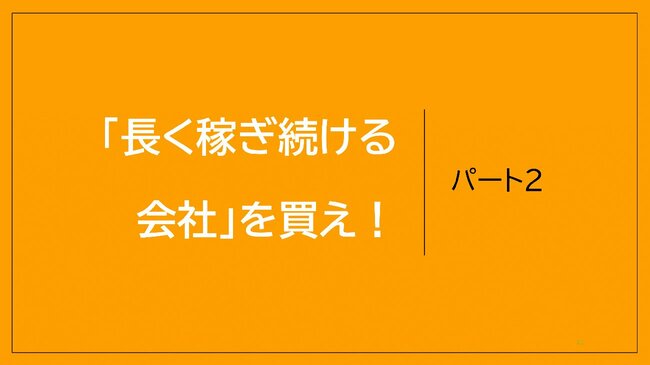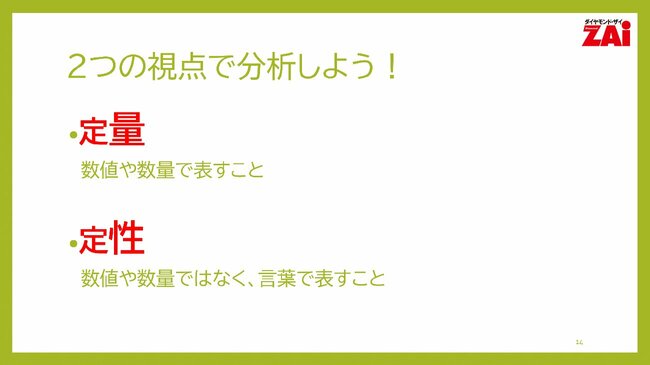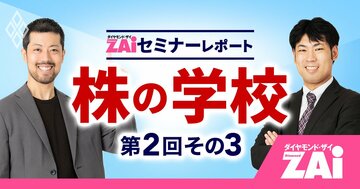一番売れてる月刊マネー誌『ダイヤモンドZAi』が、そのノウハウを駆使して、6回連続のオンライン講座「株の学校」を開校! 株の基礎知識や“7つの儲け方”を、ザイのアナリスト2人が徹底解説した。この記事では第3回の中身を一部お届けする。今回のポイントは、「長く稼ぎ続ける会社」の見極め方。業績表のどこをどのように見れば将来有望な銘柄を見分けられるのかや、ベンチャーなど成長企業ならではの着目点について紹介する。(ダイヤモンド・ザイ編集部)
【※株の学校 第3回の「その1」はこちら】
⇒「NISAでその株は失敗です!」コロナ特需で株価10倍、その後急落…短命テーマの見分け方とは?【株の学校 第3回:その1】
※各種データは講座開催時のもの。
「長く稼ぎ続ける会社」の見極め方!
業績表の読み方を解説

ザイ優待アナリスト 小林大純(こばやし・ひろずみ) 早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現経営管理研究科)修了(MBA)。金融情報サービス会社などを経て2022年6月より現職。日本株アナリストとして各種メディアで活動中。

ザイ配当アナリスト 仲村幸浩(なかむら・ゆきひろ) 立教大学経済学部卒業。日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。証券会社や金融情報サービス会社を経て2023年10月より現職。マーケットアナリストとして各種メディアで活動中。
 小林
小林それでは、ここからはパート2に入りましょう。「長く稼ぎ続ける会社を買え」ということで、パート1の人気が長く続くというのも大事ですが、実績としてこれまでどれだけ長く稼いできたかも重要ですね。
 仲村
仲村長い間業績が良いのには、それ相応の理由があるのでその点にも注目しましょう。
さて、このパートで大切なキーワード2つを先に説明しておきます。長く稼げる会社なのかを分析する際に、「定量」と「定性」という2つの視点で見ていきます。
 小林
小林定量は「量」という字からイメージできる通り、数値や数量で表すこと。この講座の中では主に「業績」の数字からわかることを指しますね。
 仲村
仲村一方で定性は、性質の「性」なので、数字では表せない感覚や質的な特徴を表します。この講座では定義の幅を少し広げて、業績以外で判断できる要素と考えてください。
これから、この2つの視点で分析していくのですが、まずは「定量」の観点で見ていこうと思います。