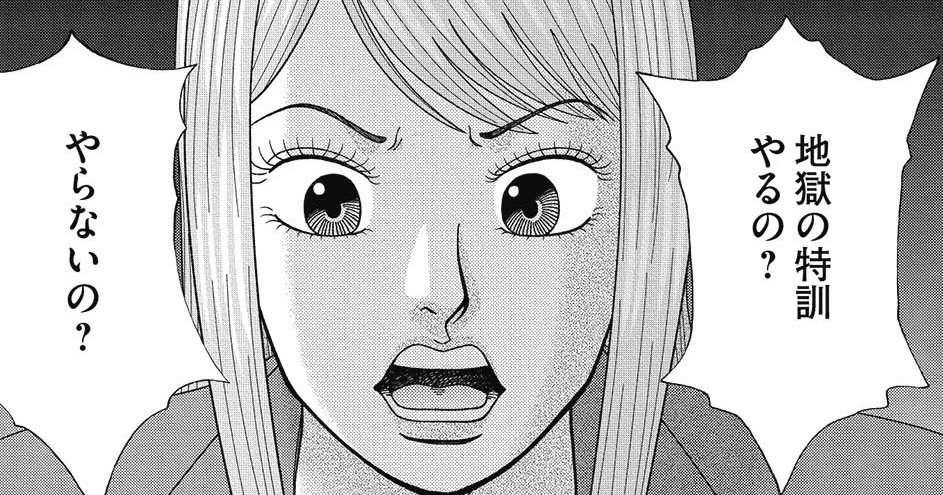 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第49回は、やる気に火がついた瞬間を振り返る。
悔し涙を流した友人
東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒の2人の生徒に、東大専科担任の水野直美は「勉強合宿」を提案する。合宿に乗り気でない2人に対して、水野は自分の「勉強スイッチが入った瞬間」について熱弁をふるう。
ある個別指導塾がCMに使い始めて以降、よく聞くようになった「やる気スイッチ」だが、私は勉強への熱意が湧くようになった瞬間をいくつか覚えている。
まずは、小学6年生の理科の授業である。電気の実験で「電熱線の本数を直列に増やすと、発熱量が減る」ということを示す内容だった。私は塾で習った知識を見せびらかしたくて「電熱線を並列に増やすと発熱量が増える」と発言した。すると担任は黒板の前で実演するように言い、私は前に出て回路を組み、実際に発熱量が増えることを示した。
だが、「なんでそうなるの?」と先生が聞いた時、私は口ごもってしまった。今となっては、当時の担任が答えを知らなかったのか、それともあえて教えてくれなかったのかはわからない。だけれども、「結果だけを覚えてもだめなんだ」ということを深く認識した瞬間だった。
次は、中学2年生の3月だ。コロナ禍で休校になる最後の登校日、「期末テストは、中止です」と担任の先生が言った時のことである。私を含め多くの生徒は喜んでいるか、ほっとしたような表情を見せていた。
ただ、一人の友達が泣いていた。定期テストの点数で私と勝負し続けていた友人だった。2人とも成績はよく、どちらかが学年トップになることもあった。それまでの対戦結果は2勝2敗で、3学期の期末試験で雌雄を決すると意気込んでいた最中だった。
「負け越しはなくなった」と安堵(あんど)する私のそばで、「勝てなくなった」と悔し涙を流した彼の存在により、自分の卑屈さを見せ付けられた気がした。だから、休校期間になって勉強のモチベーションが下がった時は、必ず彼の涙を思い出すようにしていた。
「あいつにだけは負けられない」という安易な競争心は案外役に立つ。もっといえば、「『あいつに勝つ』という目標に対して努力すらできないという事実が、集団の中で露呈されることへの恐怖」なのだ。
本当の勉強スイッチはどこにある?
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
最後は大学受験の時だ。数学、英語、世界史と立て続けに塾の授業があった日のことである。自分の頭をフル回転してギリギリ理解できるかどうかの話を延々と聞かされ、自分の知的好奇心がマックスになったような気がした。
「浪人してでも東京大学に入りたい」と感じ、帰宅して母親にそう言ったことを記憶している。
このように書き並べてみると、前者2つは「恥をかきたくない」や「負けたくない」という感情に基づき、最後は知的好奇心に基づいている。本編でも書かれているように、「恥をかきたくない」という感情から生まれるエネルギーは確かに強い。
しかし、「恥をかきたくない」という欲求を維持するためには、常に自分と比較できる対象がいなくてはならない。あまり親密でない、塾やオンライン環境などでそのような欲求を維持するのは困難な時もあるし、何よりも疲れる。現実世界での利害関係を超越した「ワクワク感」に出会える時が、本当のやる気スイッチなのではないかと思う。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







