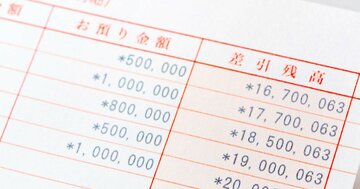【もし赤ちゃんが相続人だったら?】知らないとトラブル多発! 相続とお金のディープな話
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
知らないと絶対損する相続の話
本日は、未成年者がいる場合の相続手続きについてお話ししていきます。
相続人の中に未成年者がいると、通常の相続とは異なる手続きが必要になります。未成年者がいる場合の相続手続きの基礎知識を徹底的に解説していきます。
超基本。遺産分割の2つのルール
まず、相続人の中に未成年者がいる場合の手続きを紹介していきますが、その前に、まずは遺産分割の2つのルールについてお話しします。
亡くなった方の遺産をどのように分けるかは、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」でルールが分かれます。
遺言書がある場合は、その内容通りに分けます。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って「遺産分割協議」で分け方を決めることになります。
ただ、相続人全員で話し合おうと思っても、未成年者、たとえば赤ちゃんが相続人にいた場合は、自分で内容を理解して話し合うことができませんよね。じゃあ、こういった時にどうすればいいのでしょうか。
まず大原則として、未成年者が相続人にいる場合は、親権者が代理人として遺産分割協議に参加することができます。
知らないと絶対困る! 「特別代理人」とは?
今回、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと赤ちゃんだったとしましょう。お父さんが亡くなって、お母さんが親権者である場合ですね。この親権者が未成年者の代理人として協議に参加する、これが原則になります。ここで重要なのが「利益相反」です。
この赤ちゃんの代理人としてお母さんが協議に参加しようとすると、お母さんが多く相続すれば、赤ちゃんの取り分は少なくなる。逆に赤ちゃんが多く相続すれば、お母さんが少なくなる。こういった関係のことを「利益相反」と言います。
利益相反がある場合は、親権者は未成年者の代理人になれません。つまり、未成年者と親権者が同時に相続人になっている場合は、親権者は代理人になれないんです。
ここで出てくるのが「特別代理人の選任」です。特別代理人の選任とは、未成年者と親権者が両方相続人になっている場合に、家庭裁判所に申し立てて、第三者を代理人として選んでもらう手続きのことです。お母さんは親権者としても代理人にはなれないので、別の方を選ばなければなりません。この第三者を「特別代理人」と言います。
実際の遺産分割協議書には、お母さんと特別代理人がサイン・実印を押して手続きをします。お母さんの印鑑証明書と、特別代理人の印鑑証明書、この2つを使って手続きを進めていくことになります。この「特別代理人を選ぶ」という手続きが、通常の相続とは大きく異なる点ですね。
「未成年だけど、内容は理解できるので、話し合いに参加したい」はOK?
よくある質問で、「私は現在17歳です。未成年ですが、内容は理解できます。話し合いに参加してもいいですか?」というのがあります。
現在、成人年齢は18歳に引き下げられましたが、17歳・16歳・15歳といった年齢の方が、「ある程度理解できるから参加してもいいのでは」と思われるのも無理はありません。
ですが、これも実はダメなんです。
未成年者が自分でサインした遺産分割協議書を法務局や銀行に持って行っても、特別代理人の押印がないと受理されません。
ですので、17歳であっても、きちんと特別代理人を選ばなければならないんですね。
ここで一つポイントになるのが、18歳の誕生日を迎えてから協議を始めるという方法です。もうすぐ18歳になるという方であれば、成人になってから協議を始めた方が手続きはスムーズです。なお、相続発生時点での年齢ではなく、「遺産分割協議をする時点での年齢」で判断されます。
ただし注意点として、相続税の申告期限は相続発生から10ヵ月以内と決まっているので、そことの兼ね合いが必要になります。
「遺産をこう分けたいです」としっかり伝える
次に、「親権者が同時に相続人でない場合」について。この場合は、利益相反が起きないため、特別代理人の選任は不要です。
例えば、亡くなったお父さんが再婚していて、前の奥さんとの間に子どもがいる、というケース。この場合、相続人は後妻さんと、前妻との娘さんの2人です。娘さんの親権者は前妻さんですが、前妻さんは相続人ではありませんので、利益相反は起きません。この場合は、前妻さんが代理人として協議に参加できます。
ここからは、特別代理人の申し立て手続きについて説明します。申し立ては、未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に行います。費用は、収入印紙800円と連絡用切手のみ。必要書類は次の通りです。
・特別代理人選任申立書
・未成年者と親権者の戸籍謄本
・候補者の住民票など
・遺産分割協議書の案
ここでポイントになるのが、「候補者は家庭裁判所が勝手に決めるのではなく、こちらから申し立てる」という点です。さらに、「遺産をこう分けたいです」という分割案も合わせて提出します。つまり、申し立て前に「誰を特別代理人にするか」「遺産をどう分けるか」という点を、ある程度固めておく必要があります。
申し立てから実際に特別代理人が選任されるまでは、だいたい1ヵ月程度かかりますので、スケジュールには注意してください。
特に相続税の申告が必要な方は、代理人の選任 → 協議書作成 → 申告まで、すべて10ヵ月以内に終えないといけないので要注意です。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の著者による寄稿です)