「『なぜ、そう思うの?』は、絶対にNGです」
「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ?」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ?」「どうして?」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話=「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。
「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」=事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「ありがちなNG質問」について紹介する。(構成/ダイヤモンド社・榛村光哲)
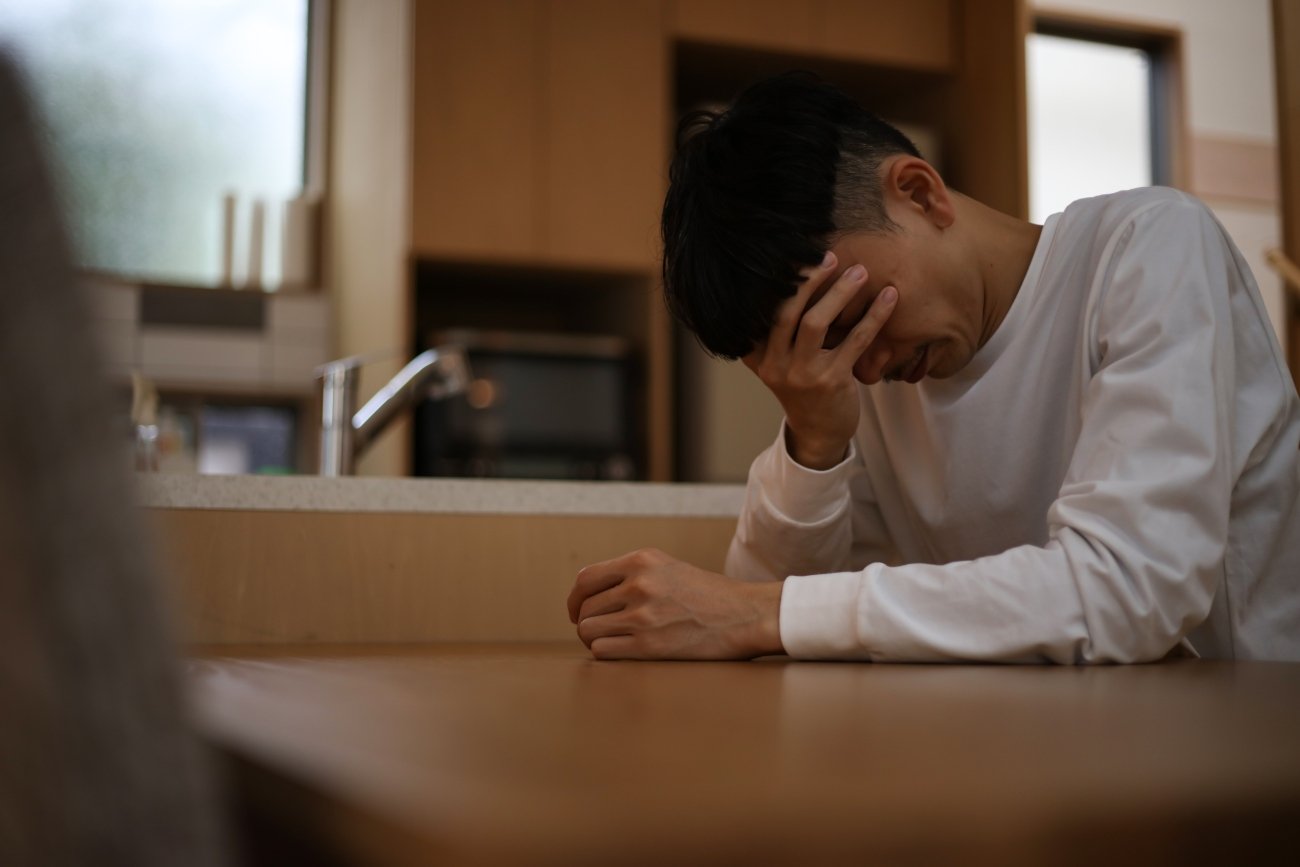 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「なぜ」が引き起こすコミュニケーションのズレ
皆さんは、つい人になぜというふうに聞いてしまってはいないでしょうか。
この「なぜ」という質問は、これまでもお伝えしてきている通り、様々な点でコミュニケーションのズレを引き起こす良くない質問です。
今回は、改めてそれについて紹介していきましょう。
「なぜ」は使ってはいけない
「なぜ」は使ってはいけない1つ目の理由としてお伝えしているのが、相手の思い込みを引き出してしまうということです。
例えば、
上司「なぜそうなったの?」
このように聞くと、相手は自分の頭に残っている曖昧な記憶や、解釈、思い込みなどに沿った「当人の考え」が出てきます。しかしこの質問では、「部下がお客さんを怒らせるに至った事実関係」を正しくキャッチすることは難しいことがあります。
しかし、本書で紹介している事実質問で次のように変えるとどうでしょう。
こうすることによって、相手は事実を思い出すということだけに集中することができます。思い出すだけなので、個人の解釈が入りづらくなります。
一見遠回りのように思えるかもしれませんが、これにより、「なぜか事実が伝わらない」という事象を回避することができるのです。
「なぜ」は言い訳を引き出してしまう
2つ目は、相手の言い訳を引き出してしまうという点です。これは次のような会話例が一番わかりやすいでしょう。
子ども:「違う。今やろうとしてたんだもん」
親:「いいから、さっさと片付けなさい!」
よくあるようなシーンかもしれませんね。
この会話で良くないのが、質問の形式をとってはいるものの、その実中身は「子どもを責めて、片付けをさせようとしている」点です。
「なぜ」という言葉を使っていますが、いわゆる「どうしてやっていないの?」という、詰問調の問いかけになってしまっているのです。
このように、「なぜ」と問い詰めるような毎日が続いて、2人の信頼関係はいい方向に果たして向かっていくでしょうか。
対話は、どちらかが質問し、相手がそれに答えることから始まります。
よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあり、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。
(本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』に関する書き下ろし原稿です)








