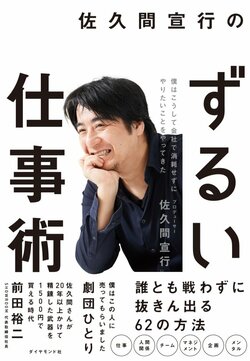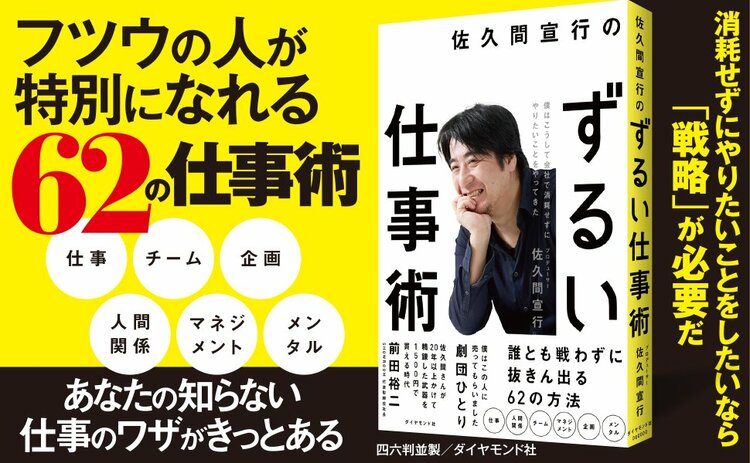「メンタル第一、仕事は第二、というメンタルに関する章が刺さった」「問題児をどうするかなどチームマネジメントが参考になった」……。こんな声が続々と寄せられ、ロングセラーとなっているのが、『佐久間宣行のずるい仕事術』だ。テレビプロデューサーであり演出家、作家、ラジオパーソナリティなど、多方面で活躍する佐久間宣行氏が、独立して初めてまとめた1冊。やりたいことをやってきた、という佐久間氏が語る「誰とも戦わずに抜きん出る方法」とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
その行動はダサい、という空気をつくる
入社したばかりの人、リーダーを命じられて責任が重くなった人、仕事が楽しめない人……。ロングセラーになっているのは、幅広い読者に支持されているからだろう。
「はじめに」では、「入社当時の絶望から20年以上かけて僕が身につけた作戦の数々が入っています」と記されている。
テレビ東京勤務時代、番組プロデューサーとして「ゴットタン」「あちこちオードリー」などヒット番組を多数制作。フリーランスになって以降も、多方面で活躍している佐久間氏だが、意外にも「自分は芸能界もテレビ界も苦手っぽい」とすぐに気づいたという。
そんな彼が「やりたいこと」を実現していくための方法として編み出したのが、もっとずるくなること、だった。
展開されていくのは、誰でもできるのに案外やっている人は少ない「いい仕事」をするための62のヒント。仕事術編、人間関係編、チーム編、マネジメント編、企画術編、メンタル編の6章に、「佐久間宣行の鞄の中身」などファン垂涎の6つのコラムから構成されている。
若者に人気の番組を手掛けてきた番組プロデューサーだけに、読者の中心になっているのは若者かと思いきや、実は必ずしもそうではない。著者と同世代の40代、50代の読者も多いというのだ。惹きつけているのは、チームやマネジメントの章のようだ。
例えば、“「問題児」には先手を打つ”。これは、多くのマネジメント層に響いたはずだ。
チームにチームクラッシャーになりかねない問題児がいるときは、事前の「封じ込め」作戦が効果を上げる。
これは先手を打って、不正解な行動は「ダサい」という空気をチーム内につくってしまうというものだ。(P.135)
正論を説いて叱るのではなく、「こういうことをしたらダサい」と周囲に伝えることで、行動を抑制していく。これには「なるほど」と膝を打つリーダーも多いのではないか。
上司の否定は受け入れにくくとも、周囲からの否定には弱い。まわりから「どう見られているか」を過度と思えるほど気にする若い世代には、極めて有効な方法だろう。
エピソードは「ねつ造」してしまっていい
世代の異なる問題児とどう接するべきか。頭を悩ませている上司世代は少なくない。
明らかな問題行動でも、怒りに任せて叱り飛ばせば、パワハラになりかねない。かといって、真正面から説こうにも、聞く耳を持ってもらえない。古い世代の説教など、ハナから聞く気もない若者もいる。
だから、周囲を使うのだ。
また、これは年代に限らずだが、自己評価やプライドが高く、メンツを重視している人には、「それはカッコ悪い」を先に吹聴しておくことが有効だ。
だが、こうした表現をしても、気づけない人も中にはいる。この文章を書いている私は長く書く仕事をしているが、書かれていることがすんなりと読者に受け入れられるとは限らない。いや、むしろ簡単には理解してもらえない。
とりわけ抽象的な言葉は、読者にはなかなか刺さらない。そういうときに効果を生むのが、具体的な事例だ。具体例があれば、グッと身近なものとして受け止めることができる。腹落ちしやすくなるのだ。
佐久間氏も、このことをよくわかっているらしい。
「嫌なヤツ」の話をねつ造する方法だ。
「前の現場にはこんなことでキレた人がいて、ほんとダサかったし困った」
「あの局には理不尽をまき散らすディレクターがいて、だれにも慕われてないらしい」
架空の悪役やエピソードをでっちあげて、「われわれのチームにはそういう人はいないですよね」と事前の圧をかける。(P.136)
具体的な例は、説得力を持つ。メンバーは同じ轍を踏まなくなり、驚くほど平和な現場になっていくという。
そしてこの方法は、トラブルを避けるときにも応用できる。「こんなトラブルがあった。このチームでは気をつけよう」と伝えておくと、「言わんこっちゃない」と言われないためにも、みんな意識してくれるというのだ。
部下の仕事を簡単に引き取ってはいけない
一見、良かれと思う上司の行動が、実は必ずしもそうではないというヒントも挙げている。“部下の仕事は「引き取らない」”だ。
部下がもたもたしていると、ついつい「あとはやるよ」と引き取ってしまう。すべて任せるより、あとは自分でやったほうがクオリティが上がるからと途中で預かってしまうのだ。
しかし、これはダメだという。
70点くらいの出来で提出したら、「後はやっておくよ」と言ってくれると、部下としては安心だし、「手離れ」のいい仕事になる。正直「ラッキー」と思うかもしれない。僕はそう思っていた。
でも、そういう上司の下では、僕は伸びなかった。
無意識のうちに、手を抜いてしまっていたからだ。(P.141)
これでは部下が、最後の最後まで粘ることをしなくなってしまう。あとは上司が得点を上げてくれるとわかっているから。これでは力はつかない。最終責任を自分が引き取るからこそ、緊張感も生まれるのだ。
そんな覚悟のない仕事では、経験は血肉にならないし、「個」としてのスキルも身につかないと佐久間氏は記す。
受け取ったら面倒くさくても、フィードバックして修正させる。(中略)
フィードバックには、ダメな理由と「どうすればもっといいアウトプットになるか」のアドバイスを添えること。ただ「ダメ」と突き返されても、努力の方向がわからないから、正解の方向性だけは見せて、そこからのディテールは本人に任せるのがいい。(P.142)
手間はかかる。面倒である。しかし、部下の成長に気づくことができる。
部下もいずれ、「面倒くさかったけれど、あのやり方で育てられてよかったな」と思う。そうでなければ、単なる「たたき台製造機」をつくることになってしまいかねないという。
かつて私が取材した著名人が語っていた話を思い出す。
温和で叱ることなどない先輩と、厳しくて叱ってばかりの先輩と、本当はどちらがやさしい先輩なのか。
指摘され、叱られなければ、成長することはないのだ。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。