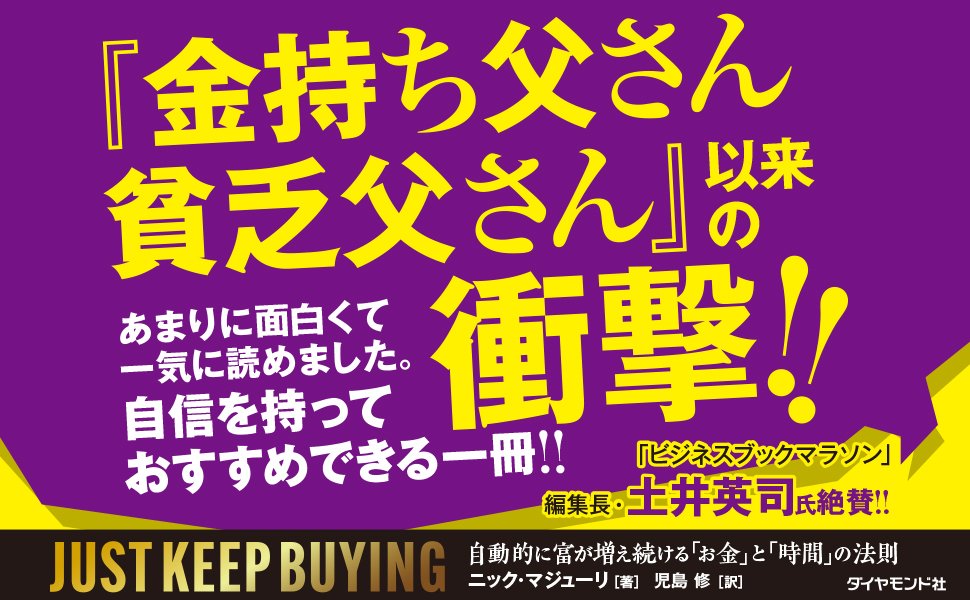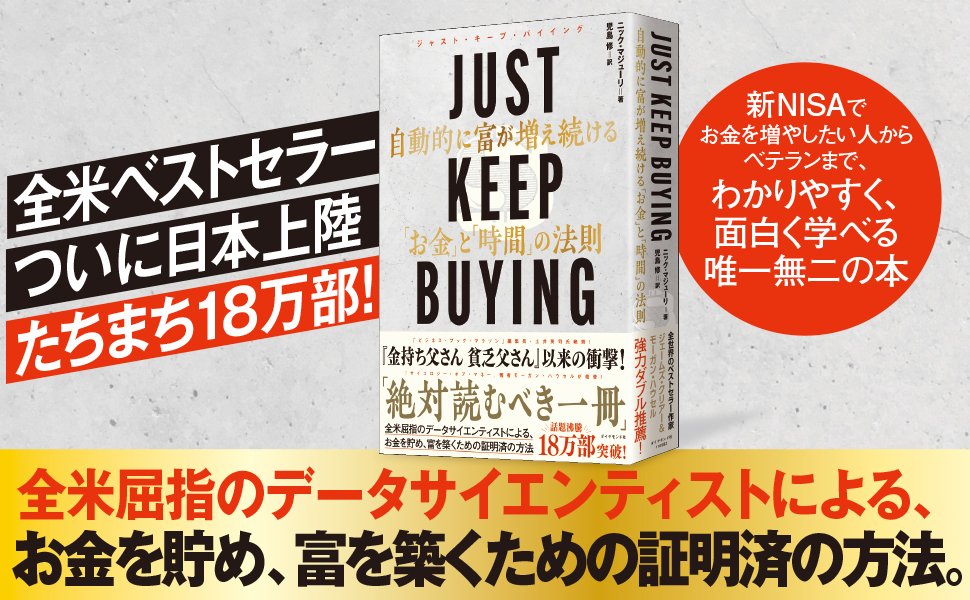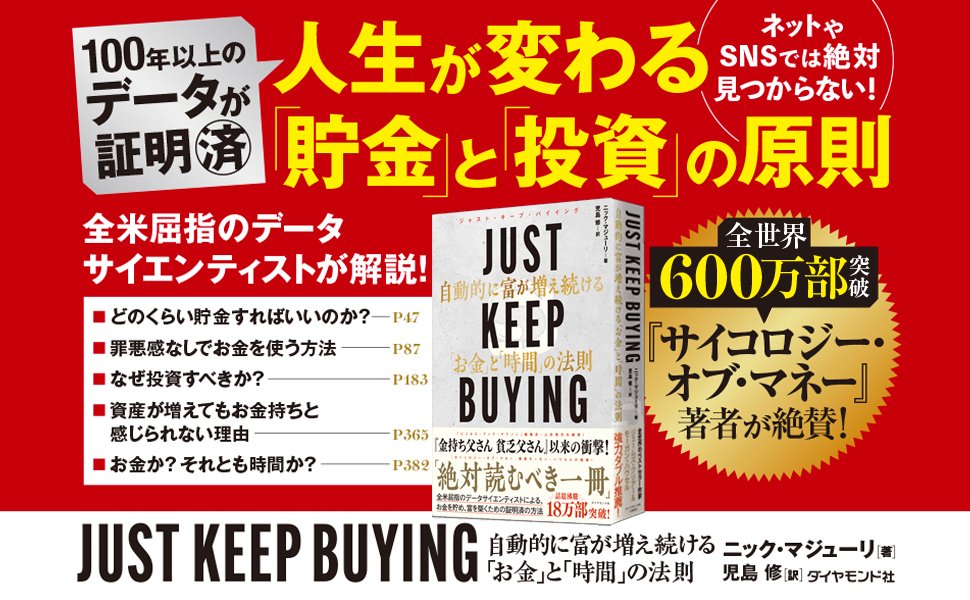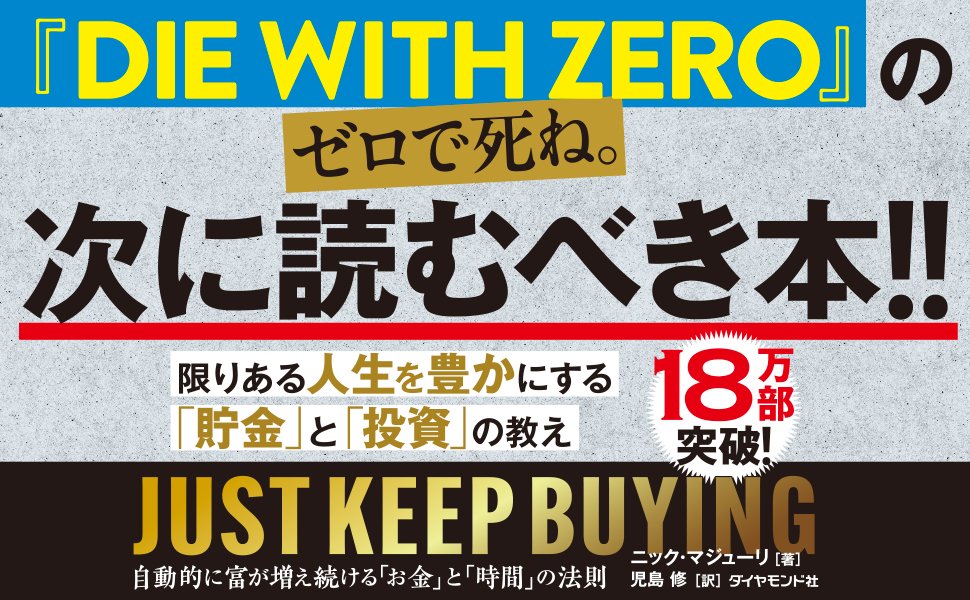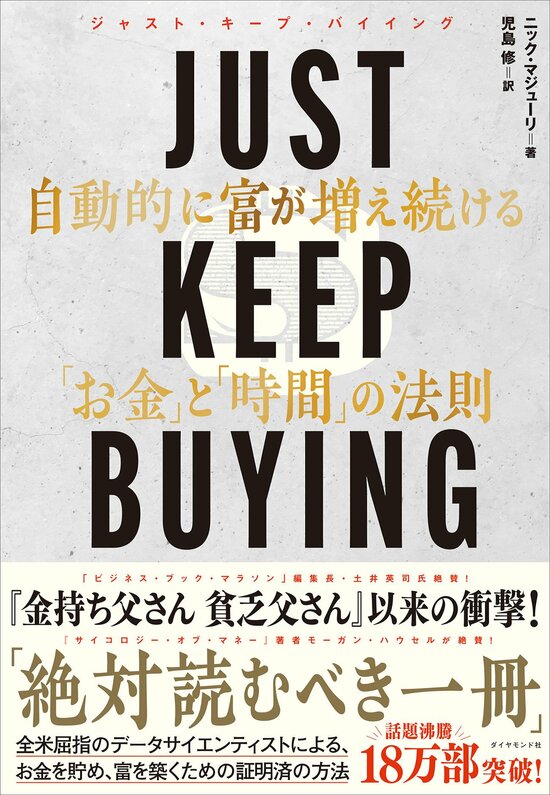昨年から新NISAがスタートした。だが、投資には「不確定要素」がつきものだ。どうすれば不運な目に遭わずに投資で成功できるのか?
今、全国の書店で話題となっているのが、「読むと人生が変わる」「シンプルすぎ最強」「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書!」と絶賛されている全世界40万部のベストセラー『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』(ニック・マジューリ著)だ。前回に引き続き『ストーリーとしての競争戦略』の楠木建氏(一橋大学特任教授)の特別投稿第3弾をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)
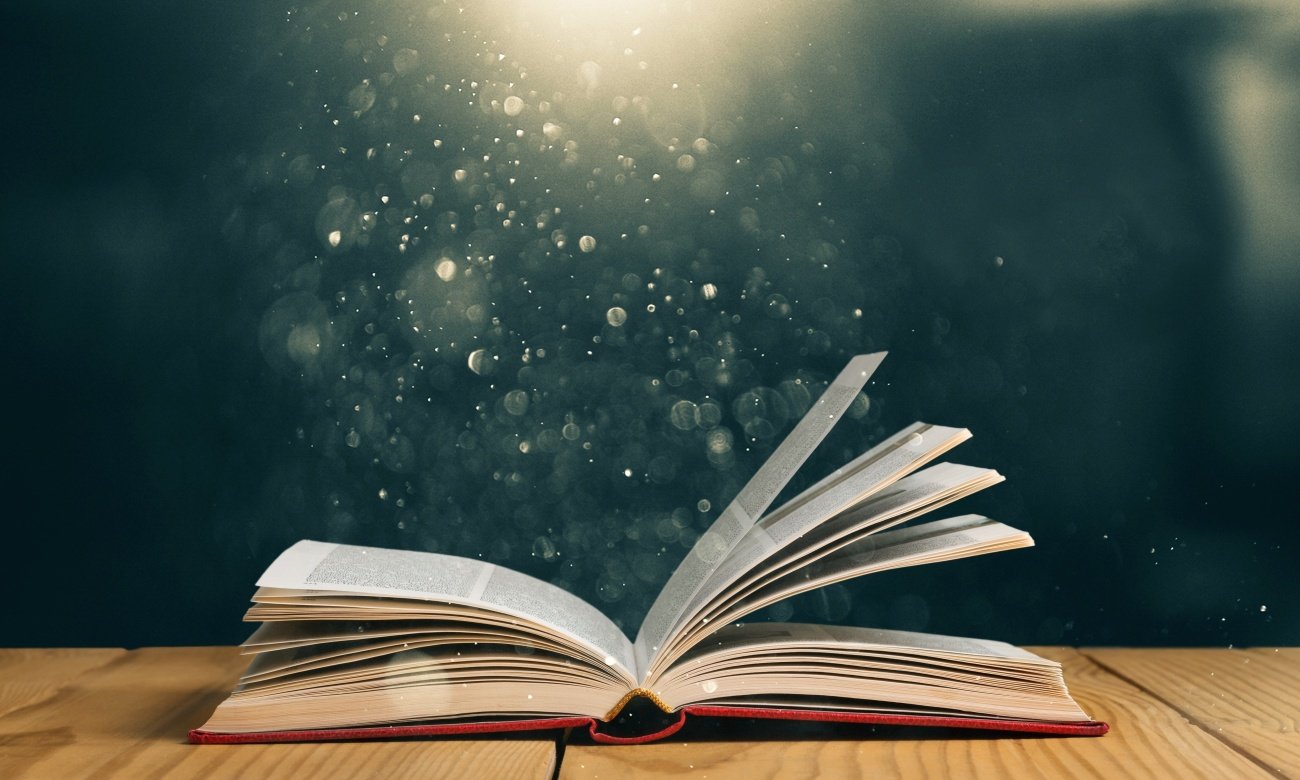 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
節約で貯金を増やすのは可能か?
「貯金=収入-支出」である以上、貯金を増やすには収入を増やすか支出を減らすかしかない。
問題はこの2つのうち、どちらが効果的なのかということだ。
『JUST KEEP BUYING』の著者ニック・マジューリは、広範なデータに基づいて、節約で貯金を増やすのは限界があることを示している。
収入が増えても支出が同じように増えるわけではない。
突き詰めて言えば、貯蓄の王道は収入を増やすことにある。
もちろん、支出の管理も大切だ。
定期的に自分のお金の使い方を見直し、無駄がないことを確認するべきだ。
利用していないサブスクリプションがあれば契約を解除するべきだし、不要な贅沢品には手を出すべきではないだろう。しかし、一杯のコーヒーを楽しむ時間を我慢し続けなくてもいい。
個別株投資はやるべきか?
個別株投資はするべきではない――その金融論的な理由はよく知られている。
個別株投資をしても、専門家を含むほとんどの人は市場全体に投資をするインデックス投資には勝てない。
この主張を裏づけるデータははっきりしている。
世界各国の株式市場について、インデックス運用と個別株投資によるアクティブ運用の結果を比較すると、5年間を対象とした分析では、75%のアクティブファンドはベンチマークとなる市場の指数を超えていない。
この75%は専門のアナリストチームを大勢抱える資産運用会社が運用するファンドだ。
その道のプロがフルタイムで取り組んでもインデックスを凌駕できないのに、私たち個人投資家はそれを上回ることができるだろうか。
しかも、長期的に成功し続ける個別銘柄はごくわずかしかない。
1926年以来、米短期国債を上回る株式の超過リターンを生み出した個別株は実質的にわずか4%にすぎない。この4%の銘柄を選び出すのは至難の業だ。
さらに言えば、優良企業であってもいずれは衰退する。
1950年以来、米国株式市場で取引された2万8853社のうち2009年時点で78%に相当する2万2469社が姿を消している。
幅広い株を保有するインデックス運用のほうが個別株投資で大当たりを引こうとするよりはるかに合理的だ。以上が個別株投資を批判する金融論的な理由である。
個別株投資の「存在論的な難点」とは?
本書が面白いのは、この種の金融論的な議論を別にしても、個別株投資には存在論的な難点があるとしているところだ。
スポーツやエンジニアリングの分野では、能力あるかどうかはすぐにわかる。バスケットボールのシュートや、コンピュータプログラムの作成結果を見れば、能力の判断がつく。
しかし、株の銘柄選びはどうか。その人の力量を判断するには時間がかかる。数年試してもまだ確実なことはわからない。
株の銘柄選びではパフォーマンスとの因果関係を特定するのが難しいからだ。
株価はその人の予想とは全く違う理由で上がるかもしれない。
市場心理が予想と逆に働いたときはどうすればいいのか。買い増しをするべきなのか。
個別株投資では常にこうした問題について自問自答しなければならない。
自分が銘柄選びに長けているかどうかを判断できない。これが個別株投資の存在論的な問題だ。
自分の実力が証明できない分野に挑戦する理由はない。趣味でやるなら問題はない。しかし、趣味でもないのに自分に能力があるのかわからないことに多くの時間を費やす意味はあるのか。
一時的に優れたパフォーマンスを示せても問題はそこで終わらない。
どんな投資家も、保有株の業績が低迷する時期は避けられない。それまでは調子が良かったのに今は不調になった。これは一時的なスランプにすぎないのか、それとも本当に腕が落ちてしまったのか。それは誰にもわからない。
データ分析以上の本書の魅力とは?
自分の技量が判断できない世界では、金融論的な損得を超えて精神的な苦しみがはるかに大きくなる。
一方のインデックス投資は、単純かつ放置できる。個別株投資のように頻繁に株価を気にする必要もない。だから、ほかの重要なことに集中できる。
本書の冒頭には、世界的ベストセラー『サイコロジー・オブ・マネー』の著者モーガン・ハウセルの推薦の言葉がある。
「世の中に優れたデータサイエンティストもいるし、
優れたストーリーテラーもいる。
だが、ニックのように、データの真の意味を理解できる
データサイエンティストでありながら、
説得力のあるストーリーを語れる人はまずいない。
これは絶対読むべき一冊だ」
著者の議論は常にファクトとデータから入るのだが、
最後は人間という存在の本質に戻ってくる。
ここにデータ分析以上の本書の魅力がある。
(本稿は、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』に関する書き下ろし記事です。)
経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)
専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。